生徒会の推薦責任者という大役を任されたものの、「推薦文ってどうやって書けばいいんだろう…」と頭を抱えていませんか。そもそも推薦責任者とはどんな役割なのか、ただ真面目なだけでなく、聞いているみんなの心に残る面白いスピーチでインパクトを与えるにはどうすれば良いのか、悩む点は多いでしょう。
インターネットで生徒会選挙の推薦文で使える例文を探しても、ありきたりなものばかりでピンとこないかもしれません。特に、スピーチ全体をビシッと引き締める締めの言葉や、どうせなら高校の選挙でも通用するような、本格的な書き方のコツを知りたい、というその向上心は素晴らしいです。
この記事では、中学生向けの推薦責任者の例文を豊富に交えながら、あなたの「どうしよう」を「こうしよう!」に変える、具体的で実践的な方法を余すところなく解説します。
- 推薦責任者の役割と推薦文の基本構成
- 聞き手の心に残る具体的なエピソードの見つけ方
- 面白いだけじゃない信頼される推薦文の作り方
- そのまま使える推薦文の例文とアレンジ方法
推薦責任者の例文|中学生が知るべき基本

- そもそも推薦責任者とはどんな役割?
- 推薦文の基本的な書き方4ステップ
- 生徒会選挙で候補者の魅力を伝えるコツ
- 聞き手を惹きつける面白い推薦文のコツ
- 生徒会選挙の推薦文で使える例文を紹介
そもそも推薦責任者とはどんな役割?
生徒会選挙における推薦責任者とは、単に候補者の友だちとして応援するだけでなく、立候補者がどれだけ生徒会役員にふさわしい人物であるかを、全校生徒に向けて公式に推薦し、その信頼性を保証する非常に重要な役割を担います。
なぜなら、立候補者本人が「私はリーダーシップがあります」「みんなのために頑張ります」とアピールしても、それはある意味で当たり前のことです。しかし、普段からその候補者をよく知る第三者である推薦責任者が、客観的な視点から具体的なエピソードを交えてその魅力を語ることで、言葉の一つひとつに重みと信頼性が生まれるからです。言ってしまえば、候補者の「応援団長」であり、その人柄を証明する「証人」でもあるわけです。
主な仕事は全校生徒の前で行う「推薦演説」ですが、その役割は演説だけにとどまりません。候補者が演説で何を話すべきか一緒に考えたり、選挙ポスターのデザインについてアイディアを出し合ったり、朝の挨拶運動に一緒に立って声を枯らしたりと、選挙活動期間中の最も身近なパートナーとして、精神的な支えになることも求められます。
推薦責任者の主な役割・活動内容
- 推薦演説の実施:候補者の人柄、能力、実績を具体的なエピソードと共に全校生徒に伝え、支持を訴える最も重要な仕事です。
- 信頼性の担保:「私が保証します」という立場で候補者を推薦し、その言葉に客観性と説得力を持たせます。
- 選挙活動の全面サポート:演説原稿の相談からポスター作成、選挙活動の同行まで、候補者を全面的にバックアップします。
- 精神的な支え:選挙期間中のプレッシャーや不安を抱える候補者にとって、最も信頼できる相談相手となります。
このように、推薦責任者は選挙の当落を左右するキーパーソンであり、非常に責任のある立場です。だからこそ、引き受けたからには、候補者のことを誰よりも深く理解し、その魅力を自分の言葉で、心を込めて伝える準備が不可欠となります。
推薦文の基本的な書き方4ステップ
説得力があり、聞いている人の心に響く推薦文を作成するには、自己流で書き始めるのではなく、決まった「型」に沿って構成を組み立てるのが最も効果的で確実な方法です。ここでは、文章を書くのが苦手な人でも、分かりやすく伝わりやすい推薦文が作れる基本的な4つのステップを紹介します。
この流れは、スピーチの王道とも言える構成です。このステップを意識するだけで、話があちこちに飛んでしまうことなく、聞き手が自然に内容を理解し、最後まで集中して耳を傾けてくれるようになります。
| ステップ | 内容 | ポイントと具体例 |
|---|---|---|
| ① 導入 (Point) | 自己紹介と推薦する候補者の紹介 | 「誰が、誰を、何の役に推薦するのか」を最初に明確に宣言します。「〇年〇組の〇〇です。私が〇〇さんを生徒会長に推薦します」と、ハキハキとした声で始めましょう。ここで聞き手の関心を掴むことが重要です。 |
| ② 人柄・魅力の紹介 (Reason) | 候補者の性格や長所を伝える | 候補者の最も素晴らしい点を象徴的なキャッチフレーズで表現します。「彼はクラスの太陽です」「彼女は静かなるリーダーです」のように、人柄が一言で伝わる言葉を見つけましょう。 |
| ③ 具体的なエピソード (Example) | 人柄や魅力を裏付ける出来事を話す | 推薦文の心臓部です。前のステップで述べた人柄が、どのような行動に表れたのかを具体的に語ります。「〇〇の時、彼は〇〇と言って、〇〇してくれました」と、情景が目に浮かぶように話すのがコツです。 |
| ④ 結論・お願い (Point) | 改めて推薦する理由と投票のお願い | エピソードを踏まえ、「このような理由から、彼(彼女)こそが相応しい」と再度結論を述べます。そして、「どうか皆さんの清き一票をお願いします」と、力強く、そして誠実に投票を呼びかけて締めくくります。 |
この4ステップは、推薦文の揺るぎない骨格となります。いきなり全文を書こうとせず、まずは各ステップにどのような内容を盛り込むか、メモに書き出すことから始めてみてください。そうすることで、頭の中が驚くほどクリアになり、自信を持って文章を組み立てられるようになるでしょう。
生徒会選挙で候補者の魅力を伝えるコツ

候補者の魅力を、他の誰よりもリアルに、そして最大限に伝えるための最大のコツ。それは、「説明」するのではなく「描写」することです。つまり、抽象的な褒め言葉を並べるのではなく、具体的な行動や情景が目に浮かぶようなエピソードを描写することに全力を注ぎましょう。
例えば、「Aさんはとても優しくて、リーダーシップがある人です」と説明されても、聞いている人にはその「優しさ」や「リーダーシップ」がどの程度のものなのか、具体的にイメージすることはできません。ありきたりな言葉に聞こえてしまい、右から左へと聞き流されてしまう可能性が高いです。しかし、これを具体的なエピソードに変えるだけで、印象は180度変わります。
他の誰も知らない、あなただけが目撃した候補者の素敵な一面を思い出してみてください。それが、どんな立派な言葉よりも雄弁に、候補者の魅力を物語ってくれる、最高の推薦文の材料になります。
抽象的な「説明」を具体的な「描写」に変える練習
- 抽象的な説明:「彼はリーダーシップがあります。」
→ 具体的な描写:「体育祭のクラス対抗リレーの選手決めで意見が割れた時、彼は焦っている人、不満そうな人、一人ひとりの元へ歩み寄り、『どうしてそう思う?』と丁寧に話を聞いていました。そして、全員が納得できる新しい走順を提案し、見事にクラスを一つにまとめてくれました。」 - 抽象的な説明:「彼女は責任感が強いです。」
→ 具体的な描写:「クラスで飼育していた金魚の世話は、正直誰もが面倒くさがる仕事でした。しかし、彼女は夏休みの間も一日も欠かすことなく学校へ来て、黙々と水槽の掃除をしていました。その背中を見て、本当の責任感とは何かを教わった気がします。」
このように、具体的な「行動」や「セリフ」、さらにはその時の「情景」や「あなたの気持ち」を描写することで、候補者の人柄が生き生きと立体的に伝わり、聞き手の記憶に深く刻まれます。単なる推薦文ではなく、60秒のショートストーリーを語るような気持ちで、最高のエピソードを選び抜いてみましょう。
聞き手を惹きつける面白い推薦文のコツ
推薦文における「面白い」とは、決してウケを狙ったギャグやモノマネをすることではありません。むしろ、候補者の人間味あふれる意外な一面や、思わずクスッと笑みがこぼれるような微笑ましいエピソードを紹介し、聞き手に親近感を持ってもらうことを指します。
体育館に集まった全校生徒は、何人もの真面目な演説を聞き続けるうちに、どうしても集中力を失いがちです。そんな時、少し肩の力が抜けるような、人間味のあるエピソードを効果的に挟むことで、会場の空気をリフレッシュさせ、他の候補者との差別化を図り、候補者の人柄をより一層魅力的に印象付けることができるのです。
効果的なのは、少しドジな一面や、意外な特技、ユニークなこだわりなどを、ポジティブな魅力に繋げて紹介することです。
面白いエピソードの例
- 例1(ドジな一面):「私が推薦するAくんは、学校一の方向音痴として有名です。校内の保健室に行こうとして、なぜか3回も図書館に迷い込んだ伝説を持っています(笑)。しかし、そんな彼だからこそ、初めてこの学校に来て戸惑っている新入生の気持ちが誰よりも分かります。校内で困っている後輩がいると、誰よりも早く気づいて声をかけている姿を、私は何度も見てきました。」
- 例2(意外な特技):「Bさんは、一見すると物静かな文学少女に見えるかもしれません。しかし、彼女は実は、指パッチンで校歌の全フレーズを演奏できるという、誰にも真似できないであろう驚くべき特技を持っています。このユニークな発想力と実行力があれば、誰も思いつかなかったような楽しい学校行事を企画してくれるに違いありません。」
このように、一見すると弱点や変わった特徴に思えるようなことでも、ポジティブな人柄や能力に繋げて語ることで、それは聞き手の心に残る魅力的なギャップとして映ります。候補者の人間的な温かさやユニークさが伝わるような、あなただけが知っているエピソードを探してみてください。
ユーモアの注意点:尊敬の念を忘れずに!
ただし、ユーモアを取り入れる際には絶対に守るべき一線があります。それは、候補者をからかったり、見下したり、馬鹿にしたりするような内容は絶対に避けるということです。あくまでも候補者への深い尊敬と愛情を土台とし、聞いている人が温かい気持ちになるような、ポジティブな笑いを目指すことが何よりも大切です。
内輪ウケで終わるようなネタも、全校生徒の前では不適切なので注意しましょう。
生徒会選挙の推薦文で使える例文を紹介
ここでは、候補者の異なるタイプ別に、すぐに使える推薦文の例文を3つ紹介します。これらの例文はあくまで土台です。この型を参考にしながら、あなた自身の言葉で、候補者との具体的なエピソードを肉付けし、世界に一つだけのオリジナルの推薦文を完成させてください。
例文1:クラスを明るくするムードメーカータイプ
皆さん、こんにちは。2年1組の〇〇です。私が生徒会長に推薦するのは、同じクラスの〇〇さんです。
〇〇さんは、誰もが認める「クラスの太陽」のような存在です。彼女が笑顔で「おはよう!」と教室に入ってくるだけで、朝の少し眠い空気がパッと明るくなります。特に印象的だったのは、昨年の合唱コンクールの練習期間中のことでした。本番が近づくにつれ、思うように声が出ず、クラスの雰囲気がピリピリと沈んでいた時、彼女は突然「みんな、一回ストップ!円になろう!」と提案しました。そして、一人ひとりの良いところ、例えば「〇〇さんのソプラノ、すごく綺麗だよ!」「〇〇くんのバス、みんなを支えてくれてるよ!」と、大きな声で伝え始めたのです。その真っ直ぐな言葉のおかげで、私たちは自信を取り戻し、再び笑顔で練習に臨むことができました。
このように、人の心を前向きにし、集団を自然に一つにする力を持つ〇〇さんなら、きっとこの学校全体をもっと明るく、一人ひとりが輝ける活気あふれる場所にしてくれると、私は固く信じています。皆さん、どうか〇〇さんに、あなたの温かい一票をお願いします。
この例文のポイント解説
「クラスの太陽」というキャッチフレーズで人柄を分かりやすく提示し、「合唱コンクール」という具体的なエピソードでそのリーダーシップを証明しています。候補者のセリフを具体的に入れることで、臨場感と説得力を高めているのが特徴です。
例文2:縁の下でみんなを支えるしっかり者タイプ
こんにちは。1年3組の〇〇です。私が生徒会副会長に推薦するのは、部活動の先輩である2年生の〇〇さんです。
〇〇先輩は、決して派手に前に出るタイプではありません。しかし、誰も見ていないところで、誰も気づかないような細やかな気配りで、みんなのために行動できる人です。例えば、私たちが所属するバスケットボール部で使うボールやビブスは、本来であれば練習後に全員で片付けるのがルールです。しかし、先輩はいつも練習が終わった後も一人だけ残り、ボール一つひとつの空気圧をチェックし、汚れたビブスを洗濯ネットに入れてくれています。私がそのことに気づいて「どうしていつも一人でやってるんですか?」と尋ねた時、先輩は「みんなが次の日、気持ちよく練習を始められるのが一番だから」と、はにかんで答えてくれました。その時、私は「本当の優しさ、本当のリーダーシップとは、こういうことなんだ」と深く感動しました。
このような見返りを求めない誠実な姿勢と、みんなを陰で支える真の優しさを持つ〇〇先輩こそ、生徒会長を支え、全校生徒のために働く副会長に最もふさわしい人物です。どうか、〇〇先輩に皆さんの力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
この例文のポイント解説
「誰も見ていないところでの行動」というエピソードに焦点を当てることで、候補者の誠実さや謙虚さを際立たせています。候補者との会話(セリフ)を入れることで、その人柄をよりリアルに伝えているのが効果的です。
例文3:冷静な分析力で問題解決に導く知性派タイプ
3年2組の〇〇です。私が生徒会書記に推薦するのは、2年生の〇〇くんです。
皆さんは、〇〇くんに対して「物静かで冷静な人」というイメージを持っているかもしれません。確かにその通りです。しかし、彼の本当のすごさは、その冷静さの奥にある、鋭い分析力と問題解決能力にあります。昨年度、生徒会で「目安箱に投書が少ない」という問題が持ち上がった時、多くの人が「もっと呼びかけよう」という精神論に留まる中、彼は一人だけ違いました。彼はまず、過去3年間の投書内容を全て分析し、「意見を書いても、どうなったか分からないことが問題の本質ではないか」と指摘したのです。そして、投書された意見への回答を、生徒会だよりで報告する「目安箱アンサー」という新企画を提案し、見事に投書数を3倍に増やしました。
感情論に流されず、事実に基づいて問題の本質を見抜き、具体的な解決策を打ち出せる〇〇くんなら、生徒会の活動記録を正確に残す書記として、そして生徒会の頭脳として、間違いなく活躍してくれるでしょう。皆さん、彼の静かなる情熱に、ぜひ一票を託してください。
この例文のポイント解説
「冷静」という一見すると地味な特徴を、「分析力」「問題解決能力」という生徒会に必要なスキルへと繋げています。「投書数が3倍になった」という具体的な数字を入れることで、実績を客観的に示し、説得力を高めています。
推薦責任者の例文【中学生向け応用編】
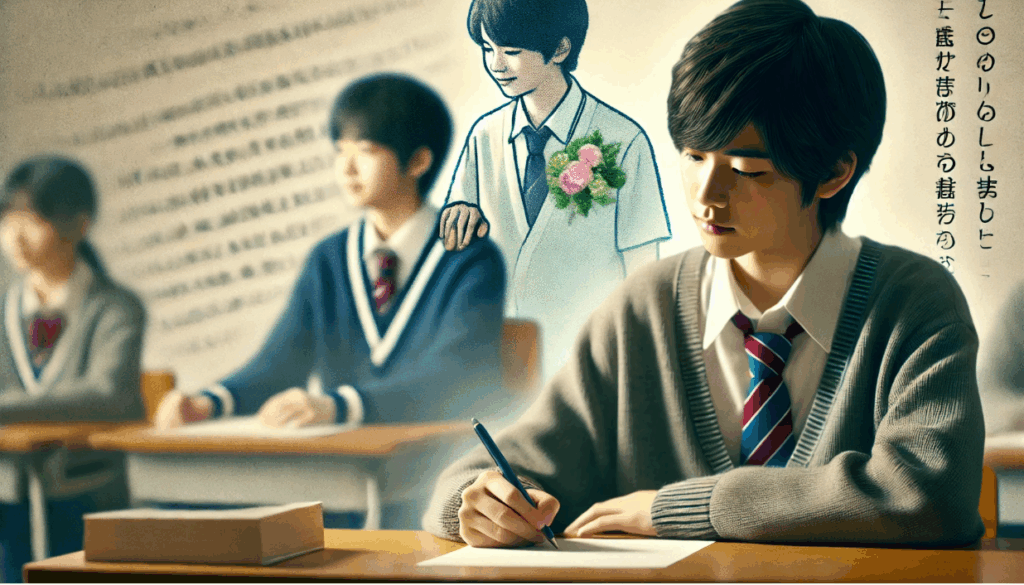
- 具体的なエピソードでインパクトを与える
- 面白いだけじゃない!信頼されるユーモア
- 心に残る推薦スピーチの締めの言葉
- 高校の生徒会選挙にも通じるポイント
- まとめ:推薦責任者の例文で中学生も自信がつく
具体的なエピソードでインパクトを与える
推薦文に、他の誰もが真似できないような強いインパクトと圧倒的な説得力を持たせるための応用テクニック。それは、前述の通り、エピソードに「具体的な数字」を効果的に盛り込むことです。
なぜなら、数字は誰が聞いても解釈がぶれない客観的な事実であり、候補者の実績や努力の「規模」や「程度」を、聞き手が一瞬で理解できるようにしてくれるからです。「たくさん」「一生懸命」「長い間」といった曖昧な言葉を、具体的な数値に置き換えるだけで、あなたのスピーチの信頼性は劇的に向上します。
数字を使った表現のビフォーアフター
| Before(曖昧な表現) | After(数字を使った具体的な表現) | |
|---|---|---|
| 実績の規模 | 「文化祭の準備で、たくさんのクラスメイトの意見をまとめました。」 | 「文化祭の準備では、わずか3日間で50人以上の意見を聞き、それをたった一つの企画案にまとめ上げました。」 |
| 成果の大きさ | 「彼の企画したイベントは、みんなが満足していました。」 | 「彼の企画したイベントは、終了後のアンケートで全校生徒の90%が『満足した』と回答する大成功を収めました。」 |
| 努力の継続性 | 「彼女は長い間、地域のボランティア活動を続けています。」 | 「彼女は、小学校4年生から6年間、一度も休むことなく毎月の地域清掃ボランティアに参加し続けています。」 |
エピソードに使える「数字」が見つからない場合は?
必ずしもパーセントや人数といった明確な統計データでなくても構いません。「クラス全員が納得するまで、放課後毎日話し合った」「15年ぶりに、生徒たちの手によって校則の改定を実現させた」「彼が挨拶運動を始めてから、たった1ヶ月で、朝の挨拶の声が明らかに大きくなった」など、規模感や継続性、変化のスピードを示す言葉を意識的に探してみるだけでも、文章の具体性は格段にアップします。
このように、エピソードのどこか一箇所にでも客観的な数字を加えるだけで、話の信憑性が増し、聞き手の印象に強く残りやすくなります。候補者のこれまでの活動を一緒に振り返り、数字で表現できる輝かしい実績がないか、ぜひ探してみてください。
面白いだけじゃない!信頼されるユーモア
推薦文で使うユーモアは、単に笑わせるためだけのものではありません。応用編として、候補者の「弱み」や「欠点」とさえ思える特徴を、逆転の発想で「強み」や「魅力」に転換して語ることで、面白さと同時に、人間的な深みと深い信頼感を生み出すことができます。
なぜなら、完璧で非の打ち所がないスーパーマンのような人物よりも、少し弱点や苦手なことがある人の方が、聞き手は親近感を覚え、人間的な魅力を感じるからです。そして、その弱点を自覚し、克服しようと努力する姿や、弱みがあるからこその他人への優しさを語ることで、候補者の人間的な器の大きさを最大限に引き出すことが可能になります。
一見すると短所に思えることも、視点を変えれば、他の誰にもない個性や素晴らしい長所になり得ます。その「リフレーミング(物事の捉え方を変える)」こそが、人の心を動かす、温かくて信頼されるユーモアを生むのです。
「弱み」を「強み」に変える魔法の言い換え術
- 弱み:「彼は極度の心配性で、石橋を叩いて渡るタイプです。」
→ 強み(リフレーミング):「彼は、人一倍慎重で、心配性なところがあります。しかし、だからこそ準備は誰よりも徹底していて、彼が実行委員長を務めた昨年の体育祭では、事前に考えうる全てのトラブルを想定し、完璧なマニュアルを作成してくれました。そのおかげで、当日は一つの大きな混乱もなく、スムーズに進行しました。彼のその慎重さが、私たちの学校生活の『安心』と『安全』を、誰よりも確実に守ってくれるはずです。」 - 弱み:「彼女は少し人見知りで、自分から前に出るのが苦手です。」
→ 強み(リフレーミング):「彼女は、自分から積極的に大勢の前で話しかけるのは少し苦手かもしれません。しかし、だからこそ、教室の隅で一人で悩んでいる人の心の痛みが誰よりも分かります。困っているクラスメイトがいると、決して騒ぎ立てず、そっと隣に寄り添い、静かに話を聞いてあげている姿を私は何度も見てきました。彼女のその優しさは、この学校から『孤独』をなくす、何より大きな力になると信じています。」
このように、「しかし、だからこそ」という魔法の接続詞を使って弱みと強みを繋げることで、候補者の欠点さえもが、生徒会役員として不可欠な素晴らしい資質であるかのように伝えることができます。この高等テクニックは、聞き手に深い共感と揺るぎない信頼感を与える、非常に効果的な方法です。
心に残る推薦スピーチの締めの言葉

推薦スピーチの締めくくりは、わずか数秒ですが、演説全体の印象を決定づけ、聞き手の記憶に最も長く残る、極めて重要なパートです。ここまで候補者の魅力を情熱的に伝えてきたあなたの熱意を全てこの一言に込め、聞いている全校生徒の心に直接語りかけるような、自信に満ちた力強い言葉で、投票を呼びかける必要があります。
心理学には「ピーク・エンドの法則」というものがあり、人は物事の最も感情が盛り上がった点(ピーク)と、最後の場面(エンド)を最も強く記憶すると言われています。つまり、あなたのスピーチの「締め」が、候補者の印象そのものを左右するのです。「清き一票をお願いします」という決まり文句ももちろん大切ですが、それだけではありきたりで、記憶に残りません。
あなた自身の言葉で、候補者への揺るぎない信頼と、学校の未来への明るい期待を表現することで、聞き手の心を最後のひと押しすることができます。
聞き手の心を動かす締めの言葉フレーズ例
- 熱意と信頼を伝えるフレーズ
「〇〇さんの誰かのために行動できるその優しさと、一度決めたことをやり抜くその強さがあれば、この学校はもっと素晴らしい場所になると、私は心の底から信じています。私が、自信を持って推薦します。」 - 明るい未来を想像させるフレーズ
「彼が生徒会長になった未来を想像してみてください。きっと、今よりももっと一人ひとりの笑顔が増え、活気と優しさにあふれた学校生活が待っているはずです。その未来を、皆さんの手で実現させてください。」 - 力強く、そして誠実にお願いするフレーズ
「言葉だけでは終わりません。彼は必ず行動で示してくれます。どうか、皆さんのその貴重な一票に込められた期待と願いを、〇〇さんの背中を押す力として、彼に託してください。心から、よろしくお願いいたします。」
そして、締めの言葉を述べる際は、技術も重要です。少しだけ間(ま)を取ってから、ゆっくりと、しかしハッキリとした口調で、まっすぐに全校生徒の顔を見渡し、一人ひとりに語りかけるように、はっきりと発言することを意識してください。あなたの本気の想いは、その声の震えや眼差しを通じて、必ず聞き手に伝わります。最後まで自信を持って、あなたの信じる候補者への応援の気持ちを、力強く届けましょう。
高校の生徒会選挙にも通じるポイント
これまで解説してきた推薦文の書き方、特に「具体的なエピソードで人柄を語る」という基本原則は、実は中学校の生徒会選挙だけに留まるものではありません。これは、高校の生徒会選挙はもちろん、大学のゼミ選考、さらには将来の就職活動の面接や社会に出てからのプレゼンテーションにも直接応用できる、一生モノの普遍的なコミュニケーションスキルです。
ただ、高校の生徒会選挙では、中学生の時よりも一歩進んで、候補者の「人柄」だけでなく、より具体的な「政策」や「公約(マニフェスト)」が重視される傾向が強まります。そのため、推薦文もその変化に合わせて、少しだけレベルアップさせる必要があります。
高校で推薦文を書く際のレベルアップ・ポイント
高校の推薦文で差をつけるポイントは、候補者の素晴らしい経験や能力(過去の実績)が、「具体的にどのような学校改革や問題解決に繋がり、生徒たちにどんなメリットをもたらすのか」という、未来への明確な展望(ビジョン)まで言及することです。
| 中学レベル(実績の紹介) | 高校レベル(実績と未来のビジョンの連結) | |
|---|---|---|
| 主張 | 「彼はクラスの意見をまとめ、文化祭を成功に導きました。リーダーシップがあります。」 | 「彼は文化祭で多様な意見をまとめ上げた、卓越した調整力を持っています。その力を活かし、形骸化している校則の見直しという、賛否両論が巻き起こる難しい問題にも、全校生徒の意見を丁寧に集約しながら、誰もが納得できる新しいルール作りを実現してくれるはずです。」 |
このように、過去の実績(エピソード)を、未来の公約(ビジョン)を達成できる能力の「証明」として結びつけて語ることで、候補者が単に「良い人」であるだけでなく、「私たちの学校を具体的に変えてくれる有能なリーダー」であることを力強くアピールできます。
中学生のうちからこの論理的な思考と表現の仕方を意識して練習しておけば、高校に進学してからも、あらゆる場面であなたの言葉は一目置かれるものになるでしょう。
まとめ:推薦責任者の例文で中学生も自信がつく
この記事のポイントをまとめます。
- 中学生が推薦責任者の例文を探す際はまず基本構成を理解する
- 推薦責任者とは候補者の魅力を第三者の視点で伝え信頼性を保証する重要な役割
- 推薦文の書き方は「導入」「人柄紹介」「エピソード」「結論」の4ステップが基本
- 抽象的な褒め言葉は具体的な行動の描写に置き換えることが最も重要
- 「優しい」ではなく「夏休みも毎日金魚の世話をしていた」のように情景が浮かぶように語る
- 面白い推薦文とは候補者の人間味あふれる意外な一面を紹介し親近感を持たせること
- 候補者への尊敬を忘れふざけすぎるとイメージダウンに繋がるため注意が必要
- スピーチにインパクトを与えるには「50人」「90%」といった具体的な数字を取り入れると効果的
- 候補者の弱みを「だからこそ」という言葉で強みに転換するユーモアは信頼感を生む
- 締めの言葉は定型句だけでなく自分の言葉で候補者への期待と学校の未来を語る
- スピーチの際は自信を持ってまっすぐに前を向き全校生徒に語りかけるように話すことが大切
- ここで学んだ推薦文の基本は高校の生徒会選挙や将来の社会生活でも通用する普遍的なスキル
- 高校では過去の実績と未来の公約を結びつけて語る論理的な視点が加わるとより良くなる
- この記事で紹介した豊富な例文や具体的なテクニックを参考にすれば自信を持って推薦文を作成できる
- 推薦責任者という大役は候補者への信頼を自分の言葉で伝える貴重な経験となる



