生徒会選挙の公報の書き方に悩む人は多いものです。
「どんな内容を書けばよいのか」「立候補理由をどうまとめれば伝わるのか」「公約が思いつかないときはどうすればいいのか」――そんな切実な疑問を抱く中学生に向けて、本記事では“読まれる公報”を作るための本質的なコツから具体的なテクニックまで、詳しく解説します。
公報は、あなたの「学校を良くしたい」という情熱を全校生徒に届けるための、非常に強力なツールです。しかし、ただ想いを書き連ねるだけでは、その熱意は伝わりません。読み手の心を掴み、「この人に任せたい」と思わせるには、戦略的な構成と具体的な表現が不可欠です。
また、本記事では、公約を整理するための一覧の作り方や、他の候補者と差をつけるための面白いアイデアを盛り込む工夫、中学生でもすぐに使える具体的な例文、さらには演説の例文を活用してインパクトのある公報に仕上げる方法まで、選挙活動全体を見据えた実践的なノウハウを紹介します。
この記事を読むことで、生徒会選挙の準備が格段にスムーズになり、不安が自信に変わるはずです。あなたらしい、説得力のある公報を完成させるためのガイドとして、ぜひ最後までお役立てください。
- 生徒会選挙の公報の書き方の基本と立候補理由のまとめ方
- 公約が思いつかないときに使える発想法と公約一覧の作り方
- 面白いアイデアで差をつけるコツと例文 中学生向けサンプル
- 演説 例文を活用してインパクトのある公報を作る方法
生徒会選挙の公報の書き方!基本と考え方

生徒会選挙の公報を書くとき、まず押さえておきたいのは「なぜ書くのか(目的)」「何を伝えるのか(内容)」「誰に伝えるのか(対象)」という基本です。
いきなり白紙の原稿用紙やPCの画面に向かっても、内容がまとまらず時間だけが過ぎて悩んでしまうことも多いでしょう。それは、公報が果たすべき役割や、盛り込むべき要素が整理できていないからです。
ここでは、生徒会選挙の本来の目的や公報が持つ独自の役割をはじめ、最も重要な「立候補理由」の論理的なまとめ方、公約が思いつかないときの具体的な発想法、そして中学生でもすぐに実践できるわかりやすい例文までを丁寧に紹介します。
さらに、最後には多くの公報の中で埋もれないための「インパクトのある書き出し」のコツも解説します。
これらを順に学び、一つずつステップを踏むことで、あなたの熱意とビジョンが的確に伝わる公報を、自信を持って作り上げることができるでしょう。
生徒会選挙の目的と公報の役割を理解しよう
生徒会選挙の最大の目的は、「学校をより良くするための意見を持ち、それを行動に移せるリーダーを選ぶこと」です。
単なる人気投票や、目立つためのイベントではありません。学校生活を生徒自身の手で、より豊かで実りあるものにするための方針を示し、その実現に向けて全校生徒をまとめ、行動できる代表者を選出する点に、本来の意味があります。
文部科学省が示す学習指導要領においても、生徒会活動は「望ましい人間関係を形成し,集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し,諸課題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる」場として位置づけられています。
(参照:文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編」)
そのため、立候補者は「自分がどんな学校を目指したいのか(ビジョン)」「どんな課題を解決したいのか(現状認識)」「そのために何をするのか(具体的行動)」を、明確かつ具体的に伝える必要があります。
そこで重要な役割を果たすのが「公報」です。公報は、生徒全員に自分の考えや人柄を知ってもらう“第一印象の場”であり、選挙活動の中核を担う公式文書です。
公報と演説の決定的な違い
演説は「熱意」や「人柄」を直接的に伝える場ですが、聞ける時間や回数には限りがあります。一方、公報は全校生徒の手に渡り、教室や自宅で「何度も読み返される」ものです。演説では伝えきれない詳細な公約や、あなたの真剣な想いを、文章としてじっくりと届ける唯一の手段なのです。そのため、内容の分かりやすさ・誠実さ・読みやすさが、演説以上に票を左右することもあります。
また、公報には「誰が(人柄・信頼性)」「どんな考えを持ち(理念・ビジョン)」「何を実現したいのか(公約)」が明確に伝わる構成が求められます。
限られた紙面、短い文字数の中で、自分の個性や信念を効果的に表現することが鍵です。ただ漠然と「頑張ります」と書くのではなく、「なぜ、そう思うのか」という背景まで伝える必要があります。
生徒会選挙の民主的なプロセスを支えるという目的を理解し、公報が持つ「文章で想いを届ける」という役割を意識することで、単なる自己紹介文ではなく、「学校全体へのメッセージ」としての重みを持つ公報を作成できるようになります。
公報で伝えるべき内容とは?立候補理由のまとめ方
公報で最も大切な核となる部分、それは「なぜ立候補したのか」という理由を明確に伝えることです。
読者である生徒たちは、無意識のうちに「この人に私たちの学校を任せて大丈夫か?」「この人なら信頼できるか?」という視点で公報を読んでいます。そのため、彼らが「この人なら安心して任せられる」と感じられるような、説得力のある根拠を提示する必要があります。
そのため、立候補理由は「楽しそうだから」といった個人的な感情だけでなく、学校の現状や課題を踏まえた具体的な動機にすることが重要です。
たとえば、「学校をもっと楽しくしたい」という理由は、それ自体は悪くありませんが、あまりにも漠然としています。これでは、読み手は「どうやって?」「他の人も同じことを言っている」としか感じません。
しかし、「休み時間が短く、クラス間の交流が少ないと感じています。そこで、昼休みの時間割を見直し、全校生徒が自由に参加できるイベント(例:eスポーツ大会、中庭でのミニライブなど)を企画し、学年を超えた交流の場を増やしたい。だから立候補しました」といったように、現状認識(課題)と具体的行動(解決策)を結びつけて書くと、説得力が格段に増します。
さらに、立候補理由を書く際は、次の4つのステップを意識して文章を組み立てると、論理的で伝わりやすい内容になります。
| ステップ | 内容 | ポイントと具体例 |
|---|---|---|
| 1. 結論(動機) | なぜ立候補したのかを一文で述べる | 例:「私は、全校生徒が『明日も学校に来たい』と心から思える、居心地の良い学校をつくりたいと思い、立候補しました。」 |
| 2. 現状認識(課題) | その動機に至った背景や、感じている課題を具体的に示す | 例:「しかし今、学校生活の中で『自分の意見がどうせ通らない』と感じたり、行事の準備が一部の人に偏っていたりする場面を見ることがあります。」 |
| 3. 解決策(公約への布石) | その課題をどう改善したいか、自分なりの解決の方向性を示す | 例:「私は、生徒会がもっとみんなの声に耳を傾け、一人ひとりの『やりたい』という気持ちをサポートする仕組みが必要だと考えます。」 |
| 4. 決意表明 | 最後に、学校をどうしたいか、仲間とどう取り組むかを述べる | 例:「そのために、私は生徒会の一員として、みんなと協力し、意見を形にするために全力で行動することを誓います。」 |
公報は単なる宣言文ではなく、自分の考えを通して“学校全体の未来像”を全校生徒と共有するものです。
立候補理由をこの4ステップで丁寧にまとめることで、論理が飛躍せず、読む人に「この人はしっかり考えているな」「この人なら変えてくれそうだ」という強い期待と信頼感を持たせることができます。
公約が思いつかないときの考え方と発想法
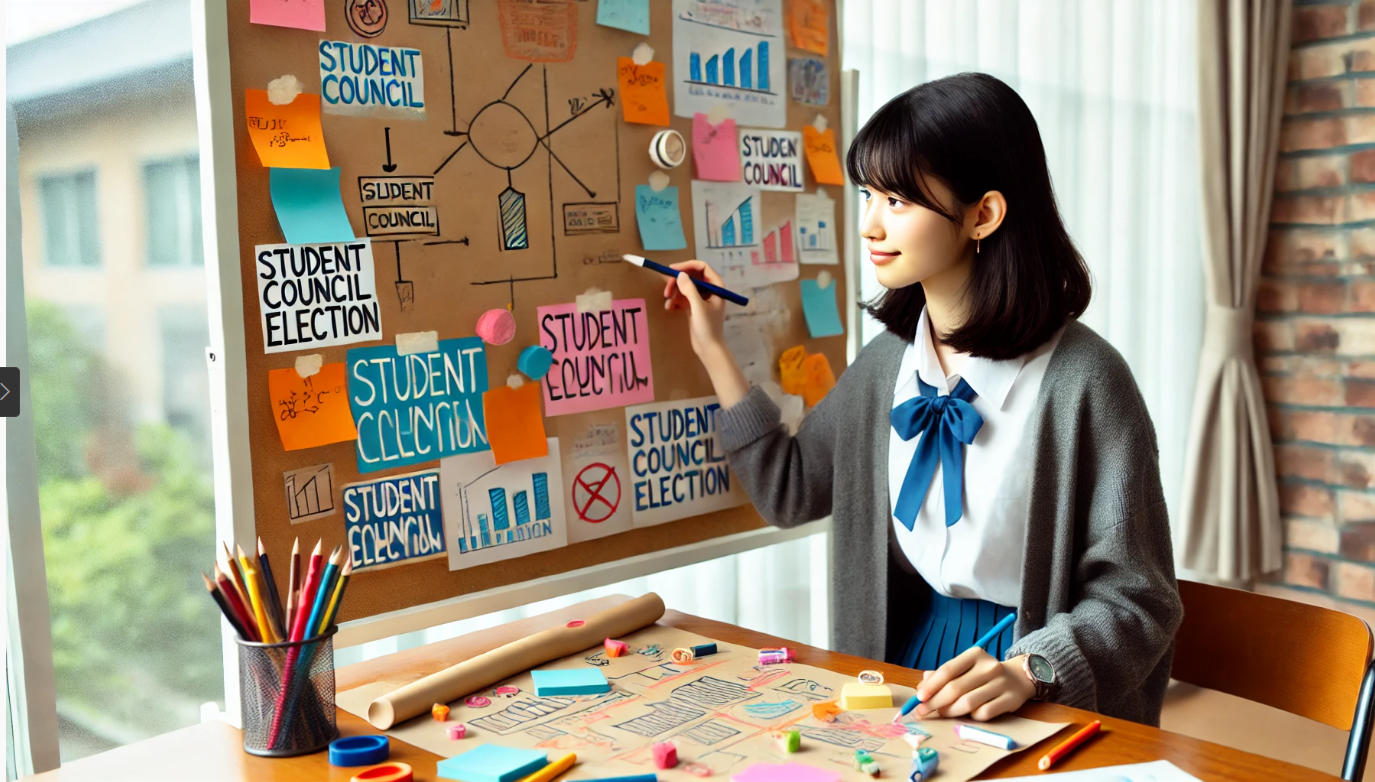
公約が思いつかないときは、「何か大きなことを言わなければ」と気負わず、自分の身近な学校生活に深く目を向けることが最大のポイントです。
「世界平和」のような壮大なスローガンは必要ありません。多くの生徒が日々感じている小さな「不便」「不満」「不安」、あるいは「もっとこうなったらいいな」という「願望」の中にこそ、実現可能で魅力的な公約のヒントが隠れています。
まずは「自分が日々感じている不便」「クラスメイトからよく聞く意見(愚痴や要望)」「学校行事や校則、設備などで改善できそうなこと」を、質や実現可能性を考えずに、とにかくたくさんリストアップしてみましょう(ブレインストーミング)。
アイデア出しのヒント:カテゴリ別発想法
公約のアイデアを以下のカテゴリに分けて考えると、発想が広がりやすくなります。
- 学習環境:「図書室の本を増やしたい」「自習室が欲しい」「ICT機器(タブレットなど)をもっと活用したい」
- 学校行事:「体育祭の種目を増やしたい」「文化祭の企画を自由にしたい」「合唱コンクールの選曲方法を見直したい」
- 学校生活・ルール:「校則(服装、髪型など)を見直すための議論の場を作りたい」「掃除の分担を公平にしたい」「目安箱をデジタル化したい」
- 設備・環境:「トイレをきれいにしてほしい」「昼休みに読書できる静かなスペースを作りたい」「校内放送でリクエスト曲を流したい」
- 交流・その他:「他学年との交流イベントを企画したい」「ボランティア活動を推進したい」「SDGsに関する取り組みを始めたい」
また、発想を広げるには「問いかけの形」で考えるのも非常に効果的です。
「なぜ、みんなは休み時間にスマホを使いたがるのか? → もっと楽しいアナログな交流があればいいのでは?」
「どうすれば学校がもっと明るくなるか? → 挨拶運動+αで、感謝を伝える『サンクスカード』企画はどうか?」
「どうすればみんなが意見を出しやすくなるか? → 無記名のWebアンケートを定期的に実施してはどうか?」
このように、現状を「問い」の形に変え、それに対する自分なりの「答え(仮説)」を探すことで、他の人とは違う、独自性のある公約が生まれます。
大切なのは、特別な才能や奇抜なアイデアではなく、「学校を良くしたいという当事者としての視点」です。
完璧な公約でなくても構いません。自分の言葉で「なぜそれが必要なのか」を説明できる現実的な提案をすることが、全校生徒からの信頼を得る第一歩になります。
中学生でも書ける!わかりやすい公報の例文紹介
中学生が公報を書くときに最も意識したいのは、「難しい言葉や堅苦しい表現を使わず、自分の素直な気持ちを伝えること」です。
立候補理由や公約を、どこかで聞いたような立派な言葉で書こうとすると、どうしても形式的になり、文章に心がこもらず、読む人にあなたの本当の想いが届きにくくなります。
そこで、わかりやすい構成とシンプルな表現を心がけましょう。基本となるのは「動機 → 現状(課題) → 改善策(公約) → 意気込み」という流れです。この流れを意識すれば、短い文章でもしっかりとした構成になります。
【例文①:基本形】
私は、みんなが安心して過ごせる学校をつくりたいと思い、生徒会(役職名)に立候補しました。
学校生活の中で、時には「自分の意見を言いにくい」と感じることがあると思います。また、困ったことがあっても、誰に相談すればいいか分からない人もいるかもしれません。
そこで、私はクラスごとに「目安箱」を設置し、どんな小さな意見や悩みも生徒会で必ず話し合える場をつくりたいです。
一人ひとりが自分の声を届けられる、風通しの良い学校にするために、みんなと力を合わせてがんばります。ご支援よろしくお願いします。
【例文②:行事改善パターン】
「今年の体育祭、最高だったね!」——全校生徒がそう言い合えるような、活気ある学校行事をつくりたくて立候補しました。
去年の体育祭は楽しかったですが、「一部の競技が中心で、出る機会が少なかった」という声も聞きました。
私は、体育祭実行委員会と協力し、運動が苦手な人でも楽しめる「eスポーツ大会」や「クイズリレー」などの新種目を導入することを公約にします。
全員が主役になれる学校行事を目指して、皆さんの意見を積極的に取り入れていきます!
このように、「動機 → 現状 → 改善策 → 意気込み」という流れが明確であれば、読み手はあなたの考えをスムーズに理解できます。
大切なのは、上手な文章を書くことよりも「自分の言葉で書かれているか」どうかです。
背伸びをせず、あなたが本心から感じていること、やりたいことを、誠実な言葉で込めることで、読み手の心に響く、あなただけの公報になります。
インパクトのある書き出しで注目を集めるコツ
選挙公報は、多くの場合、全候補者のものが一覧で掲示されたり、冊子として配布されたりします。その中で、まず「読んでもらう」ためには、最初の一文が勝負です。
多くの候補者の中からあなたの公報に目を留めてもらうためには、「おっ」と思わせるようなキャッチーな書き出しで、読者の関心を瞬時に引くことが非常に重要です。
インパクトのある書き出しを作るには、次の3つのアプローチが効果的です。それぞれの「良い例」と「避けた方がよい例」を比較してみましょう。
- キャッチフレーズ風に始める短く力強い言葉、スローガンで理念を打ち出します。
◎ 良い例:「学校をもっと笑顔であふれる場所にしたい!」「『できない』を『できる』に変える生徒会へ。」
△ 避ける例:「私が生徒会長になったら頑張ります。」(具体的でなく、インパクトが弱い) - 質問で引き込む読み手に問いかけることで、自分事として考えてもらうきっかけを作ります。
◎ 良い例:「今の学校生活に、100%満足していますか?」「もっと『学校が楽しい』と思える毎日を、一緒につくりませんか?」
△ 避ける例:「皆さんはどう思いますか。」(何についての質問か不明確) - 体験談(課題提起)から入る自分の実体験や具体的なシーンを描写することで、共感を呼びます。
◎ 良い例:「去年の文化祭で感じた、クラス全員で一つのものを作り上げたあの感動を、もっと広げたい。」「『どうせ変わらない』。そんな言葉を聞くたびに、私は悔しく思っていました。」
△ 避ける例:「私は以前から思っていましたが…」(回りくどく、何を言いたいのかが伝わりにくい)
また、どのパターンを使うにしても、書き出しの文章は長すぎないことが鉄則です。
理想は、最初の3行(50~70文字程度)で「あなたがどんな人で、何を目指しているのか」がぼんやりとでも伝わるように意識しましょう。
公報の第一印象は、その先を真剣に読んでもらえるかどうかを決める重要な分かれ道です。読者の関心をぐっと引く書き出しを工夫することで、あなたの公約や熱意が書かれた本文へと確実に誘導することができます。
生徒会選挙の公報の書き方!実践ステップ

ここからは、生徒会選挙の公報を具体的に書き上げるための「実践ステップ」に進みます。
基本となる考え方を理解したら、次はあなたの考えを論理的に整理し、読み手である全校生徒に伝わる形へと仕上げていく段階です。
まずは、あなたの公約を具体化し、一覧表にまとめることで自分の強みを明確にします。次に、読みやすく共感を呼ぶための文章構成(流れ)を整えます。
さらに、他の候補者と差をつけるための「面白いアイデア」を取り入れる方法や、演説の例文を参考にしながら公報の説得力を高める方法を学びます。
最後に、公報が完成した後に必ず行うべき「見直しチェックポイント」を確認することで、誤字脱字を防ぐだけでなく、あなたの公報を“伝わる文章”から“心を動かす文章”へと磨き上げることができます。
公約一覧を作って自分の強みを整理しよう
生徒会選挙の公報を書くときは、まず「自分が当選したら、何を実現したいのか」を具体的かつ明確にすることが何よりも大切です。
そのための必須の第一歩が、「公約一覧」を作って自分の考えを整理することです。
いきなり文章を書き始めると、伝えたい内容の優先順位がぼやけたり、途中で言いたいことが変わってしまったり、論理に一貫性がなくなったりすることがあります。
しかし、公約一覧(マニフェスト)を作ることで、「学校のどんな課題に取り組みたいのか」「それを実現するために、具体的にどんな行動を取れるのか」が視覚的に整理されます。
具体的には、次のようなステップで「公約整理シート」を作成してみましょう。
- 現状の課題を挙げる(As-Is)
例:「掃除の時間がバラバラで、真面目にやらないクラスがある」「生徒からの意見を吸い上げる仕組みが古い(目安箱が機能していない)」「行事の準備が特定の人に偏っている」
- 理想の姿を描く(To-Be)
例:「みんなが公平感を持って掃除に取り組める」「どんな小さな意見でも生徒会に届き、議論される」「行事準備を効率化し、全員が参加しやすくする」
- 具体的な公約(行動)にまとめる
例:「掃除当番のローテーションを見直し、美化委員会によるチェック体制を強化する」「目安箱のデジタル化(Webフォームの導入)と、月1回の生徒会による回答を公表する」「行事の準備チーム制度を導入し、タスクを明確化する」
このように整理すると、単なる思いつきのスローガンではなく、“現状分析に基づいた根拠のある提案”として説得力が飛躍的に増します。
以下の表は、公約を整理するための一例です。これを参考に、自分なりの公約一覧を作成してみてください。
| カテゴリ | 現状の課題(As-Is) | 理想の姿(To-Be) | 具体的な公約(Action) | (自分の強みとの関連) |
|---|---|---|---|---|
| 学校生活 | 校則が厳しく、何のためにあるのか分かりにくいルールがある。 | 生徒自身がルールを理解し、納得して守れる状態。時代に合った見直しがされる。 | 「校則見直し検討会」を月1回開催し、生徒と先生が対話する場を設ける。 | (強み:人の意見を聞き、まとめるのが得意) |
| 学校行事 | 文化祭のクラス企画がマンネリ化している。 | 生徒の「やりたい」というアイデアが実現でき、オリジナリティ溢れる文化祭になる。 | 文化祭の企画予算の配分を見直し、「新規企画コンテスト枠」を設ける。 | (強み:新しいアイデアを考えるのが好き) |
| 学習環境 | 図書室に新しい本(ラノベや専門書)が少なく、利用者が限られている。 | 全校生徒が読みたい本があり、休み時間に気軽に立ち寄れる図書室になる。 | 全校生徒対象の「リクエスト図書アンケート」を実施し、購入予算への反映を学校に働きかける。 | (強み:読書家で、アンケート集計なども得意) |
さらに、自分の得意分野や性格(例:「人前で話すのが得意」「コツコツ作業するのが好き」「絵を描くのが得意」など)と公約を結びつけて考えることで、「なぜ自分がそれをやるべきなのか」という、あなただけの個性が伝わる公約になります。
公約一覧は、あなたの考えを整理するための設計図であると同時に、“自分らしさ”という武器を見つけるための地図のような存在です。
一度書き出して客観的に整理することで、より具体的で、多くの生徒の共感を呼ぶ公報に仕上げることができます。
読まれる文章にするための構成と流れのコツ
読まれる公報、そして「心を動かす」公報にするためには、ただ正しい内容を書くのではなく、「読み手が理解しやすく、共感しやすい流れ」を作ることが決定的に重要です。
どんなに素晴らしい公約や熱意があっても、構成が整理されておらず、あちこちに話が飛んでいては、読み手は途中で疲れてしまい、あなたの想いは伝わりにくくなります。
中学生の公報で最もおすすめの構成は、「導入 → 理由 → 公約 → 結び」の4段階です。
これは、ビジネスプレゼンなどでも使われる「PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論)」の考え方に基づいています。この流れは、読み手が最も自然に内容を理解しやすく、説得力を高めることができます。
公報を「読まれる」構成 4ステップ
- 導入(Point):
自分の核となる想い(キャッチフレーズ)を短く伝えます。
例:「私は、全校生徒が主役になれる学校をつくりたいと思っています。」
→ 読み手の関を引きつけ、「この人は何を目指しているのか」を最初に示します。
- 理由(Reason):
「なぜそう思うのか」を、具体的なエピソードや感じている課題を交えて説明します。
例:「昨年の学校行事で、一部の人だけが活躍しているのを見て、もっと全員が輝ける場が必要だと感じたからです。」
→ 導入で示した理念に「説得力」と「共感」を与えます。
- 公約(Example):
その理念を実現するために、「自分が実際に取り組みたいこと」を明確に提示します。
例:「そこで私は、①目安箱のデジタル化による意見収集、②体育祭での新種目導入、③文化祭での企画コンテストの実施、を公約します。」
→ 理念を「行動」に落とし込み、具体性と実現可能性を示します。公約は3つ程度に絞ると伝わりやすいです。
- 結び(Point):
最後に、改めて「協力をお願いする言葉」や「学校全体への意気込み」で力強く締めくくります。
例:「一人ではできません。皆さんの力を貸してください。みんなでより良い学校をつくりましょう!」「応援よろしくお願いします。」
→ 読み手の記憶に残り、行動(投票)を促します。
この流れを意識することで、あなたの公報は論理的で読みやすく、感情のこもった、説得力のある文章に仕上がります。
読まれる文章とは、決して難しい言葉や美しい比喩を使った文章ではなく、「伝えたいことが整理されている文章」です。
この構成と流れを工夫することで、あなたの熱い想いが全校生徒にしっかりと届く、強力なメッセージに変わります。
面白いアイデアを盛り込んで差をつける方法

生徒会選挙の公報で他の候補者と明確な差をつけるためには、「面白いアイデア」を取り入れることが非常に効果的です。
ここでいう“面白い”とは、単に奇をてらったり、笑いを狙ったりするという意味ではありません。「なるほど、その視点はなかった」「それなら楽しそう」「私たちの学校も変わりそうだ」と、読む人の心を動かし、期待感を抱かせるようなユニークな発想を指します。
公報は多くの人が読むため、特に「挨拶運動をします」「目安箱を設置します」といった定番の公約は、内容が似通ってしまうことがよくあります。
そこで、あなたらしいユニークな切り口を加えることで、あなたの公報は数ある候補者の中で埋もれず、強く印象に残ります。
たとえば、「挨拶運動」を「朝の時間を有効活用して交流を深める“ハイタッチ&朝トークタイム”」と言い換える。「目安箱」を「全校アンケートで学校の“改善してほしいところ総選挙”を実施したい」とイベント化する。このように、具体的で楽しいイメージを描ける提案は、強い印象を与えます。
面白いアイデアのヒント:「学校生活」×「自分の得意」×「社会の動き」
アイデアを生み出すには、「学校生活」と「自分の得意分野」を掛け合わせるのがおすすめです。
- (例)音楽が好き → 「校内BGM企画(昼休みにお悩み相談とリクエスト曲を流すラジオ番組風)」
- (例)運動が得意 → 「スポーツデーの新種目提案(ドッジボール大会、学年対抗リレーなど)」
- (例)デザインが得意 → 「生徒会ニュースのレイアウト刷新(インフォグラフィック化して掲示)」
さらに、「社会の動き」を取り入れるのも効果的です。
- (例)SDGs → 「給食の残飯を減らすキャンペーン」「制服のリサイクル・リユース活動の推進」
- (例)デジタル活用 → 「生徒会公式SNS(または校内限定ブログ)での情報発信」「行事のペーパーレス化」
ただし、注意点があります。単なる思いつきではなく、「なぜそれが学校にとって良いのか」「どうやって実現するのか」をセットで説明できると、アイデアが“面白いだけで終わらない”説得力を持ちます。
創意工夫のある公約は、読み手の共感を呼ぶと同時に、あなた自身の「積極性」と「柔軟な発想力」をアピールする最大のチャンスです。
演説の例文を活用して説得力を高めるテクニック
立会演説会で使う「演説の原稿」を活用することは、公報の内容をより熱く、説得力のあるものにするための有効な方法です。
演説と公報は、発表する場(全校生徒の前 vs 紙面)や形式(話し言葉 vs 書き言葉)が異なりますが、どちらも「限られた時間・スペースの中で、聞く人・読む人に自分の考えを伝え、共感を得て、行動(投票)を促す」という点では全く同じ目的を持っています。
そのため、演説の構成やインパクトのある言葉遣いを公報に参考にすることで、より伝わる公報が書けるようになります。
たとえば、演説では聴衆の心をつかむために「共感を呼ぶ導入 → 問題提起 → 解決策(公約) → 未来のビジョン → 最後の訴え・意気込み」という流れがよく使われます。この構成は、そのまま公報に応用することができ、読者が自然に内容を理解しやすくなります。
| 項目 | 演説(話し言葉) | 公報(書き言葉) | 公報への活用テクニック |
|---|---|---|---|
| 伝達手段 | 声の強弱、表情、ジェスチャー | 文字、レイアウト、写真 | 演説の「熱意」を、公報では「!」や太字、力強い言葉(「必ず実現します」など)で表現する。 |
| 情報量 | 時間は短いが、印象に残りやすい | 詳細は伝えられるが、読まれないとゼロ | 演説で最も伝えたい「キャッチフレーズ」を、公報の「見出し」や「書き出し」にそのまま使う。 |
| 構成 | 聴衆の共感を呼ぶストーリー性が重要 | 読みやすさ、論理的な正しさが重要 | 演説で使う「具体的なエピソード」を、公報の「立候補理由」に組み込むと、文章にリアリティが出る。 |
例文を参考にする最大のポイントは、次の2点です。
- 「自分の言葉に言い換える」こと
例文をそのまま写すのではなく、自分の体験や自分の学校の状況に合わせてアレンジします。
- 「エピソードを加えて個性を出す」こと
(例)演説例文に「もっと意見を出しやすい学校にしたい」というフレーズがあった場合、公報では「私が1年生の時、意見を言えずに悔しかった経験があります。だからこそ、誰でも安心して意見を出せる環境(デジタル目安箱など)をつくりたいのです」といったように、自分の体験(エピソード)に落とし込んで書き換えます。
また、演説ではリズムや感情のこもった表現が重視されますが、公報では「読み手に具体的な行動や変化をイメージさせる具体性」が重要です。
演説の原稿を作成する過程で見つけた「心に響くフレーズ」や「力強い言葉」を公報にも散りばめ、自分の提案に合わせて調整すると非常に効果的です。
演説の例文を活用することは、ただ文章を真似るのではなく、自分の考えを整理し、他者に「伝える力」を磨くための絶好のトレーニングです。
演説と公報、双方の原稿を練り上げることで、それぞれの内容がより深まり、読み手・聞き手の共感を強く得る、説得力あるメッセージに仕上げることができます。
公報完成後に見直すチェックポイント
公報が書き終わったら、満足感からすぐに提出するのではなく、必ず「見直しの時間」を最低でも1日は取りましょう。
文章は書いている最中(主観的)よりも、少し時間をおいて冷静になって読み返す(客観的)方が、誤りや改善点、論理の飛躍に気づきやすくなります。
見直す際は、ただ誤字脱字を探すだけでなく、次のポイントを「チェックリスト」のように一つひとつ確認するのがおすすめです。
公報 完成前チェックリスト 5項目
- 内容はわかりやすいか(読者視点)
□ 専門的な言葉や難しい漢字、回りくどい表現を使っていないか?
□(例:「DXの推進」→「タブレットをもっと活用する」)
□ 小学6年生が読んでも、あなたが何をしたいのかが理解できるか?
- 構成に一貫性があるか(論理)
□ 冒頭で述べた「理念」と、中盤の「公約」、最後の「意気込み」が、きちんとつながっているか?
□ 途中で話題が急に飛んだり、矛盾したりしていないか?
- 公約が現実的で実現可能か(信頼性)
□ 「校則をすべて撤廃する」「宿題をゼロにする」など、理想論や実現不可能な公約になっていないか?
□ 先生方や学校の理解・協力が必要な公約の場合、その「働きかけをします」という姿勢が書かれているか?
→ 実現可能性がある公約の方が、真剣さが伝わり信頼されます。
- 誤字・脱字や文のリズム(品質)
□ 誤字や脱字はないか?(名前や役職名の間違いは致命的です)
□ 「てにをは」や句読点の位置は適切か?
□ 一度、声に出して読んでみる。つっかえたり、息継ぎが苦しかったりする部分は、一文が長すぎるか、リズムが悪いです。短く区切る修正をしましょう。
- 感情(熱意)が伝わっているか(共感)
□ 全体的に事務的な報告書のような、冷たい文章になっていないか?
□ 「私はこう思う」「みんなとこうしたい」「必ず実現したい」といった、あなたの主体的な意志や熱意が伝わる表現が適切に入っているか?
最後に、もし可能であれば、先生や親、部活の先輩や友達など、信頼できる第三者に読んでもらうのも非常に有効です。
他人の目で客観的にチェックしてもらうことで、自分では気づかなかった文章のわかりにくい部分や、印象の薄い箇所を発見できます。
見直しは面倒に感じるかもしれませんが、この最後の「磨き上げ」の工程こそが、あなたの公報を「読まれる」レベルから「心を動かし、投票につながる」レベルへと引き上げる最大のステップです。
丁寧に磨き上げることで、あなたの真剣な想いがより多くの人の心に届く公報になります。
まとめ
この記事では、生徒会選挙の公報の書き方について、基本の考え方から実践的なテクニックまでを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
- 生徒会選挙の目的は、学校をより良くするために考え行動できるリーダーを選ぶこと
- 公報は、立候補者の想いを文章でじっくりと伝える「第一印象」の重要なツールである
- 立候補理由は感情だけでなく、学校の「課題」と「解決策」をセットで伝えると説得力が増す
- 公約が思いつかないときは、身近な不便さや「もっとこうしたい」という願望から発想を広げることが効果的
- 公約一覧を作って、自分の得意分野や強みを整理することで、内容に一貫性と独自性が出る
- 中学生でも書けるように、構成は「導入→理由→公約→結び」を意識し、シンプルな言葉でまとめることが大切
- 面白いアイデア(ユニークな切り口)を取り入れることで、他の候補者との明確な差別化ができる
- 演説 例文を参考に、自分の言葉やエピソードに置き換えて公報に活かすと表現に深みと熱意が出る
- インパクトのある書き出し(キャッチフレーズ、問いかけ等)を工夫することで、読み手の関心を引くことができる
- 公報完成後は、内容・構成・誤字・感情表現などを客観的に丁寧に見直すことで完成度が格段に高まる
生徒会選挙の公報の書き方の基本を押さえ、自分の考えを整理し、それを読み手に伝わるよう丁寧に表現することが、信頼される候補者への第一歩です。決して、完璧な文章や、大人びた難しい言葉を使う必要はありません。
最も大切なのは、あなたの「学校を良くしたい」という純粋な想いが、「誰かの心に届くかどうか」です。
この記事で紹介したステップを参考に、あなたらしい、誠実な言葉で書かれた公報を作成してください。その公報は、きっと多くの生徒の共感を呼び、選挙という大切な舞台であなたの魅力を最大限に伝えてくれる、最強のパートナーとなるでしょう。あなたの挑戦を心から応援しています。


