中学校の生徒会役員になったものの、「何か新しい取り組みの例はないだろうか…」「毎年同じような活動ばかりでマンネリ化している…」と、大きな期待と共に責任の重さを感じていませんか。
面白い案を頭の中で描いてみても、それを具体的な企画アイデアに落とし込み、全校生徒を巻き込むまでに至るのは決して簡単なことではありません。
また、これから生徒会選挙に挑戦しようと考えている方にとっては、当選を勝ち取るための説得力ある生徒会の公約の例文や、有権者である生徒たちの心に響く応援演説の例文が不可欠でしょう。
さらに、生徒会活動の具体例を知るだけでなく、生徒たちの関心がどこにあるのかを示す委員会 人気ランキングの傾向や、少し先の未来像として参考になる高校の先進的な事例まで、幅広く情報を集めたいと考えているかもしれません。
この記事では、そんな意欲あふれる皆さんの悩みを解決するために、中学校の生徒会で実現可能な新しい取り組みのアイデアを、企画成功のポイントとあわせて、より深く、そして徹底的に解説していきます。
この記事を読めば、あなたの生徒会活動が一段と輝きを増すヒントがきっと見つかるはずです。
- 全校生徒が一体となって楽しめる面白い企画の具体例がわかる
- 日々の学校生活をより快適で豊かにするための改善案のヒントが見つかる
- アイデア出しから実現までの具体的な企画の立て方とその手順を深く学べる
- 生徒会選挙や応援演説で他の候補者と差をつける実践的な例文を参考にできる
【アイデア集】中学校の生徒会で輝く新しい取り組み例

- 全校生徒が盛り上がる面白い取り組み
- 具体的なイベントの企画アイデア
- 学校生活を快適にする改善活動の案
- 生徒会活動の具体例をカテゴリ別に紹介
- 少し背伸び?参考になる高校の取り組み
- 周りの人を巻き込む企画の進め方
さらに、他校の実例も含めてアイデアを広げたい場合は、生徒会の面白い取り組み事例も参考にしてみてください。
全校生徒が盛り上がる面白い取り組み
生徒会の新しい取り組みを成功に導くための最も重要な鍵は、役員だけでなく、一般の生徒、さらには先生方まで巻き込んだ「参加型」の企画を立案することです。
一部の人たちだけで盛り上がるのではなく、全員が「これは自分たちのイベントだ」と感じられるような仕組みを作ることで、学校全体にポジティブな一体感が生まれ、生徒会活動そのものへの関心と評価を高める絶好の機会となります。
ここでは、普段の学校生活に新鮮な風を吹き込み、誰もが主役になれる面白くて参加しやすい取り組みを、具体的な運営のポイントと共に3つ紹介します。
生徒会 vs 先生 チャレンジ対決
これは、生徒会役員チームと先生方有志チームが、威信をかけて様々な種目で対決する、世代を超えた交流イベントです。昼休みや放課後といった限られた時間を有効活用し、全校生徒が観戦しやすい形式で開催するのがポイントです。
種目は、定番のドッジボールやリレーといったスポーツから、学校の歴史や先生の意外な特技に関するクイズ大会、さらにはeスポーツなど、多様なジャンルを取り入れるとより多くの生徒の興味を引くことができます。
普段は教壇に立つ厳格な先生が、驚くほどの運動神経を発揮したり、クイズで珍回答を連発したりと、普段の学校生活では決して見ることのできない一面が垣間見えるかもしれません。
このような非日常的な光景は、生徒と先生の心理的な距離をぐっと縮め、学校全体のコミュニケーションを活性化させる強力な起爆剤となるでしょう。
企画成功のヒント
対決の様子をビデオで撮影し、編集して後日、給食の時間に上映会を行うのも面白いでしょう。
また、対決の勝敗を全校生徒に予想してもらう投票企画を事前に実施すれば、イベント当日までの期待感をさらに高めることができます。
校内おもしろフォトコンテスト
「学校」という身近な舞台を新たな視点で見つめ直す、創造性あふれるコンテストです。
「学校でしか撮れない面白い写真」という大きなテーマのもと、「偶然が生んだ奇跡の一枚」「思わず笑ってしまう友達の変顔」「先生の決定的瞬間(撮影・応募には本人の許可が必須)」「校内に潜む不思議スポットやアートな風景」など、複数の部門を設けることで、多様な才能が発掘されるかもしれません。
応募された作品は、ただ掲示するだけでなく、各写真に撮影者による一言コメントを添えることで、作品の魅力がより深く伝わります。
全校生徒が審査員となる投票期間を設け、最も多くの票を集めた作品にはグランプリを、生徒会特別賞や先生方が選ぶユニークな賞を用意するのも一興です。
受賞者には賞状だけでなく、少し豪華な文房具セットや図書カードといった実用的な景品を用意することで、参加へのモチベーションを大きく向上させることができるでしょう。
ポイント
フォトコンテストは、文化祭の生徒会企画として実施することで、その効果を最大限に発揮します。
来場した保護者や地域の方々にも投票に参加してもらうことで、学校の日常にある温かさや楽しさを外部に効果的にアピールする絶好の機会となります。
学校オリジナルスタンプラリー
校舎全体を冒険の舞台に変えてしまう、探求心をくすぐるイベントです。
校内に複数のチェックポイントを戦略的に配置し、生徒たちが地図を片手にそれらを巡ってスタンプを集めます。
この企画の面白さは、ミッションの多様性にあります。「図書室の先生におすすめの本を一冊紹介してもらう」「音楽室で校歌の一節を歌う」「理科室にいる先生に元素記号クイズを出してもらう」といった、各場所の特性を活かしたミッションを加えることで、単なるスタンプ集めではない、知的好奇心を満たすゲームへと進化します。
この企画は、学年やクラスの垣根を越えて誰もが平等に楽しめるため、新入生と上級生の交流を促進したり、普段あまり話す機会のない生徒同士が協力するきっかけを生み出したりと、学校全体のコミュニケーションを活性化させる上で非常に有効です。
安全管理の徹底
スタンプラリーを実施する際は、何よりも生徒の安全を最優先に考える必要があります。
授業時間中に行うのは避け、昼休みや放課後の時間帯に限定しましょう。また、階段での競争による転倒や、理科準備室のような危険な場所、普段生徒が立ち入らない管理区域などにポイントを設置することは絶対に避けてください。
企画段階で必ず複数の先生とルートを共有し、安全面のチェックを念入りに行うことが不可欠です。
万が一の事態に備え、各ポイントに監視役の生徒や先生を配置するなどの対策も検討しましょう。
具体的なイベントの企画アイデア
全校を巻き込むような大規模なイベントは準備が大変ですが、日常のちょっとした隙間時間を使って実施できる小規模な企画も、学校生活に彩りと潤いを与える上で非常に価値があります。
ここでは、比較的少ない労力で実現可能ながら、生徒の心に残るイベントの企画アイデアを深掘りして紹介します。
「〇〇の日」限定の特別企画
カレンダーに記されている多種多様な記念日をイベントの「フック」として活用する、一日限りの特別企画です。
普段は気にも留めないようなユニークな記念日を取り上げることで、生徒たちに新鮮な驚きと日常の中の非日常的な楽しみを提供できます。
この企画の魅力は、アイデア次第で無限のバリエーションが生まれる点にあります。
| 記念日 | 企画アイデア例 | 発展のポイント |
|---|---|---|
| メガネの日(10月1日) | その日にメガネをかけている生徒と先生の人数をカウントし、昼の放送で「本日のメガネ着用者数」として発表する。 | 「ベストドレッサー(メガネ部門)」を先生と生徒から1名ずつ選び、ささやかな賞品を贈る。メガネに関する豆知識クイズを出題するのも面白い。 |
| カレーの日(1月22日) | 給食がカレーの日に合わせて、カレーにまつわる歴史やスパイスの効能などを紹介するクイズを放送で出題する。 | 栄養士の先生にインタビューを行い、「今日のカレーの隠し味」やこだわりポイントを紹介してもらう。給食委員会との連携企画としても有効。 |
| 推しの日(11月4日) | 自分の好きなアニメキャラクター、アイドル、歴史上の人物など、「推し」のイラストや紹介文を書いてもらい、特設コーナーに掲示する。 | 「#〇〇中学校推しの日」といったハッシュタグを作り、校内SNSなどで共有する(学校のルールを確認)。自分の「推し」への愛を語る1分間スピーチ大会なども盛り上がる。 |
このような「小ネタ」的なイベントを定期的に開催することで、マンネリ化しがちな学校生活に心地よいリズムとアクセントを加えることができるでしょう。
朝のハッピー音楽リクエスト
一日の始まりである朝の時間を、生徒自身の選んだ音楽で彩る企画です。
登校後の慌ただしい時間や、朝の会が始まる前のわずかな数分間、生徒から事前に寄せられたリクエスト曲を校内放送で流します。
好きな音楽を聴くことでリラックス効果や気分を高める効果が期待でき、生徒が前向きな気持ちで一日のスタートを切る手助けとなります。
リクエストの募集方法には工夫が必要です。各教室に専用のリクエストボックスを設置するアナログな方法に加え、学校で許可されていればGoogleフォームなどを活用したオンラインでの募集も効率的です。
特に、名前を出されることに抵抗がある生徒も少なくないため、匿名でのリクエストを可能にすることは、参加のハードルを大きく下げる上で非常に重要です。
また、曲のジャンルが偏らないよう、「今週はJ-POP特集」「来週は洋楽特集」といったテーマを設けるのも良いでしょう。
著作権に関する重要な注意点
学校教育の目的で、校内放送にて市販のCD音源を流す行為は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のウェブサイトによると、通常は学校がJASRACと包括的な利用許諾契約を結んでいるため、著作権法上の問題は生じないとされています。しかし、このルールはあくまで一般的なケースです。
企画を実行する前には、必ず音楽の先生や生徒会担当の先生を通じて、自分たちの学校がどのような契約を結んでいるかを確認し、適切な手順を踏むようにしてください。
学校生活を快適にする改善活動の案
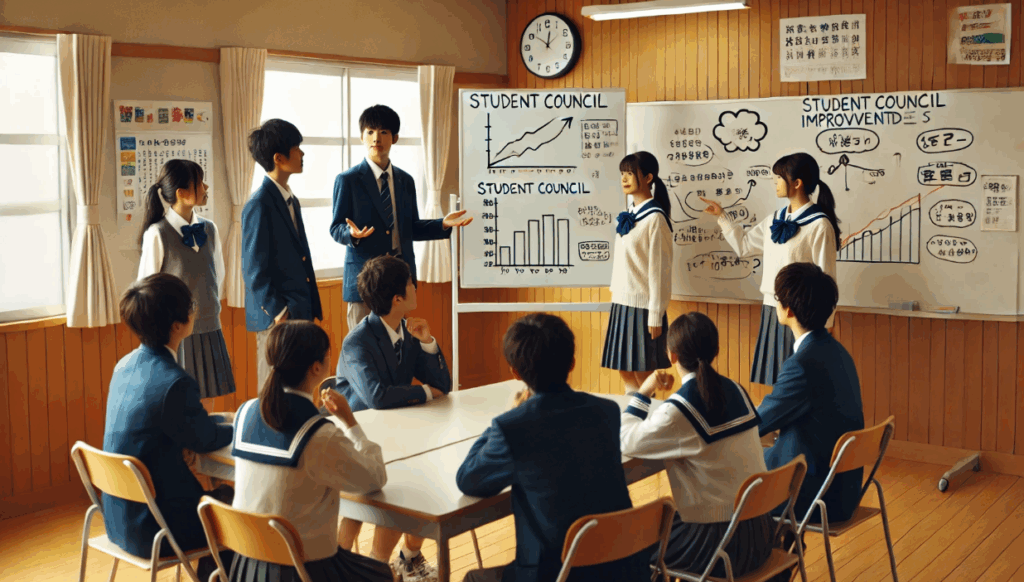
全校生徒を沸かせる華やかなイベント企画は生徒会の花形活動ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、生徒一人ひとりの学習環境や学校生活をより快適にするための地道な改善活動です。
生徒たちが日々感じている「ちょっとした不便」や「あったらいいな」という願いを丁寧に拾い上げ、実現していくことで、生徒会への信頼感と存在意義は格段に向上します。
ここでは、学校生活の質の向上に直結する、実用的で効果の高い改善活動の案を3つ、具体的な導入方法と共に紹介します。
デジタル目安箱の設置・活用
各教室の隅に置かれがちな従来の「意見箱」を、現代のコミュニケーションスタイルに合わせて進化させる取り組みです。無料で利用できるGoogleフォームやMicrosoft Formsなどを活用し、オンライン上の「デジタル目安箱」を設置します。
このシステムの最大の利点は、生徒が24時間365日、スマートフォンやタブレットから、匿名で気軽に意見を投稿できる点です。これにより、これまで紙の意見箱には届かなかった、内気な生徒の切実な声や、より率直な意見を集めやすくなります。
集約された意見は、生徒会役員が定期的に(例えば週に一度)内容を確認し、実現可能性や緊急性に応じて優先順位をつけ、議論します。
そして、ただ議論するだけでなく、「〇月〇日に寄せられた『トイレの石鹸を補充してほしい』という意見について、美化委員会と連携して対応しました」「『体育館のバスケットボールを新しくしてほしい』という意見は、現在、先生方と予算について相談中です」というように、意見に対するアクションの進捗状況を、生徒会新聞や掲示物、校内放送などを通じて全校生徒にフィードバックすることが極めて重要です。
このサイクルを確立することで、生徒会の活動の透明性が高まり、「自分たちの声が本当に届いている」という実感が生徒の中に育まれます。
生徒会備品の貸し出し
生徒会費の有効活用と、生徒の自主的な活動をサポートすることを目的とした、実用性の高い制度です。「あったら便利だけど、クラスや個人で買うには少し高い」と感じるような備品を生徒会予算で購入し、全校生徒が利用できるように貸し出します。
例えば、球技大会のクラス練習で必要になる各種ボールやビブス(ゼッケン)、文化祭のクラス展示の装飾に役立つインパクトドライバーやグルーガンといった工具、さらにはプレゼンテーションで使用するレーザーポインターなどが候補として考えられます。
この制度を円滑に運営するためには、明確な貸し出しルールの策定が不可欠です。貸し出し簿を作成し、「いつ」「誰が」「何を」「いつまでに返すか」を記録する仕組みを整えましょう。また、紛失や破損した場合のペナルティについても事前に定めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
多くの生徒がこの制度を利用することで、生徒会費が自分たちの学校生活に直接役立っているという納得感を得やすくなります。
おもしろ校則チェック
「ルールだから守る」という受け身の姿勢から一歩進んで、「なぜこのルールは存在するのか」を生徒自身が主体的に考えるきっかけを作る、教育的意義も大きい企画です。
自分たちの学校に、制定された時代背景から現代の実情に合わなくなってしまった校則や、他校の生徒が聞いたら驚くようなユニークな校則、さらには明文化されていない「暗黙のルール」がないかを、全校生徒へのアンケートやグループディスカッションを通じて調査します。
この活動の目的は、単に面白い校則を見つけて笑うことではありません。集まった意見をもとに、「この校則は本当に今の私たちに必要か?」「もっと合理的なルールに変えることはできないか?」と、校則の意義や必要性について全校生徒で議論を深めることにあります。
もし、多くの生徒が「これは変えるべきだ」と考える校則が見つかれば、生徒会として具体的な改善案を作成し、全校生徒の署名を集めて学校側に正式に改正を提案するという、次の具体的なアクションへとつなげることができます。
これは、生徒の自治意識を育む上で非常に価値のある活動と言えるでしょう。
生徒会活動の具体例をカテゴリ別に紹介
生徒会の活動は、その範囲が広く多岐にわたりますが、活動の目的や方向性を明確にすることで、より計画的で効果的な取り組みが可能になります。
ここでは、生徒会の活動を大きく3つのカテゴリに分類し、それぞれの具体的な活動例を紹介します。自分たちの生徒会がどの分野に力を入れたいかを考える際の、思考のフレームワークとして活用してください。
カテゴリ1:社会貢献・SDGs推進活動
このカテゴリの活動は、自分たちの学校という枠組みを越え、より広い地域社会や地球全体が抱える課題に目を向けることを目的とします。
社会の一員としての自覚を育み、持続可能な未来のために自分たちに何ができるかを考え、行動に移す経験は、生徒にとって大きな成長の機会となります。特に近年では、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマとした活動が注目されています。
具体的な活動例
- エコキャップ運動:ペットボトルのキャップを回収し、リサイクル業者を通じて得た対価をNPO法人に寄付し、世界の子どもたちのためのワクチン代とする活動。
- ユニセフなどへの募金活動:自然災害の被災地支援や、開発途上国の子どもたちの教育支援などを目的とした募金活動を、学校行事や地域のイベントに合わせて実施する。
- フードドライブの実施:家庭で余っている未開封の食品を持ち寄り、フードバンク団体を通じて食料を必要としている人々に届ける活動。
- 校内環境整備:ゴミの分別徹底を呼びかけるポスターの作成や、緑化委員会と連携した花壇の花植え、省エネを呼びかけるキャンペーンの実施。
カテゴリ2:地域連携・ボランティア活動
学校が孤立した存在ではなく、地域社会を構成する重要な一員であることを意識し、地域との積極的な関わりを深めていく活動です。地域の人々と顔の見える関係を築き、共に活動することで、コミュニケーション能力や社会参加への意欲を育むことができます。
具体的な活動例
- 地域清掃活動:通学路や学校周辺の公園などを、部活動単位や有志で定期的に清掃する。
- 高齢者施設や児童施設での交流:総合的な学習の時間などと連携し、施設を訪問して合唱を披露したり、レクリエーションを一緒に行ったりする。
- 地域イベントへの参加協力:地域のお祭りや防災訓練などの運営スタッフとして、受付や会場設営、見回りなどのボランティアに参加する。
- 伝統文化の継承:地域に伝わる伝統的な踊りや祭事について学び、その担い手として参加したり、学校内で発表会を開いて後輩や地域住民に紹介したりする。
カテゴリ3:校内交流・学校生活の充実
生徒会活動の根幹をなす、最も基本的かつ重要なカテゴリです。全ての生徒が安心して学校生活を送り、生徒同士の良好な人間関係を築き、日々の学校生活をより楽しく、思い出深いものにすることを目的とします。
具体的な活動例
- 新入生歓迎会の企画・運営:寸劇を交えた学校生活の紹介や、部活動紹介、校舎案内ツアーなどを企画し、新入生の不安を和らげる。
- 挨拶運動の強化:生徒会役員が校門に立ち、登校してくる生徒に元気よく挨拶をすることで、学校全体の明るい雰囲気作りのきっかけとする。
- 異学年交流レクリエーション:昼休みなどを利用して、学年の垣根を越えたチームでドッジボール大会やクイズ大会などを開催し、縦のつながりを深める。
- 季節感の演出:七夕には笹と短冊を、クリスマスにはツリーを設置するなど、季節を感じられる装飾を施し、学校生活に潤いを与える。
これらの3つのカテゴリをバランス良く組み合わせることで、生徒会の活動はより多角的で深みのあるものになります。「私たちの生徒会は、今期どのカテゴリに特に力を入れていこうか?」と役員同士で話し合ってみるのも良いでしょう。
少し背伸び?参考になる高校の取り組み

中学生の皆さんにとって、高校の生徒会活動は、自分たちの活動の数年先を行くモデルケースとして、非常に多くの示唆を与えてくれます。
中学校よりも生徒の自主性や裁量が尊重されることが多い高校では、より主体的で社会との連携を意識したスケールの大きな取り組みが展開されています。これらの先進的な事例を知ることは、皆さんの視野を広げ、活動の可能性を再発見する絶好の機会となるでしょう。
ここでは、中学校でもそのエッセンスを取り入れ、応用することが可能な高校のユニークな取り組みを3つ紹介します。
学生ビジネスコンテスト
これは、数人のグループで新しいビジネスや社会貢献活動のアイデアを創出し、その企画の新規性、実現可能性、社会への影響力などをプレゼンテーション形式で競い合うイベントです。マーケティング、資金計画、プレゼン能力など、社会で求められる実践的なスキルを総合的に学ぶ「探究学習」の一環として、多くの高校で導入されています。
これを中学生向けにアレンジするのであれば、テーマをより身近な「私たちの学校生活を劇的に良くする新商品・新サービス開発コンテスト」といった形にするのがおすすめです。
「朝の忘れ物チェックを自動化するアプリ」「給食のメニューを栄養バランスと美味しさの両面から提案する企画」など、中学生ならではの柔軟な発想で、学校が抱える課題を解決するアイデアを競い合います。この経験は、問題発見能力や論理的思考力を養う上で非常に有益です。
全国生徒会ネットへの参加
これは、地理的に離れた他校の生徒会役員とオンラインで繋がり、情報交換や合同企画を行うという、現代ならではのネットワーク活動です。全国規模の生徒会交流イベントやオンラインフォーラムに参加することで、自分たちの学校だけでは得られない多様な価値観や革新的な活動事例に触れることができます。
「自分たちの悩みは、他の学校も同じだったんだ」という共感や、「そんな面白い取り組みがあるのか!」という新たな発見は、活動のマンネリ化を防ぎ、新たなモチベーションを生み出します。
中学生であっても、市や県の単位で開催される生徒会のリーダー研修会や交流会に積極的に参加することで、同様の貴重な経験を得ることが可能です。他校の役員と積極的に交流し、自分たちの学校をより良くするためのヒントを探してみましょう。
生徒作の学校パンフレット
学校説明会やオープンスクールで、未来の後輩となる小学生やその保護者に配布される公式の学校案内パンフレット。これを、業者に任せるのではなく、生徒会のメンバーが主体となって企画から取材、デザイン、制作までを手掛けるという先進的な取り組みです。
生徒自身の言葉で語られる学校の魅力や、生徒が撮影した生き生きとした学校生活の写真は、どんなプロのライターやカメラマンが作ったものよりも、受験生の心にリアルに響きます。
この活動を通じて、生徒たちは自分たちの学校の魅力や課題を再認識することができます。さらに、写真撮影の技術、読者の心を引きつける文章力、情報を分かりやすく整理するデザイン力、そして仲間と協力して一つのものを創り上げる協調性など、将来社会で必ず役立つ多くのスキルを実践的に身につけることができる、非常に教育的価値の高い活動です。
まずは、生徒会新聞の延長として、学校の魅力を伝える特集ページを作成することから始めてみるのも良いでしょう。
周りの人を巻き込む企画の進め方
どんなに独創的で素晴らしい企画も、生徒会役員の熱意だけでは実現しません。
一般の生徒、クラスのリーダー、部活動のキャプテン、そして何よりも先生方といった、学校を構成する多くの人々を巻き込み、その理解と協力を得ることが、企画を成功へと導く絶対条件となります。
ここでは、企画を円滑に進め、多くの味方を作るための具体的な3つのポイントを、プロの視点から解説します。
1. 事前準備を徹底する
企画の成功は、準備段階で8割が決まると言っても過言ではありません。思いつきや勢いだけで「やります!」と宣言する前に、まずは冷静に企画の骨子を固める必要があります。そのために不可欠なのが、具体的で詳細な「計画書」の作成です。
計画書は、単なるアイデアメモではありません。企画の全体像を客観的に示し、関係者全員が共通の認識を持つための設計図であり、先生方に協力を依頼する際の公式なプレゼンテーション資料となります。
【最重要】計画書に必ず盛り込むべき8項目
- 企画の名称と目的:この企画で何を達成したいのかを簡潔に記述する。(例:「異学年交流ドッジボール大会」「目的:学年の垣根を越えた交流の促進と、体力向上」)
- 開催日時と場所:具体的な日時と、使用したい場所を明記する。
- 参加対象者:「全校生徒」「希望者のみ」など、対象範囲を明確にする。
- 具体的な内容とルール:企画の流れやルールを、誰が読んでも理解できるように具体的に記述する。
- 必要な物品と予算:必要なものをリストアップし、それぞれのおおよその費用を計算して、合計予算を算出する。
- 担当者の役割分担:「司会担当:〇〇」「備品準備担当:△△」のように、誰が何に責任を持つのかを明確にする。
- 当日のタイムスケジュール:準備から片付けまでの時間を分単位で計画する。
- 安全管理上の注意点:予想されるリスク(例:怪我、熱中症)と、それに対する具体的な対策を記述する。
この計画書を丁寧に作り込む過程で、企画の課題や準備すべきことが自ずと見えてくるはずです。
2. 先生や生徒の協力を取り付ける
完成した計画書を持って、まずは生徒会担当の先生に相談しましょう。先生は、学校全体の視点から、企画の問題点や改善点を的確に指摘してくれる最も身近なアドバイザーです。先生からのフィードバックを真摯に受け止め、計画書をさらにブラッシュアップしていきましょう。
また、他の生徒に協力を依頼する際には、コミュニケーションの仕方が非常に重要です。
「手伝って!」と漠然とお願いするのではなく、「この企画のポスターデザインを、イラストが得意なあなたにお願いしたい」「バスケ部のキャプテンとして、球技大会の審判を手伝ってもらえないか」というように、相手の得意なことや立場を尊重し、具体的な役割を提示することで、相手は「自分が必要とされている」と感じ、快く協力してくれる可能性が高まります。
3. 広報活動で期待感を高める
企画の存在を多くの人に知ってもらい、「そのイベント、面白そう!」「ぜひ参加したい!」という気持ちを高めるためには、戦略的な広報活動が不可欠です。告知のタイミングや方法を工夫することで、企画の効果を何倍にも高めることができます。
広報の基本は、段階的な情報解禁です。
例えば、開催の1ヶ月前には「近日、生徒会主催の大型イベント開催決定!」というティザーポスターを掲示して謎めいた予告をし、2週間前に企画の全貌をポスターや校内放送で発表、そして開催直前にはリマインドの放送を行う、といった流れが効果的です。
このプロセスを通じて、生徒たちの期待感を徐々に醸成していくのです。
広報物では、単に日時や場所といった情報を伝えるだけでなく、「この企画に参加することで、どんな楽しい体験ができるのか」「どんなメリットがあるのか」を魅力的に伝えることを意識しましょう。
「クラスの団結が深まる!」「豪華景品ゲットのチャンス!」といった、参加意欲を刺激するキャッチコピーを考えるのも、生徒会の腕の見せどころです。
実行に移そう!中学校の生徒会の新しい取り組み例

- 活動の基盤となる委員会人気ランキング
- 立候補で使える生徒会選挙の公約の例文
- 心に響く応援演説の例文のポイント
- 企画を実現するための手順と注意点
- まとめ:中学校の生徒会で新しい取り組み例に挑戦
活動の基盤となる委員会人気ランキング
生徒会は、会長や副会長といった本部役員だけでなく、学校生活の様々な側面を支える専門委員会の活動によって成り立っています。
どの委員会に人気が集まるかは、その学校の伝統や行事の特色によって異なりますが、一般的には、体育祭や文化祭といった、学校全体が一体となって盛り上がる大きなイベントの企画・運営に中心的に関わる委員会に、多くの生徒の関心と希望が集まる傾向が見られます。
例えば、「体育委員会」や「文化委員会(学校によっては行事委員会や学芸委員会)」、「放送委員会」などは、イベントの成功を左右する重要な役割を担うため、達成感ややりがいを強く感じられることが人気の理由でしょう。自分たちのアイデアや働きかけで、学校全体の感動や興奮を創り出せることは、何物にも代えがたい経験となります。
一方で、図書委員会、保健委員会、美化委員会といった、日々の学校生活の基盤を地道に支える委員会の活動も、学校運営には絶対に欠かせない重要な存在です。これらの委員会は、目立つ活動は少ないかもしれませんが、全ての生徒が快適で安全な学校生活を送るための環境を整えるという、極めて重要な役割を担っています。
どの委員会活動も、責任感や協調性、問題解決能力といった、社会で生きる上で必要な力を育む貴重な学びの場です。
| 委員会名 | 主な活動内容 | 活動のやりがい | 求められるスキル |
|---|---|---|---|
| 体育委員会 | 体育祭の企画運営、ルールの策定、体育倉庫の備品管理、昼休みのボール貸出など。 | 学校で最も盛り上がる行事の一つを、自分たちの手でゼロから作り上げる大きな達成感。 | リーダーシップ、企画力、体力 |
| 文化委員会 | 文化祭や合唱コンクールの企画運営、テーマやスローガンの決定、ポスター作成、当日の進行管理など。 | クラスや学年の団結力を引き出し、文化的な活動を通じて学校全体の感動的な場面を演出できる。 | 創造力、調整能力、デザインスキル |
| 放送委員会 | 朝や給食、下校時の定時放送、学校行事での司会進行や音響・照明操作など。 | 自分の声や選曲、言葉で学校全体の雰囲気を演出し、情報を的確に全校に伝える重要な役割を担う。 | 表現力、コミュニケーション能力、機材操作スキル |
| 図書委員会 | 図書の貸出・返却業務、蔵書点検、図書だよりの発行、新刊図書の紹介や展示企画など。 | 静かで知的な環境で本に囲まれて活動でき、おすすめの本を通じて友達に新しい世界を紹介できる。 | 正確性、探求心、整理整頓能力 |
| 美化委員会 | 校内の清掃状況のチェック、美化コンクールの企画、ゴミの分別指導、ワックスがけの準備など。 | 自分たちの手で学校をきれいにすることで、全校生徒の学習環境を快適に保つという縁の下の力持ち。 | 責任感、継続力、奉仕の精神 |
最終的に大切なのは、「人気があるから」という周囲の評価で選ぶのではなく、自分自身がどの活動に本当に興味を持ち、三年間責任を持って真剣に取り組めるかを自問自答することです。
その選択こそが、あなたの中学校生活をより一層充実させることにつながります。
立候補で使える生徒会選挙の公約の例文
生徒会選挙は、学校の未来を担うリーダーを選ぶ重要な機会です。立候補者にとって、自分の考えや情熱を全校生徒に伝え、支持を得るための最も強力な武器が「公約」です。
有権者である生徒たちに「この人なら、私たちの学校を本当に良くしてくれそうだ」と信頼してもらうためには、夢物語ではない、具体的で実現可能な公約を練り上げることが絶対条件となります。
ここでは、有権者の心をつかむ良い公約のポイントと、そのまま使える具体的な例文をカテゴリ別に詳しく紹介します。
良い公約が満たすべき3つの条件
- 具体性(What):「学校を楽しくする」というような曖昧なスローガンではなく、「昼休みの中庭に、誰でも自由に使えるスピーカーを設置し、音楽を聴けるようにします」というように、何をするのかが情景として目に浮かぶレベルで具体的であること。
- 実現可能性(How):「修学旅行の行き先をハワイにする」といった、予算や安全面から明らかに実現不可能な提案ではなく、生徒会の権限や先生方との交渉の中で実現できる範囲の公約であること。そのためには、事前のリサーチが不可欠です。
- 共感性(Why):一部の生徒だけが喜ぶような内容ではなく、多くの生徒が日頃から感じている不満や願いに応えるような、ニーズに合った内容であること。「確かに、それは良い考えだ!」「やってほしい!」と多くの生徒から共感を得られるかが勝負の分かれ目です。
【カテゴリ別】心を動かす公約の例文集
【学校生活の質的向上カテゴリー】
- 現在、形骸化しがちな目安箱を「デジタル目安箱」に移行し、投書された全ての意見に対して、1週間以内に生徒会としての見解や進捗状況を、生徒会新聞および掲示板で回答することを約束します。皆さんの声を絶対に無視しません。
- 冬の寒さ対策として、現在の校則を見直し、健康管理の観点から、式典などを除く通常授業日において、各自の判断でカーディガンやウィンドブレーカーなどの防寒着を制服の上から着用できる試行期間を設けるよう、学校側に強く提案します。
【学校イベントの革新カテゴリー】
- 毎年同じ種目になりがちな体育祭に、生徒からのアンケートで最も票を集めた「障害物競走」や「玉入れ」などの新しい競技を一つ導入し、マンネリを打破します。
- 文化祭において、各クラスの展示やステージ発表の魅力をより多くの人に伝えるため、生徒会が運営する公式YouTubeチャンネル(限定公開)を開設し、準備風景のドキュメンタリーやクラス代表によるPR動画を配信します。
絶対に避けるべきNG公約の例
「校則を全て撤廃します」「スマートフォンの校内での使用を完全に自由にします」といった、聞こえは良いものの、学校の秩序や安全を考えると実現が極めて困難な公約は、無責任で現実を見ていないという印象を与えかねません。
校則に疑問がある場合は、「なぜそのルールがあるのか」を調べた上で、「〇〇という目的を達成するために、現在の△△というルールを、□□という新しいルールに変更することを提案します」と、具体的な代替案とセットで建設的に示す姿勢が、真のリーダーとして評価されます。
心に響く応援演説の例文のポイント

応援演説は、単に立候補者を褒めるだけの場ではありません。立候補者の人柄や隠れた魅力を、有権者である生徒たちに生き生きと伝え、心を動かし、「この人に投票したい」と思わせるための、選挙戦における重要なスピーチです。
成功の鍵は、抽象的な賞賛の言葉を並べるのではなく、聴衆が思わず引き込まれるような、具体的で共感できるエピソードを盛り込むことにあります。
聴衆を惹きつける応援演説の基本構成
- 挨拶と関係性の提示:「皆さん、こんにちは。〇年〇組の△△です。私が応援する□□君とは、小学校からの親友です。」というように、自分が誰で、候補者とどのような関係なのかを明確に述べ、話の信頼性を高めます。
- 人柄を象徴する具体的なエピソード:これが演説の核心部分です。「彼はリーダーシップがあります」と結論から言うのではなく、「昨年の体育祭の準備で、クラスの意見がまとまらず雰囲気が最悪になった時、彼は一人ひとりの意見を根気強く聞き出し、『この二つの案の良いところを合わせるのはどうかな?』と、誰もが納得できる新しい提案をしてくれました。あの時の彼の調整力と誠実さがなければ、私たちのクラスはバラバラのままだったでしょう。」というように、具体的な情景を描写します。
- 未来への期待感の醸成:語ったエピソードと候補者の公約を結びつけ、「あの時のように、彼は必ず全校生徒の多様な意見に耳を傾け、学校をより良い方向へ導いてくれるはずです」と、候補者が当選した後の明るい未来を聴衆に想像させます。
- 力強い締めとお願い:「この学校の未来を、私たちの学校生活を、安心して任せられるのは□□君しかいません。皆さん、どうか□□君に、あなたの大切な一票を託してください。よろしくお願いします!」と、自信を持って、そして誠実に投票を呼びかけ、演説を締めくくります。
ユーモアと誠実さを両立させた演説例文
皆さん、こんにちは!〇年〇組の△△です。私が応援するのは、ご存知、□□君です。皆さんは□□君というと、いつもニコニコしていて、ちょっとおっちょこちょいなイメージがあるかもしれません。確かに、彼はこの前も、社会の先生の面白くないジョークに、教室で一番大きな声で笑ってあげて、逆に先生を困らせていました。そんな、どこまでも優しい男です。
でも、私が彼を推薦する理由は、ただ優しいからだけではありません。彼の本当の強さは、その優しさの裏にある「行動力」です。
以前、私たちのクラスで、車椅子を使っている友人が教室の移動で困っていたことがありました。多くの人が「大変そうだね」と声をかけるだけで終わっていた中、□□君は違いました。彼はすぐに先生方に相談し、クラスの皆に呼びかけて、その友人が通りやすいように教室の机の配置を変えることを提案し、実行してくれたのです。
彼のすごいところは、誰かの「困った」を、見て見ぬふりしないことです。そして、文句を言うのではなく、どうすれば解決できるかを考え、すぐに行動に移せることです。この、小さな声に耳を傾ける優しさと、それを解決するための具体的な行動力こそ、今の私たちの生徒会に最も必要な力ではないでしょうか。
□□君が生徒会長になったら、私たちの学校はきっと、誰もが安心して過ごせる、もっと温かい場所になります。そして、私たちの「こうだったら良いのに」という小さな声が、実現に向けて動き出すはずです。皆さん、この学校の未来のために、ぜひ、□□君に清き一票をよろしくお願いします!
このように、親しみやすい導入から入り、具体的なエピソードで信頼性を示し、未来への期待感へと繋げるストーリーテリングが、聴衆の心を動かすのです。
企画を実現するための手順と注意点
中学校の生徒会で新しい取り組みを成功させるためには、情熱やアイデアだけでなく、それを着実に形にしていくための現実的な手順を理解し、実行することが不可欠です。
ここでは、企画を単なる「夢物語」で終わらせず、「実現」へと導くためのプロフェッショナルな4つのステップ(PDCAサイクル)と、それぞれの段階での重要な注意点を詳しく解説します。
Step1:企画書を作成する(Plan:計画)
全ての活動の出発点であり、最も重要な工程です。頭の中にある漠然としたアイデアを、誰が読んでも理解できる客観的な資料、すなわち「企画書」として文書化します。
この企画書は、生徒会役員内での共通認識を形成するだけでなく、先生方に企画の意図と安全性を説明し、公式な承認を得るための最重要ツールとなります。
【プロレベルの企画書】必須項目と記述のポイント
- 企画名と目的:「なぜこの企画をやるのか?」を明確に。例:「新入生と在校生の交流促進を目的とした、異学年混合ドッジボール大会」
- 目標(ゴール):「何がどうなれば成功か?」を具体的に。例:「新入生の8割以上が『楽しかった』と回答する」「上級生と話すきっかけができた新入生が5割を超える」
- 日時・場所・対象者:基本的な情報を正確に記載。
- 内容・ルール:時系列に沿って、企画の流れを具体的に記述。曖昧な表現は避ける。
- 予算計画:必要な物品をリストアップし、単価と数量、合計金額を明記。生徒会費から支出するのか、別途徴収するのかも示す。
- 役割分担と責任者:役員それぞれの担当業務(広報、備品、司会など)と、全体の責任者を明確にする。
- リスク管理:予想されるトラブル(怪我、熱中症、備品の破損など)と、それに対する具体的な予防策・対応策を記述する。
特に「リスク管理」の項目を丁寧に記述することで、先生方からの信頼を得やすくなります。
Step2:先生に相談し、承認を得る(Do:実行、ただしここでは交渉)
完成度の高い企画書を作成したら、まずは生徒会担当の先生にアポイントメントを取り、プレゼンテーションを行います。
先生は、長年の経験から生徒が見落としがちな問題点や、より良い企画にするためのアイデアを提供してくれる、最も頼りになるアドバイザーです。先生からの指摘や助言を真摯に受け止め、企画書を修正・改善していきましょう。
担当の先生の了承が得られたら、次のステップは学校全体の公式な承認を得るための「職員会議」です。この場では、企画の楽しさや盛り上がりをアピールする以上に、その教育的意義と安全対策を論理的に説明することが求められます。
先生方を説得する交渉のコツ
「この企画は、学習指導要領にある『主体的な態度の育成』や『協同して学ぶ喜び』を生徒が実践的に学ぶ絶好の機会となります」「安全対策として、当日は各ポイントに教員1名と生徒会役員2名を配置し、救護担当として保健委員も待機させます」といったように、教育的な視点と具体的な安全管理計画を強調することで、先生方は安心して企画を承認しやすくなります。
Step3:役割分担をして準備を進める(Do:実行)
学校からの承認が無事に下りたら、いよいよ本格的な準備期間に突入します。計画書に基づき、各担当者が責任を持って自分の役割を果たしていきます。企画の規模が大きい場合は、生徒会役員だけでなく、クラスや部活動から有志の協力スタッフを募り、「実行委員会」を組織するのも非常に有効な手段です。
多くの人を巻き込むことで、企画はよりダイナミックになり、全校的なイベントとしての機運が高まります。
Step4:アンケートなどで活動を振り返る(Check & Action:評価・改善)
イベントが無事に終了しても、それで終わりではありません。本当の意味での成功は、この最後のステップにかかっています。やりっぱなしにせず、必ず活動の「振り返り」を行い、次へと繋げることが重要です。参加した生徒を対象に、Googleフォームなどを活用した無記名アンケートを実施し、「企画の満足度」「最も楽しかった点」「改善してほしい点」などを数値と自由記述で集めます。
まとめ:中学校の生徒会で新しい取り組み例に挑戦
この記事では、中学校の生徒会活動をこれまで以上に活性化させ、全校生徒にとって意義深いものにするための、新しい取り組みの具体的なアイデアから、それを実現するための詳細な手順までを網羅的に解説しました。
最後に、この記事で紹介した重要な要点をリスト形式で振り返ります。このまとめが、皆さんのこれからの活動の道標となれば幸いです。
- 生徒会の新しい取り組みを成功させる最大の鍵は「全校参加型」であること
- 面白いイベント企画は学校生活に彩りを与え、生徒と先生の一体感を高める
- 生徒会vs先生の対決企画は、世代間のコミュニケーションを活性化させる特効薬となる
- フォトコンテストやスタンプラリーは、学校という空間を新たな視点で楽しむきっかけを作る
- 「〇〇の日」のような小規模でユニークなイベントは、日常のマンネリ化を防ぐ良いアクセントになる
- デジタル目安箱の活用は、これまで届かなかった生徒の正直な声を聞くための強力なツールである
- 生徒会の活動は「社会貢献」「地域連携」「校内交流」の3つの軸で考えると視野が広がる
- 高校の先進的な取り組み事例は、自分たちの活動の可能性を広げるための貴重なヒントの宝庫である
- どんな企画も、成功の8割は「目的」「予算」「リスク管理」を盛り込んだ詳細な計画書の質で決まる
- 周囲を巻き込むためには、具体的な役割を示して協力を依頼し、段階的な広報で期待感を醸成することが重要
- 説得力のある公約とは「具体的」で「実現可能」かつ多くの生徒が「共感」できるものである
- 聴衆の心を動かす応援演説は、抽象的な賞賛ではなく、人柄が伝わる具体的なエピソードで構成する
- 企画の実現は「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」のPDCAサイクルを意識する
- 企画書は、先生方に教育的意義と安全対策を論理的に説明するための最重要プレゼン資料である
- 活動の振り返りをアンケートや報告書として記録に残すことが、生徒会の伝統と未来を築く礎となる


