新学期や選挙の時期になると、「生徒会の役職一覧」って検索する学生さん、結構多いんじゃないかなと思います。生徒会に立候補してみたいけど、そもそもどんな役職があるんだろう?中学や高校で活動内容に違いはあるのかな?とか、生徒会長や書記、会計といった役職の具体的な仕事内容がわからないと、自分に何が向いているか判断しづらいですよね。
「生徒会長って、全校生徒の前で話す以外に何するの?」「書記って地味そう…」「会計ってお金が合わなかったらどうしよう?」なんて、具体的なイメージが湧かないと不安になるかもしれません。
それに、どうやって決めるのかという決め方や、立候補に必要な選挙のルール、そしてやっぱり気になるのが、生徒会活動が内申点にどう影響するのか…なんてところも、ぶっちゃけ知りたいポイントだと思います。
この記事では、そうした疑問をまるっと解決できるように、生徒会の役職リストからそれぞれの役割、立候補の方法、活動のメリットまで、私が知っていることを幅広く、そして詳しくカバーしていきますね。
- 生徒会の組織と役職の全体像
- 生徒会長・副会長・書記・会計の具体的な仕事
- 役員になるための選挙プロセスとルール
- 生徒会活動が内申点や受験に与える影響
生徒会の役職一覧と組織図
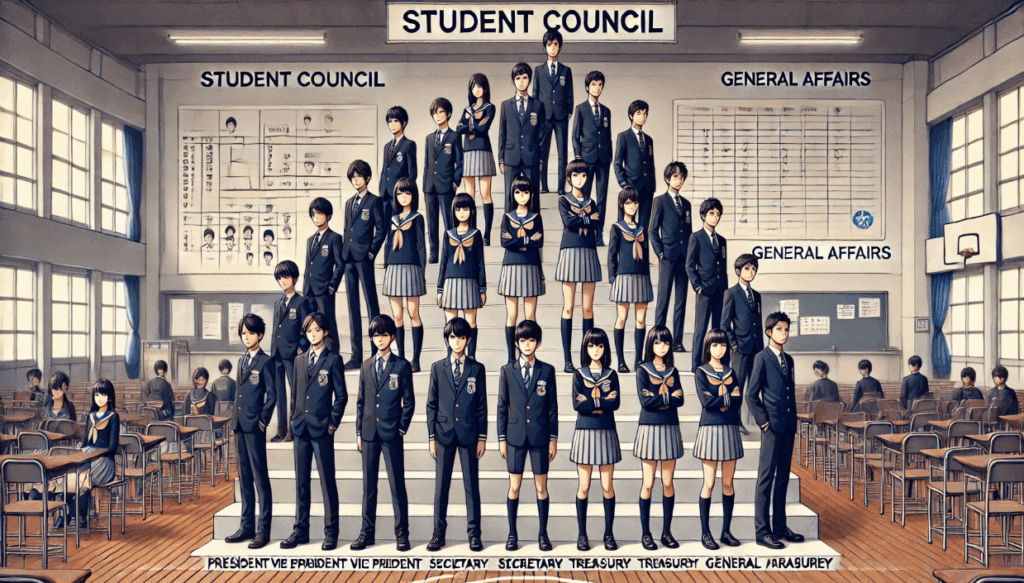
まずは、「生徒会」という組織がどうなっているのか、その全体像から見ていきましょう。「生徒会役員」というと、会長や副会長といった「執行部」のメンバーを思い浮かべる人が多いかなと思います。でも実は、生徒会というのはもっと大きな枠組みで、執行部はその中の一部なんですよ。この「組織図」をイメージできると、各役職の役割がグッと理解しやすくなります。
生徒会の役職の種類と役割
学校によって少し名前が違うかもしれませんが、生徒会活動の中心を担う「生徒会執行部(役員会)」には、だいたい以下のような役職が設置されていますね。
| 役職名 | 主な役割(概要) | こんな人に向いているかも? |
|---|---|---|
| 生徒会長 | 生徒会の最高責任者。学校の代表として活動全体をまとめる。 | リーダーシップがある人、人前で話すのが得意な人 |
| 副会長 | 会長の補佐役。会長不在時の代理も務め、実務を調整する。 | サポート役が得意な人、広い視野を持てる人 |
| 書記 | 会議の議事録作成や、生徒会だより発行などの「記録」と「広報」担当。 | コツコツ作業できる人、文章を書くのが好きな人 |
| 会計 | 生徒会費(予算)の管理・運営を担当する「財務」責任者。 | 数字に強い人、責任感があり正確な作業ができる人 |
| 総務・庶務 | 他の役職のサポートや連絡調整など、多岐にわたる業務を担当。 | 臨機応変に対応できる人、「何でも屋」として動ける人 |
「一覧」として見るとこんな感じです。総務や庶務は、学校によっては設置されず、書記が兼任したり、副会長が調整役を担ったりすることもあります。逆に、書記から「広報」が独立して、ポスター作成やSNS更新を専門に担当する学校もあるみたいですね。
そして大事なことですが、「生徒会」=「生徒会執行部」ではありません。本来、生徒会というのは、その学校の生徒全員が会員となって構成される「自治組織」なんです。つまり、生徒全員が生徒会のメンバーなんですね。その中で、選挙で選ばれた代表者(執行部)が、みんなの意見を吸い上げて、学校生活を良くするための企画を「実行」していく中心的な役割を担っている、というわけです。
生徒会長と副会長の仕事内容
では、執行部の中でも特に中心となる生徒会長と副会長の仕事内容を、もう少し深掘りしてみましょう。
生徒会長:学校の「顔」であり「最高責任者」
生徒会長は、まさに学校の「顔」であり、リーダーですね。全校生徒の前で話す機会も多いですし、その言動は常に注目されます。
- 全校生徒の代表としての役割:朝礼や始業式・終業式での挨拶、新入生歓迎会や卒業式での送辞・答辞など、生徒を代表してスピーチします。また、全校生徒からの意見や要望を集約する仕組み(目安箱の設置など)を作り、それを集約する役割も担います。
- 学校側との「交渉役」:集約した生徒の意見を、顧問の先生や、時には校長先生・教頭先生との「代表者会議」のような場で伝え、学校運営の改善を求める「交渉役」でもあります。校則の見直しなどを議題にすることも。
- 行事の最高責任者:体育祭や文化祭、球技大会といった学校行事では、実行委員会のトップとして、全体の統括や運営を主導します。各委員会の調整や、長期休暇中の部活動の体育館割り当て調整など、地道な実務も多いです。
強いリーダーシップと、全校生徒をまとめる情熱、そして先生方とも対等に渡り合える調整力が求められる、大変ですが最もやりがいのある役職と言えるでしょう。
副会長:会長を支える「扇の要」
一方、副会長は、そんな生徒会長の最強のサポート役です。会長が「表」の顔として動くことが多いのに対し、副会長は「裏」の実務を支える「扇の要」とも言える存在ですね。
- 会長の「代理」と「補佐」:会長の仕事のサポートが基本です。会長が他の会議や校外活動で不在の時には、その代理として挨拶をしたり、会議の議長を務めたりします。
- 内部の実務管理(プロジェクトマネージャー):会長が学校側との交渉や全体方針の決定に時間を使う一方、副会長は執行部内部のタスク管理や、各専門委員会との進捗管理を担当することが多いです。会長が「こんな学校にしたい!」というビジョンを示し、副会長が「じゃあ、そのために書記はこれを、会計はこれを、体育委員会はこれをいつまでにやろう」と具体的な実行計画に落とし込むイメージです。
会長のような目立つリーダーシップとは別に、一歩引いた視点で全体を見渡し、実務を冷静に管理・調整する能力が求められます。会長と副会長のコンビネーションが生徒会活動の質を決めると言っても過言ではないですね。
書記の仕事内容とは?

「書記」と聞くと、ただ会議のメモを取るだけ…みたいに地味なイメージがあるかもしれません。でも、実は生徒会活動の「土台」を支える、すごく重要なポジションなんです。
書記の2大ミッション
- ミッション1:記録(アーキビスト):執行委員会や各委員会の会議に出席し、「何が話し合われ、何が決まったのか」を議事録として正確に残します。これは単なるメモではなく、生徒会の「公式な決定事項」として保存されるものです。これがないと活動が前に進みませんし、後で「言った・言わない」のトラブルにもなりかねません。
- ミッション2:広報(PR):生徒会新聞(例:「二中のビッグショ-」みたいな名前がついていることも)の作成・発行や、活動報告の掲示物作成など、生徒会の活動を全校生徒に「発信」する役割も担います。活動の「透明性」を保ち、生徒会活動への関心を持ってもらうための大事な仕事です。
質の高い「記録」と「広報」とは?
議事録は、ただ会話を全部文字起こしすれば良いわけではありません。「いつ」「誰が」「何を話し合い」「何が(なぜ)決まったのか」が、後から読んでも分かるように、簡潔に箇条書きなどでまとめるスキルが求められます。過去の議事録を参照し、活動の「継続性」を保つ役割もあるんですよ。
また、広報活動も重要です。生徒会新聞や掲示物が、読みにくかったり、面白くなかったりすると、せっかくの活動も全校生徒に伝わりません。「どう伝えたら、みんなが読んでくれるか?」を考える、見る人の立場に立った広報が求められます。最近では、学校の許可を得て、生徒会独自のWebサイトやSNSを更新するケースもあるかもしれませんね。
その他、各種プリントの印刷や、行事ごとの係一覧表の作成など、活動に必要な文書管理全般を担当します。文章を書くのが好きだったり、パソコン作業(WordやExcel、PowerPointなど)が得意だったりする人に向いているかも。
会計の仕事内容と責任
会計は、ズバリ「お金」の専門家です。全校生徒から集めた大切な生徒会費(予算)の管理・運営を担う、とっても責任のある役職です。会長や書記とはまた違った緊張感がありますね。
主な仕事は、大きく分けて3つのステップになります。
1. 予算案の作成(プランニング)
年度の初めに、各部活動や専門委員会から「今年はこれくらいのお金が必要です」という要望書(予算要求)を集めます。しかし、生徒会費の総額は決まっていますから、全ての要望を鵜呑みにはできません。会長や副会長、顧問の先生と相談しながら、「体育祭にはこれくらい」「あの部活にはこれくらい」と、公平かつ効果的にお金を割り振る「予算案(予算書)」を作成します。これは生徒議会や生徒総会で承認を得る必要があります。
2. 日常の出納管理(モニタリング)
予算が決まったら、次はその予算が正しく使われているかを日々チェック(出納管理)します。部活動や委員会から「備品を買いたい」と申請があれば、予算の範囲内かを確認して出金を許可し、必ず領収書を回収して帳簿に記録します。「今、生徒会費がいくら残っているか」を常に把握しておく必要があります。
3. 決算報告(アカウンタビリティ)
年度の終わり(または任期の終わり)には、「今年度は、みなさんから集めた生徒会費を、このように使いました」という「決算報告」を作成し、生徒総会などで全校生徒に報告します。これは、生徒会活動の透明性を担保し、会員(全校生徒)への説明責任を果たすための非常に重要な仕事です。
会計の最大の違いは、やはり「1円単位でのお金を扱うこと」です。全校生徒の「お金」を預かるという責任の重さがあり、数字に強く、コツコツと正確な作業ができる人が求められます。学校運営の「財務」を間近で学べる、貴重な経験ができる役職ですね。
執行部以外の委員会と議会
さて、ここまで執行部(役員)の話が中心でしたが、冒頭でお話しした通り、生徒会は執行部だけで動いているわけではありません。ここも大切なポイントです。
-
専門委員会
- 執行部が活動全体を「統括」するのに対し、具体的な学校行事や日常業務の「実務」を担うのが専門委員会です。クラスから選ばれた委員で構成されますね。
-
- 文化学芸委員会:文化祭(学芸会)の企画・運営、文集の作成など。
- 体育委員会:体育祭や球技大会の運営補佐、体育倉庫の管理など。
- 環境美化委員会:ゴミの分別管理、清掃用具の管理、ワックスがけの計画など。
- その他:風紀委員会(あいさつ運動など)、企画広報委員会、そして選挙を運営する「選挙管理委員会」などが設置されます。
生徒会長や副会長の「リーダーシップ」とは、具体的にはこれらの専門委員会と良好な関係を築き、学校行事を成功に導くための「調整能力」と「実行力」であると言えます。
-
生徒議会(または中央委員会・代議委員会)
- 各クラスから選出された議員(学級委員長などが兼ねることも多い)が集まる組織です。学校生活に関する重要な議案(例:校則の変更、予算案の承認など)を審議し、「議決」する役割を持ちます。国会のようなイメージですね。執行部は、この生徒議会で議決された事項を、専門委員会と協力しながら「実行に移す」という重要な役割も担っています。
-
生徒総会
- 生徒全員によって構成される、形式上の「最高議決機関」です。予算や決算の承認、活動方針の決定などがここで行われます(学校によっては、実質的な審議は生徒議会で行われることも多いですが)。
このように、生徒会は「執行部(実行)」「議会(議決)」「委員会(実務)」が連携し合って成り立っているんですね。
生徒会の役職一覧への道とメリット

さて、役職の仕事内容や組織の全体像がわかってきたところで、次はいよいよ「どうすれば役員になれるのか?」というプロセスと、「役員をやったらどんないいことがあるの?」という、みんなが一番知りたい(かもしれない)実践的な話に移っていきましょう。
生徒会の役職の決め方と選挙
多くの学校では、生徒会役員(執行部)は、全校生徒による選挙によって選ばれますね。これが一番メジャーな「決め方」だと思います。
選挙の時期(年に1回か、前期・後期で2回か、学校によります)が近づくと、生徒会とは独立した組織として「選挙管理委員会(選管)」が設置されます。選管が、選挙の日程やルール(公示)を発表し、立候補の受付を開始します。
もし立候補者が定員内(例:副会長の定員2名に対し、立候補者が2名)だった場合は、無投票当選…ではなく、「信任投票」が行われることが多いです。これは、「その候補者で良いですか?」と全校生徒の賛成・反対を問う投票で、規定の賛成票(例:有効投票数の過半数)を得なければ当選できません。
立候補と推薦責任者のルール
役員に「なりたい!」と思ったら、まずは期間内に選挙管理委員会に立候補の届け出を行う必要があります。その際、いくつかのルールがあります。
立候補の資格
学校によっては、「1年生は書記と会計のみ」とか「生徒会長は2年生から」といった学年に関する資格が定められている場合があります。まずは自分の学校の「生徒会選挙規定」をしっかり確認することがスタートラインですね。
推薦責任者と推薦人
立候補の際、多くの学校で「推薦責任者」を1名(または複数名)立てるルールになっています。
推薦責任者とは、「この候補者を、私が責任を持って推薦します!」と応援してくれる人のこと。立候補の届け出に同行するだけでなく、後述する「立会演説会」で候補者の応援演説者となる、非常に大事なパートナーです。
中学生の推薦責任者の演説の例文は別記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね!
選挙の公平性を保つために、選挙管理委員の人は推薦責任者になることはできませんし、立候補者自身が他の候補者の推薦責任者になることも禁じられています。
さらに、学校によっては「推薦人10名以上の署名を集めること」といった、より複雑な立候補要件が定められている場合もあります。誰に推薦責任者を頼むか、推薦人を集められるか、というのは選挙戦における最初のハードルですね。
選挙運動と演説のポイント

立候補が受理されたら、いよいよ選挙運動期間のスタートです。これも、実際の選挙のミニチュア版みたいで面白いところ。ただし、ルールは厳格に決まっています。
ポスター運動とその他の活動
選挙運動といえば、まずはポスターですね。
- 掲示場所・枚数:ポスターは、決められた場所(例:昇降口の掲示板、各階の廊下など)に、決められた枚数(例:3枚以内)だけ掲示できます。公平性を保つためですね。
- 検印:使用するポスターは、無許可の掲示やルール違反を防ぐため、事前に「選挙管理委員会の検印」を必要とすることがほとんどです。
- その他の運動:学校によっては、朝のあいさつ運動(タスキをかけて)や、お昼の放送での演説などが許可されている場合もあります。
立会演説会:最大の決戦場
選挙運動のハイライトは、なんといっても全校生徒の前で行われる「立会演説会」です。ここで、候補者本人による演説と、推薦責任者による応援演説が行われます。
演説では、ただ「頑張ります!」「清き一票を!」と叫ぶだけでは、なかなか票にはつながりません。
演説で伝えるべきこと
- なぜ立候補したのか(動機・学校への想い)
- 今の学校の何が課題だと思うか(現状分析)
- 当選したら、具体的に何をするか(公約)
- その公約は、どうすれば実現できるか(実現可能性)
特に重要なのは、「具体性」と「実現性」です。単なる理想論ではなく、「生徒の声を聞くために目安箱をデジタル化します」とか「球技大会の種目をアンケートで決めます」といった、みんながイメージできる具体策を提示することが大切です。
ちなみに、生徒会選挙のルールは、実際の「公職選挙法」の精神(選挙運動の機会均等と公正さ)を学ぶ「民主主義のシミュレーション」としての側面も持っています。(出典:総務省「選挙運動」)
とはいえ、人前で話すのは緊張しますよね。もしスピーチに苦手意識があるなら、こちらの記事も参考にしてみてください。
生徒会選挙の応援演説の例文|中学生・高校生別の面白ネタとスピーチ術
生徒会役職と内申点への影響
ここ、すごく気になっている人も多いと思います。「生徒会長になったら、内申点は上がりますか?」という質問ですね。これは、半分ホントで、半分誤解、といったところでしょうか。
内申点への影響:神話と現実
まず知っておいてほしいのは、「生徒会長になったから、自動的に内申点が+5点」といった、役職に就いたこと自体が直接的な点数として加算されることは少ないということです。もしそうだとしたら、それは公平じゃないですよね。
では、なぜ「生徒会は内申点に良い」と言われるのか? それは、活動の「過程」が評価されるからです。
先生方は、あなたが役員として活動する姿を日々見ています。その中で、
- 学校全体のために、自ら進んで行動した(主体性)
- 意見の違う仲間と協力して、体育祭などの行事を成功に導いた(協調性・リーダーシップ)
- 地道な作業や困難な課題にも、投げ出さずに最後まで取り組んだ(責任感)
こうした「目に見えない資質」が、先生方によって高く評価されます。その結果として、内申書(調査書)の評価項目である「関心・意欲・態度」や「主体的に学習に取り組む態度」といった部分に、間接的にプラス評価として反映される、というのが実情に近いと思います。
内申書のどこに書かれる?
具体的には、内申書の「特別活動の記録」や「総合所見」といった欄に、「生徒会長として体育祭の運営に尽力し、成功に導いた」といった具体的な事実が記載されることがあります。
もちろん、高校入試、特に推薦入試や面接試験においては、この「生徒会長だった」という経験は、自己PRの強力な武器になります。「生徒会長としてこんな課題があり、仲間とこう乗り越えました」という具体的なエピソードは、あなたのリーダーシップや問題解決能力を証明する最高の材料になりますからね。
活動で得られるメリットと成長
内申点への影響以上に、生徒会活動で得られる「経験」は、本当に大きな財産になると私は思います。はっきり言って、勉強だけでは絶対に学べないスキルが満載です。
役員になると、当然ながら、同学年だけでなく先輩・後輩、そしてたくさんの先生方と関わることになります。
1. リーダーシップと責任感
「会長」や「副会長」といった役職名は、自然とあなたに「まとめ役」としての行動を求めます。最初は自信がなくても、活動を通じて、人をまとめる力や、任された仕事をやり遂げる強い責任感が鍛えられます。
2. コミュニケーション能力と調整力
生徒会活動は、意見のぶつかり合いの連続です。「A案がいい」「いやB案だ」と対立することも日常茶飯事。その中で、多様な意見を尊重しながら対話し、落としどころを見つけて合意形成を図るスキルが磨かれます。これは社会に出てから最も役立つ能力の一つかもしれません。
3. 問題解決能力と実行力
「行事の参加者が少ない」「予算が足りない」といった様々な問題に直面します。そのたびに、「じゃあ、どうする?」と知恵を絞り、解決策を考えて実行に移す。このプロセスは、まさに生きた「問題解決学習」ですね。
4. タイムマネジメント能力
生徒会活動は、当然ですが放課後や休み時間を使います。つまり、勉強との両立が必須。どうやって時間を見つけて勉強するか、効率よくタスクをこなすか、自然とタイムマネジメント能力が身につきます。
もちろん、大変なことも多いです。意見がまとまらずに会議が長引いたり、先生と意見が対立したり、勉強時間が削られて焦ったり…。でも、そうした困難を仲間と協力して乗り越えた時の達成感は、きっと忘れられない「毎日が思い出」となるような充実感をもたらしてくれるはずです。
まとめ:生徒会の役職一覧から見る経験価値
さて、ここまで「生徒会 役職 一覧」から始まって、組織の仕組み、仕事内容、選挙、そしてメリットと、詳しく見てきました。
あなたが今「一覧」を調べているのは、なぜでしょうか? もしかしたら、内申点のため、受験のため、という理由も少しはあるかもしれません。それも大事な動機の一つだと思います。
でも、もし「内申点のためだけ」で役員になると、活動が大変になった時に「何でこんなことやってるんだろう…」と辛くなってしまうかもしれません。
生徒会活動の最大の価値は、内申書に書かれる「一行」ではなく、学校生活の「傍観者」から「主体者」へと意識が変わり、学校を自分たちの力でより良くしようと行動する「経験」そのものにあります。
どの役職に就いたとしても、いや、たとえ選挙で落ちてしまったとしても、学校のことを真剣に考えて行動しようとした経験そのものが、あなたの視野を広げ、責任感を育ててくれます。その過程で培われるリーダーシップや対話能力は、高校進学後や社会に出てからも役立つ、勉強だけでは得られない「人生の財産」になるでしょう。
この記事が、あなたにピッタリの役職を見つけ、「ちょっと勇気を出して立候補してみようかな」と一歩踏み出すきっかけになったら、こんなに嬉しいことはありません!


