生徒会選挙への立候補、その勇気ある一歩を踏み出したものの、「生徒会の公約が思いつかない…」と、期待と不安の中で頭を抱えてはいませんか。
特に中学生や高校生にとって、大勢の生徒の前で語るべきビジョンを形にし、他の候補者と差がつくようなインパクトのある面白いアイデアや、誰もがはっとする斬新な視点を見つけ出すのは、決して簡単なことではありません。
この記事では、そんなあなたの真剣な悩みに寄り添い、具体的な公約例の案を一覧で網羅的に紹介します。それだけでなく、アイデアを生み出す思考のプロセスから、当選をぐっと引き寄せる演説でのおすすめの書き方まで、段階的に徹底解説していきます。
この記事を最後まで読めば、漠然とした不安は具体的な自信に変わり、あなたにぴったりの公約がきっと見つかるはずです。
- 公約が思いつかない根本的な原因と、乗り越えるための具体的な解決策
- 中学生・高校生それぞれの視点に立った公約アイデア
- 他の候補者と差がつく斬新な公約の見つけ方
- 当選を確実なものにするための公約の書き方とプレゼンテーション術
生徒会の公約が思いつかない悩みを解決する思考法
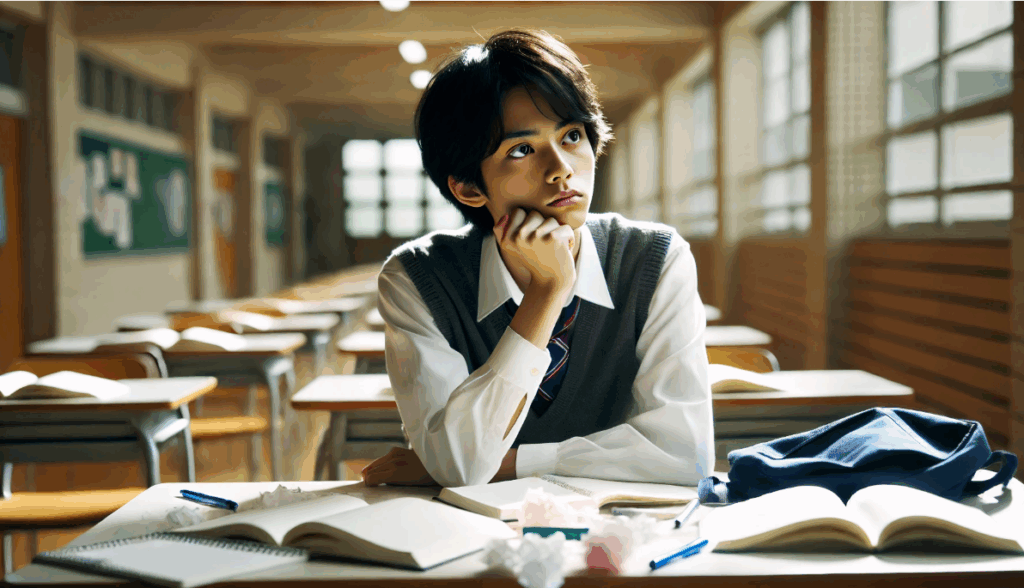
- まずは周りの意見を聞くのがおすすめ
- 中学生が意識すべき公約のポイント
- 高校生ならではの視点を取り入れる
- 実現可能性を重視した公約例の案
- 人を惹きつける面白い公約の考え方
まずは周りの意見を聞くのがおすすめ
生徒会の公約がどうしても思いつかない時、一人で机に向かってうんうん唸るのは、実はあまり効果的ではありません。最もパワフルで、かつ確実な第一歩は、あなたの周りにいる「全校生徒」という最高のアイデアソースに、真摯に耳を傾けることです。
なぜなら、生徒会はあなた一人のためのものではなく、全校生徒の代表として活動する組織だからです。あなた一人の視点では決して気づけなかった、多くの生徒が日々感じている小さな不便や、密かな願いが必ず存在します。
クラスの友人、部活動の仲間、廊下ですれ違う先輩や後輩、そして日々生徒を見守っている先生方。彼らとの何気ない会話の中にこそ、公約の原石が隠されています。
「移動教室の時の荷物が重くて大変なんだよね」「昼休みにもっと静かに読書できる場所があったらいいのに」「あの部活の活躍、もっとみんなに知ってほしい」――こうした具体的な「生の声」こそが、多くの生徒から「そうそう、それが言いたかった!」と強い共感を得られる公約の素晴らしいヒントになるのです。
効果的な意見収集の具体的な方法
- 直接ヒアリング:休み時間や放課後、友人グループに「もし生徒会長になったら何してほしい?」とストレートに聞くのではなく、「学校生活で『これ、ちょっと不便だな』とか『もっとこうなったら楽しいのに』って思うこと、何かある?」といったオープンな質問で、本音を引き出しましょう。
- 簡易アンケートの実施:クラスや部活動単位で、簡単なアンケートを実施するのは非常に有効な手段です。Googleフォームなどの無料ツールを使えば、匿名での回答も可能になり、より率直な意見が集めやすくなります。設問は「はい/いいえ」で答えられる選択式の質問と、自由に記述できる欄を組み合わせるのがおすすめです。
- 目安箱の徹底分析:もし学校に目安箱が設置されているなら、それは貴重なデータの宝庫です。生徒会担当の先生に許可を得て、過去にどのような意見が投書されていたかを確認させてもらいましょう。繰り返し投書されている意見があれば、それは多くの生徒が望んでいる改善点である可能性が高いです。
心理的安全性のある場づくりを
意見を求める際は、相手が安心して話せる雰囲気を作ることが大切です。相手の意見を否定せず、「なるほど、そういう考え方もあるんだね!」と肯定的に受け止める姿勢を見せることで、より多くの本音を引き出すことができます。これを「心理的安全性」と呼び、活発な議論には不可欠な要素です。
このようにして集められた無数の「みんなの声」を丁寧に整理し、共通する課題を見つけ出すプロセスこそが、独りよがりではない、真に価値のある公約を生み出すのです。
一人で悩まず、まずは積極的に周りを巻き込み、みんなの学校を良くするためのパートナーになってもらうことが、公約作りの成功への最短ルートと言えるでしょう。
中学生が意識すべき公約のポイント
中学生が生徒会役員に立候補する場合、公約の方向性を定める上で最も重要なキーワードは「身近で、分かりやすく、すぐに実感できる改善」です。高校生と比較して、学校という空間が生活の大部分を占める中学生にとって、自分たちの日常に直接関わる、具体的で目に見える変化をもたらすテーマが、心からの共感と支持を得やすいためです。
例えば、「グローバルな人材を育成する」といった抽象的で壮大なテーマを掲げるよりも、「雨の日に濡れた傘を置くための傘立てを増設する」や「クラス対抗のeスポーツ大会を開催する」といった公約の方が、生徒一人ひとりにとって「自分事」として捉えやすく、結果的に多くの票に繋がりやすいのです。
文部科学省が示す学習指導要領においても、中学校の特別活動では「集団や社会の一員としての見方・考え方」を養うことが目標とされており、身近な課題解決に取り組むことは、その趣旨にも合致しています。(出典:文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編」)
中学生の心を掴む公約テーマ
- 学校環境の快適化:トイレの美化キャンペーン(ポスター作成や清掃強化週間の設置)、ロッカーの整理整頓コンテスト、昇降口の混雑緩和を目的とした時差登校の提案など、日々の小さな「不快」を解消する提案。
- 学校生活の活性化:学年の垣根を越えた交流を目的とした合同レクリエーション、昼休みの中庭を使ったミニコンサートや特技発表会など、学校に来るのがもっと楽しくなる企画。
- コミュニケーションの円滑化:目安箱に寄せられた意見と、それに対する生徒会の回答や進捗状況を掲示板で定期的に報告するなど、風通しの良い「開かれた生徒会」をアピールする取り組み。
背伸びしすぎた公約がもたらすリスク
中学生の公約で最も注意したいのは、善意からであっても、あまりに規模の大きい、または多額の予算が必要となる提案を安易に掲げてしまうことです。
「体育館に最新の冷房を設置します」という公約は一見魅力的ですが、実現には数百万円単位の予算と、教育委員会の承認、長期的な工事計画など、生徒会の権限をはるかに超える多くのハードルが存在します。
このような実現不可能な公約を掲げて当選してしまうと、任期中に「公約違反だ」と批判され、生徒からの信頼を失い、その後の生徒会活動全体が停滞してしまう危険性があります。アイデアが浮かんだら、必ず一度、生徒会担当の先生に「これは現実的に可能でしょうか?」と相談する謙虚な姿勢が不可欠です。
中学生のうちは、「自分たちの手で、自分たちの学校を、少しでも良くしたい」という純粋でひたむきな情熱と、地に足の着いた具体的な提案が、同級生だけでなく、先生方や保護者の心をも動かす最大の武器となります。
高校生ならではの視点を取り入れる
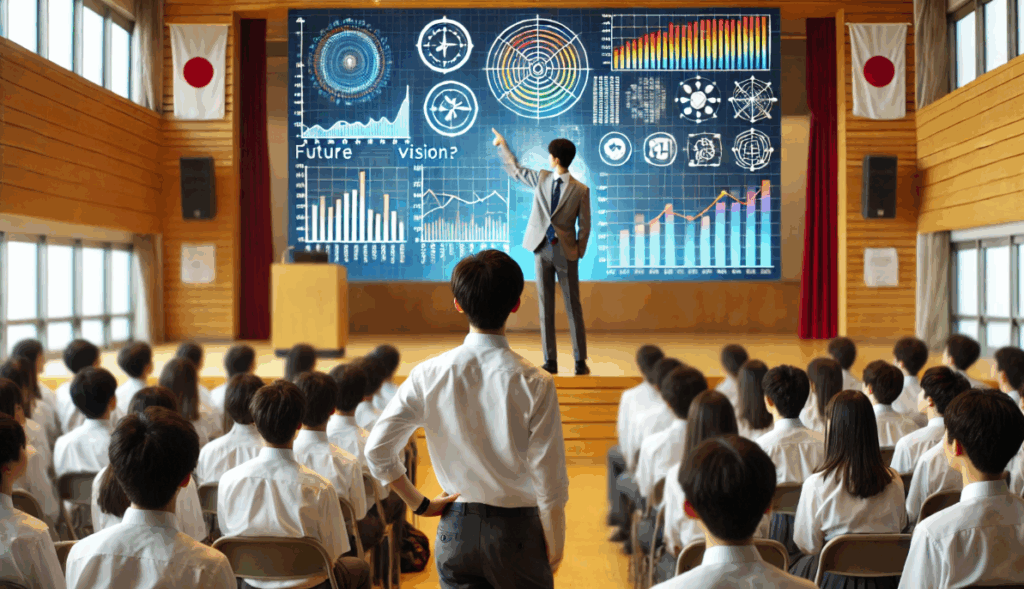
高校生が生徒会に立候補する際には、中学生の時よりも一歩踏み込んだ、より広い視野と社会との接続を意識した公約が求められます。
高校生活は、自律性が格段に高まり、目前に迫る大学進学や就職といった進路選択、さらには社会の一員としての自分の役割を真剣に考え始める重要な時期です。
そのため、単に学校内での楽しみを増やすだけでなく、生徒一人ひとりの将来に繋がり、社会貢献へと繋がるような活動が、多くの共感を呼びます。
デジタルツールを駆使した学校運営の効率化提案や、地域社会が抱える課題解決への貢献といった視点は、知識と行動力を兼ね備えた高校生ならではの強みを発揮できる分野です。
これらの取り組みは、学校生活全体を豊かにするだけでなく、参加した生徒自身のポートフォリオを充実させ、貴重な学びと経験に繋がるという付加価値も生み出します。
高校生におすすめの、一歩先を行く公約テーマ
- キャリア・進路支援の強化:地元の企業で活躍する若手社会人や、様々な分野の大学に通うOB・OGを招いたパネルディスカッション形式の講演会を企画する。生徒が主体となって運営することで、企画力や交渉力も養われます。
- 学校DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進:生徒会からのお知らせや行事予定をGoogleカレンダーなどの共有ツールでリアルタイムに配信する。また、紙ベースのアンケートをGoogleフォームに置き換えることで、集計作業を効率化し、ペーパーレス化を推進する。
- SDGsと連携した社会貢献活動:地域の清掃活動や子ども食堂でのボランティア活動への参加。また、文化祭でフェアトレード商品の販売ブースを設けたり、フードドライブ(家庭で余っている食品を集めて寄付する活動)を実施したりするなど、具体的なアクションを提案する。これらの活動は、外務省も推進する持続可能な開発目標(SDGs)への貢献に直結します。
知っておきたい!生徒会活動と大学入試の深い関係
近年、大学入試では、学力試験の点数だけでは測れない「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」が重視される傾向が強まっています。生徒会で公約を掲げ、その実現のために仲間と議論し、先生方と交渉し、時には困難を乗り越えたという経験は、まさにこの能力を証明する最高の具体例となります。
特に総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜においては、このような経験が自己PRの強力な武器となり、他の受験生との大きな差別化に繋がることがあります。
日々の学校生活の充実に加え、「未来の自分」や「より良い社会」というスケールの大きな軸を少し加えること。それが、同級生から「この人なら何かを変えてくれそうだ」と期待を寄せられる、高校生らしい深みと説得力を持った公約を作成するための重要な鍵となるでしょう。
実現可能性を重視した公約例の案
どんなに聞こえが良く、魅力的な公約を掲げたとしても、それが実現できなければ有権者からの信頼を裏切ることになり、絵に描いた餅に終わってしまいます。
公約を考える上で最も重要視すべきなのは、「やりたいこと(理想)」と「できること(現実)」のギャップを正確に把握し、そのバランスを見極めること、すなわち実現可能性の追求です。
公約が実現可能かどうかは、学校の校則、年間の予算、先生方の協力体制、さらにはPTAや地域社会の意向など、様々な外的要因によって左右されます。
立候補を決意したら、自分のアイデアを情熱的に語る前に、まずは生徒会担当の先生に冷静な視点で相談し、「この公約を実現するためには、どのようなハードルがありそうでしょうか?」とアドバイスを求めるステップを踏むことが不可欠です。
ここでは、公約の案を「実現のしやすさ」という客観的な観点から分類し、そのポイントを解説します。
公約の実現可能性チェックリスト
アイデアが浮かんだら、以下の5つの質問に答えてみましょう。すべてに明確な答えが出せるなら、その公約の実現可能性は高いと言えます。
- 【予算】この公約を実現するために、お金はかかりますか?かかる場合、どこからその予算を確保しますか?
- 【許可】校長先生や教育委員会など、誰かの許可が必要ですか?
- 【協力者】生徒会役員だけで実行できますか?他の委員会や先生方、外部の人の協力が必要ですか?
- 【ルール】現在の校則や学校の慣例と矛盾しませんか?
- 【時間】自分の任期中(通常1年間)に達成できる現実的なスケジュールですか?
| 実現度 | 公約例の案 | ポイントと解説 |
|---|---|---|
| 高 ★★★
(すぐに着手可能) |
目安箱の意見を定期的に掲示板で公開する | 予算がほぼ不要で、生徒会役員の熱意と努力次第ですぐに実行可能です。学校運営の透明性を高め、「生徒の声が届いている」という実感を生み出す効果があります。 |
| 高 ★★★
(すぐに着手可能) |
昼休みを使ったリクエスト制のラジオ放送 | 放送委員会との連携が鍵となりますが、既存の設備を活用できるため実現は容易です。全校生徒が参加できる企画であり、学校の一体感を醸成します。 |
| 中 ★★☆
(交渉・調整が必要) |
定期テスト前に放課後自習室の開放日を増やす | 最大のハードルは、監督を担当してくださる先生の確保です。「試験2週間前の期間のみ」「週2回」など、範囲を限定して提案することで、先生方の負担を軽減し、許可を得やすくなります。 |
| 中 ★★☆
(交渉・調整が必要) |
食堂の人気メニューアンケートを実施し、結果を業者に提案する | 食堂のメニューは運営会社の裁量が大きいため、直接的な変更は難しいかもしれません。しかし、生徒の具体的な希望をアンケート結果という客観的なデータで示すことで、業者側も前向きに検討してくれる可能性が高まります。 |
| 低 ★☆☆
(実現は困難) |
制服の自由選択制(スラックス等)を導入する | 服装規定は学校の伝統や教育方針の根幹に関わる部分であり、保護者や同窓会の意見も大きく影響します。生徒会の権限だけで変更するのは極めて難しく、問題提起として長期的な課題として提案するに留めるのが現実的です。 |
| 低 ★☆☆
(実現は困難) |
体育館への空調(冷房)設備の設置 | 数百万~数千万円規模の莫大な予算と、安全性に関わる大規模な工事が必要です。これは市の教育委員会の管轄であり、実現には数年単位の長期計画が求められるため、一個人の任期中に達成することは不可能です。 |
選挙戦略としては、まず実現度が高い公約を複数掲げて有権者に安心感を与え、その上で、実現度中の挑戦的な公約を「皆さんの協力があれば実現したい」という形で訴える、という構成がおすすめです。
地に足のついた堅実な提案こそが、言葉だけの理想論者ではない、実行力のあるリーダーとしてのあなたの信頼を築き上げます。
人を惹きつける面白い公約の考え方
生徒会選挙において、多くの票を集め、有権者の記憶に強く残るためには、真面目で堅実な公約だけでなく、少し「面白い」「なんだか楽しそう」と感じさせる遊び心のある要素を取り入れることが極めて効果的です。
ただし、この「面白さ」のさじ加減は非常にデリケートです。単なるウケ狙いや、現実離れした奇抜さだけを追求してしまうと、「不真面目な人」「実行する気がないのでは」と見なされ、逆効果になるリスクもはらんでいます。
ここで最も大切なのは、「面白さ(エンターテイメント性)」と「真面目さ(教育的意義)」の絶妙なバランス感覚です。一見するとユーモアのある楽しい企画に見えながら、その根底には「学校生活をより良くしたい」「みんなの課題を解決したい」という真剣な目的がしっかりと存在している。この二面性を有権者に示すことが、当選を引き寄せる鍵となります。
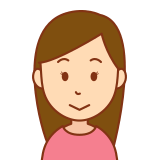
「面白い公約」って言われても、ただ笑いを取るだけじゃダメなんですよね…。真面目な目的と面白さを両立させるには、具体的にどう考えればいいんだろう?
この本質的な悩みに対する最も有効なアプローチは、「多くの人が大切だと分かっている“真面目なテーマ”を、誰もが参加したくなる“面白いイベント”に翻訳・転換する」という発想を持つことです。具体的には、以下のような思考プロセスをたどります。
- 【真面目な目的】:校内の挨拶をさらに活発にし、明るく活気のある学校の雰囲気を作りたい。
- →【面白いイベントへの転換(公約)】:月間「グッドモーニング・チャンピオンシップ」を開催!各クラスの代表が校門に立ち、挨拶の元気さや爽やかさを競います。優勝クラスには、食堂の人気デザート引換券を贈呈!
- 【真面目な目的】:生徒と先生方の間の心理的な壁を取り払い、より円滑なコミュニケーションを促進したい。
- →【面白いイベントへの転換(公約)】:昼休み放送の新コーナー「クイズ!先生の意外な㊙︎特技」を実施!「実は剣道三段の数学の先生は誰?」といったクイズを出題し、先生方の新たな一面を発見するきっかけを作ります。
- 【真面目な目的】:日々の清掃活動へのモチベーションを高め、自分たちの学習環境を大切にする心を育みたい。
- →【面白いイベントへの転換(公約)】:学期末に「教室ピカピカ選手権」を開催!美しさ、整理整頓、独創性の3項目で審査し、最も輝いていたクラスを「環境大臣」として表彰します。
「面白い」と「不快」は紙一重
面白い公約を考える際に絶対に忘れてはならないのが、多様性への配慮です。特定の生徒や先生をからかったり、誰かが不快な思いをしたりするような企画は、絶対に避けなければなりません。
例えば、「先生のモノマネ大会」は盛り上がる可能性がありますが、一歩間違えれば侮辱と受け取られかねません。全ての生徒が安心して楽しめる、ポジティブな企画を心がけましょう。
このように、誰もがその重要性を理解しているけれど、少し退屈に感じてしまいがちな普遍的なテーマを、ゲーム性や競争、エンターテイメントといった要素でコーティングすることで、多くの生徒が「それなら参加してみたい!」とワクワクするような、魅力的で独創的な公約が生まれるのです。
さらに、より多くの具体例を知りたい場合は、生徒会の公約で斬新で差がつく面白いアイデアも参考にしてみてください。
生徒会の公約が思いつかない状況を打破する具体例

- 実現可能な公約アイデア一覧
- インパクトを与える斬新な見せ方
- 聞き手の心に響く公約の書き方
- まとめ:生徒会の公約が思いつかないなら仲間と見つけよう
実現可能な公約アイデア一覧
ここでは、これまでに解説してきた「周りの意見の聞き方」「中高生それぞれの視点」「実現可能性」「面白さの加え方」といったポイントを総合的に踏まえ、具体的ですぐに使える公約のアイデアをジャンル別に一覧でご紹介します。
あなたの学校の独自の文化や、仲間から集めた意見と照らし合わせながら、「これならうちの学校でもできそう!」「これを少しアレンジすればもっと良くなるかも」といった視点で、最適な公約を見つけるための参考にしてください。
実現度の目安は「◎:生徒会の努力次第で任期内に実現可能」「◯:先生方や外部との交渉・調整が必須」「△:実現のハードルが非常に高く、問題提起に留まる可能性」の3段階で示しています。
| 分類 | 公約アイデア | 実現度 | ポイント・具体策 |
|---|---|---|---|
| 面白い系
(エンタメ・交流) |
昼休みラジオ「校内放送ジャックDAY」の定例化 | ◎ | 放送委員会との連携が前提。生徒からのお悩み相談コーナーや、部活動の告知タイムなどを設けるとマンネリ化を防げる。 |
| 先生の若い頃の写真当てクイズ「あの頃、君は若かった」 | ◯ | 先生方の協力と事前の許可が必須。個人情報とプライバシーに最大限配慮し、あくまで任意参加で募る。文化祭のステージ企画としても盛り上がる。 | |
| 季節ごとの黒板アートコンテスト | ◎ | 放課後の教室を開放。チョーク代程度のわずかな予算で実施可能。優秀作品は写真に撮り、学校のウェブサイトや広報誌で紹介する。 | |
| クラス対抗eスポーツ大会(パズルゲーム等) | ◯ | 校内のICT機器を活用。特定のゲームスキルがなくても楽しめる、全年齢向けのタイトルを選ぶのが成功の鍵。 | |
| まじめ系
(環境改善・学習支援) |
目安箱意見への「見える化」回答システムの構築 | ◎ | 最も基本的かつ重要な生徒会活動。寄せられた意見と、それに対する生徒会の回答・対応状況を一覧にして、毎月掲示板に貼り出す。 |
| 定期テスト前の図書室・空き教室の開放時間延長 | ◯ | 監督教員の確保が最大の課題。「試験2週間前の平日1時間のみ」など、具体的かつ現実的な範囲で先生方に協力を要請することが重要。 | |
| トイレの快適性向上プロジェクト | ◎ | すぐに実行できるのは、清掃用具の充実や、芳香剤・ハンドソープの設置など。アンケートで要望を集め、優先順位をつけて学校側に改善を提案する。 | |
| 忘れ物ゼロウィークの実施とクラス表彰 | ◎ | チェックシートを活用し、忘れ物が少なかったクラスを表彰する。生徒の自己管理能力を高める教育的効果も期待できる。 | |
| 未来系
(デジタル・キャリア) |
匿名で投稿できるオンライン目安箱の設置 | ◎ | Googleフォームなどを活用すれば無料で即時開設可能。紙の目安箱と併用することで、より多くの潜在的な意見をすくい上げることができる。 |
| 部活動・学校行事のGoogle共有カレンダー運用 | ◎ | 各部活動の顧問の先生と連携。試合日程や行事予定を全校生徒・教員が一覧でき、応援に行きやすくなったり、予定の重複を防いだりできる。 | |
| 様々な分野で活躍する卒業生(OB/OG)講演会の企画 | ◯ | 進路指導部の先生や同窓会と連携して講師を探す。生徒にとって身近なロールモデルの話は、将来を考える大きな刺激となる。 | |
| 小規模な電子掲示板(デジタルサイネージ)導入の提案 | △ | 昇降口や食堂にモニターを1台設置するだけでも、情報の伝達効率は飛躍的に向上する。予算確保が最大の壁だが、ペーパーレス化による長期的なコスト削減効果を訴え、粘り強く提案する価値はある。 | |
| 地域・SDGs系
(社会貢献) |
ペットボトルキャップ・古着・書き損じハガキの回収BOX設置 | ◎ | 回収後の寄付先団体(NPO法人など)を事前にリサーチし、連携体制を整えておくことが必須。誰でも気軽に参加できる社会貢献活動。 |
| 地域清掃ボランティア「クリーンアップ隊」の結成 | ◯ | 安全管理のため、必ず複数の先生の引率のもとで実施する。地域の自治会などと連携することで、より広範な活動が可能になる。 | |
| フードドライブの実施と子ども食堂への寄付 | ◯ | 家庭で消費しきれない未開封の食品を集める活動。受け入れ先の団体と事前に連携し、受け入れ可能な食品の種類や賞味期限のルールを全校生徒に周知徹底することが重要。 |
これらのアイデアはあくまで出発点です。
最も重要なのは、これらの例をヒントに、「自分たちの学校が本当に必要としているものは何か?」「どうすればもっと自分たちらしい、ユニークな企画になるか?」という視点で、仲間と共に知恵を絞り、アイデアを育てていくプロセスそのものです。
インパクトを与える斬新な見せ方

どれほど素晴らしい内容の公約を練り上げたとしても、その魅力が有権者に伝わらなければ、票には結びつきません。選挙戦において、公約の内容そのものと同じくらい重要なのが、「どう見せるか」「どう伝えるか」というプレゼンテーションの戦略です。
短い演説の時間で、多くの生徒の記憶に鮮烈な印象を残すためには、内容だけでなく、伝え方にも他の候補者にはない斬新な工夫が求められます。
その中でも特に有効かつ即効性のあるテクニックが、一つひとつの公約に、覚えやすく活動内容が一目でわかるキャッチーな名前(スローガン)をつけることです。秀逸なネーミングは、無味乾燥な政策を、ワクワクするプロジェクトへと昇華させ、演説の効果を何倍にも高める力を持っています。
公約を魅力的に見せるキャッチーな名前の付け方
- 普通の公約:「目安箱を設置して、皆さんの意見を聞きます」
- →斬新な見せ方:「みんなの声ポスト計画 ~あなたの『あったらいいな』を形に~」と名付け、双方向のコミュニケーションと実現への意欲をアピール。
- 普通の公約:「学校をきれいに保つための活動をします」
- →斬新な見せ方:「〇〇高校クリーンアップ大作戦 ~日本一きれいな学校を目指そう!~」とし、全校生徒を巻き込んだ壮大なイベント感を演出し、参加意欲を掻き立てる。
- 普通の公約:「学校行事をもっと盛り上げたいです」
- →斬新な見せ方:「青春アップデートプロジェクト ~退屈な日常に『革命』を~」と銘打ち、単なる改善ではなく、学校生活全体を根本からより良く変えていくという大きなビジョンとリーダーシップを示す。
演説の方法自体を工夫するのも非常に有効です。ただひたすら原稿を読み上げるのではなく、重要なキーワードを大きく書いたフリップや、簡単なグラフを示したスライドを用意して視覚的に訴えるだけでも、聞き手の理解度は格段に上がります。
また、演説の冒頭で「この学校のトイレに満足している人は手を挙げてください!」といったように、全校生徒に問いかけるような参加型のアイスブレイクを取り入れるのも、一気に聞き手の心を引きつけるテクニックです。
あなたの練り上げた公約という素晴らしい「商品」を、どうすれば最も魅力的にパッケージングし、お客様(有権者)に届けられるか。選挙戦においては、マーケティングや広告代理店のような視点を少しだけ取り入れることが、ライバルに差をつけ、勝利を掴むための重要な鍵となるのです。
聞き手の心に響く公約の書き方
いよいよ選挙戦のクライマックスである演説。その原稿を作成する際、聞き手の心を動かし、「この人に自分たちの学校の未来を託したい」と強く思わせるためには、話の構成、つまり文章の「型」が非常に重要になります。
世界中の優れたプレゼンターが活用する、最も説得力のある文章の型、それが「PREP法(プレップ法)」です。この型を意識するだけで、あなたの公約は驚くほど分かりやすく、論理的で、そして何より心に響くメッセージへと変わります。
PREP法とは、以下の4つの要素の頭文字を取ったもので、この順番で話を構成する手法です。
説得力を最大化するPREP法の構成
- P (Point):結論 … 「私がやりたいことはこれです!」と、最も伝えたい公約(結論)を、まず最初に、簡潔かつ力強く述べます。
- R (Reason):理由 … 「なぜなら、現状にはこのような課題があるからです」と、その公約が必要である理由や背景を、客観的な事実を交えて説明します。
- E (Example):具体例 … 「例えば、こんな出来事がありました」「実際にこんな声が寄せられています」と、理由を裏付ける具体的なエピソードやデータを紹介し、話にリアリティと説得力をもたらします。
- P (Point):結論 … 「だからこそ、私にはこれが必要です!」と、最後にもう一度、言葉や表現を変えながら公約(結論)を述べ、聞き手の記憶に強く刻み込みます。
PREP法を用いた演説原稿の具体的な例文
【P:Point / 結論】
皆さん、こんにちは。この度、生徒会長に立候補しました〇年〇組の〇〇です。私が生徒会長になったら、まず最初に、スマートフォンから誰でも匿名で意見を送れる「目安箱のデジタル化」、名付けて『サイレント・ボイス・プロジェクト』を実現します!
【R:Reason / 理由】
なぜなら、現在の昇降口にある紙の目安箱は、「友達の目があって意見を出しにくい」「何を書いていいか分からない」といった理由で、十分に活用されていないと私は感じているからです。全校生徒の貴重な意見、声なき声が、学校に届かないまま埋もれてしまっている。これは、私たちの学校にとって大きな損失です。
【E:Example / 具体例】
先日、私はクラスメイト30人に簡単なアンケートを行いました。その結果、「学校生活で改善してほしい点がある」と答えた生徒は、実に8割以上にのぼりました。しかし、その中で「実際に目安箱に投書したことがある」と答えた生徒は、たったの2人でした。このギャップこそが、私たちが解決すべき喫緊の課題ではないでしょうか。
【P:Point / 結論】
だからこそ、休み時間でも、通学中でも、自宅にいる時でも、思いついた瞬間に、誰にも知られずにあなたの本音を届けられる『サイレント・ボイス・プロジェクト』が、今、この学校には必要なのです。皆さんの小さな声一つひとつを、私が責任を持って拾い上げ、より良い学校を創るための力に変えることをお約束します。どうか、私にその仕事をさせてください!
このように、「なぜそれが必要なのか」という課題認識(Reason)と、「こうすれば解決できる」という具体的な解決策(Example)をセットで、物語のように語ることで、あなたの公約は単なる願望の羅列ではなく、聞き手が「確かにそうだ」「それなら応援したい」と心から納得し、共感できる力強いメッセージへと昇華されるのです。
演説全体の構成や本番での話し方をさらに深く知りたい人は、生徒会選挙の演説必勝法!票を集める圧倒的戦略と成功ポイントもあわせてチェックしておくと安心です。
まとめ:生徒会の公約が思いつかないなら仲間と見つけよう
この記事では、生徒会の公約が思いつかないという、立候補者なら誰もが直面する大きな壁を乗り越えるための、様々な視点や具体的な思考法、実践的なテクニックを紹介してきました。最後に、あなたの挑戦を成功に導くための最も重要なエッセンスを、改めてまとめます。
- 公約作りは孤独な作業ではない、チームで挑むプロジェクトだと心得る
- 最初の一歩は、ペンを持つことではなく、友人や先生に「ねえ、どう思う?」と話しかけること
- アンケートやヒアリングを通じて、生徒の潜在的なニーズという名の「宝」を探る
- 中学生は、日常の「ちょっとした不便」を解消する身近な公約が共感を呼びやすい
- 高校生は、進路や社会貢献といった、一歩先の未来を見据えた広い視野を取り入れる
- どんなに良いアイデアでも、実現可能性というフィルターを通して、必ず事前に確認する
- 予算、校則、先生方の協力体制といった現実的な制約を把握しておくことがリーダーの務め
- 「面白い」アイデアは、それ自体が目的ではなく、真面目な目的を達成するための「手段」であると考える
- 提供したアイデア一覧をそのまま使うのではなく、自分の学校の特色に合わせてアレンジを加える
- 公約には、人の記憶に残りやすいキャッチーなスローガン(プロジェクト名)を必ずつける
- 斬新な見せ方やプレゼンテーションで、他の候補者との差別化を図る
- 演説原稿は、聞き手の心を動かす最強の文章構成「PREP法」を意識して組み立てる
- 「なぜその公約が必要なのか」という背景にあるストーリーを、自分の言葉で情熱的に語る
- 公約が実現した後の、明るく楽しい学校生活という未来像を、有権者と共有する
- そして何より、最高の公約は、信頼できる仲間と協力すれば必ず見つかる
生徒会の公約が思いつかないという悩みは、決してあなた一人だけが抱えるものではありません。それは、学校をより良くしたいと真剣に考える、責任感の強い立候補者の誰もが一度は通る道です。
しかし、あなたの周りには、たくさんのヒントと、あなたを助けたいと願う仲間が必ずいます。
この記事で紹介した様々な方法を羅針盤として、ぜひ仲間と共に航海に出てください。あなただけの、そして学校のみんなのための素晴らしい宝物(公約)を見つけ出す、その挑戦を心から応援しています。


