生徒会副会長に立候補したものの、肝心の公約が思いつかないと悩んでいませんか。中学生でも実現可能なアイデアを探しているけれど、他の候補者と差がつくインパクトのある面白い公約も考えたいところです。
また、おすすめの具体例の一覧や、すぐに使える演説の例文があれば心強いですよね。
この記事では、そんなあなたのために、信頼される生徒会副会長の公約の例を徹底的に解説します。選挙で勝ち、信頼される副会長になるためのノウハウがここに詰まっています。
- 副会長の役割に合った公約の立て方がわかる
- 中学生でも実現可能な公約の具体例が見つかる
- 他の候補者と差がつく公約の考え方が学べる
- 演説で使える公約の伝え方のコツが理解できる
信頼される生徒会副会長の公約例と基本

- 公約が思いつかない時の考え方
- 副会長におすすめの公約の方向性
- なぜ実現可能な公約が大切なのか
- 中学生が掲げるべき公約のポイント
- 学校生活が良くなる公約の具体例
- 参考になる公約アイデア一覧
公約が思いつかない時の考え方
生徒会副会長の公約が思いつかない時、多くの人が壮大なアイデアを探そうとして行き詰まってしまいます。しかし、本当に価値のある公約の種は、「身近な学校生活の中に潜む課題を見つける」ことから生まれます。
派手なスローガンよりも、全校生徒が日常的に感じている「小さな不便」や「ささやかな願い」に光を当てることこそ、多くの共感を呼ぶ鍵となります。
例えば、教室の机がガタつく、特定のトイレだけいつも混んでいる、昼休みにボールを使える場所が少ない、といった具体的な問題点はありませんか。
自分一人の視点では気づかないことも多いため、クラスメイトや部活動の仲間に「学校生活で『これ、何とかならないかな』と思うことってある?」と積極的に話を聞いてみることが、非常に有効な手段です。実際に簡単なアンケートを実施すれば、これまで見過ごされてきた貴重な意見が集まることも少なくありません。
課題発見のための具体的な3つのステップ
- 自分の「学校生活ログ」を見直す:朝の登校から下校まで、一日の行動を思い出してみましょう。自分が毎日「当たり前」として受け入れている不便な点(例:靴箱が狭い、廊下が暗い)をメモに書き出してみます。
- 多様な立場の友人にヒアリングする:運動部の友人、文化部の友人、帰宅部の友人、それぞれに話を聞くと、立場によって異なる悩みや要望が見えてきます。多角的な情報収集が重要です。
- 「なぜそうなっているのか」を考える:例えば「渡り廊下が雨の日に滑りやすい」という課題を見つけたら、「なぜ滑りやすいのか?」「改善するにはどうすれば良いか?」と一歩踏み込んで考察することで、より具体的な公約に繋がります。
このように、まずは小さな課題から着想を得て、それを解決するための具体的なアクションを考えること。これが、多くの生徒から「自分たちのことを考えてくれている」と支持される公約を作成するための、確実な第一歩となります。
副会長におすすめの公約の方向性
生徒会副会長の公約を練る上で、最も意識すべきなのは会長を支え、組織を円滑に動かす「サポーター」としての役割です。
会長が学校全体のビジョンを示す「船長」だとすれば、副会長は航海図を読み解き、乗組員と連携して船を動かす「航海士」のような存在です。そのため、自分が先頭に立つというよりは、会長のビジョンを具体的な行動計画に落とし込み、他の役員と協力しながら実務を遂行する調整役としての働きが求められます。
この役割を理解すれば、公約の方向性も自ずと見えてきます。「私がこの学校を根本から変革します!」といった強い自己主張よりも、「会長と協力し、生徒会チーム一丸となって、皆さんの学校生活をより充実させるためのサポートを徹底します」という姿勢が、副会長にはふさわしいと言えるでしょう。
副会長の公約 3つの視点
- 会長の公約を補強・具体化する公約:例えば、会長が「生徒の意見を尊重する学校」というビジョンを掲げたなら、副会長は「そのために、私は目安箱をデジタル化し、回答率100%を目指します」と具体的な手段を公約にする。
- 生徒と生徒会の橋渡し役となる公約:「月に一度、各クラスの代表者と生徒会役員が意見交換を行う『円卓会議』を設けます」など、双方向のコミュニケーションを活性化させる仕組みを提案する。
- 学校行事を円滑に進めるためのサポート公約:文化祭や体育祭の準備において、「各クラス・団体の準備状況を共有するプラットフォームを導入し、備品の貸し出しなどを効率化します」といった、実務的な改善策を掲げる。
会長候補の公約を事前にしっかりと研究し、「〇〇会長候補が掲げる△△という目標を、私は□□という形で具体的にサポートします!」と演説で述べることができれば、非常に説得力が増し、思慮深い候補者であるという印象を与えられますよ。
冷静な判断力と着実な実行力で組織全体を支えるという姿勢こそ、副会長として最も重要な資質であり、信頼を得るための鍵となります。
なぜ実現可能な公約が大切なのか

生徒会選挙において、公約に「実現可能性」を盛り込むことは、当選後の信頼関係を築くための絶対条件です。選挙戦が白熱すると、有権者の気を引くために、どうしても聞こえが良く、スケールの大きな公約を掲げたくなります。
しかし、その公約が本当に生徒会の権限や予算の範囲内で実行可能か、冷静に分析することが不可欠です。それを怠ると、当選がゴールとなり、その後の活動で苦しむことになります。
仮に実現不可能な公約を掲げて当選してしまった場合、どうなるでしょうか。任期中に公約を実現できず、結果として有権者である生徒たちから「口だけだった」「公約違反だ」という厳しい評価を受けることになります。
一度失った信頼を回復するのは極めて困難であり、その後の生徒会活動すべてが「どうせ何も変わらない」という無関心の中で行われることになりかねません。
実現性の低い公約がもたらす深刻なデメリット
例えば「制服を廃止します」「長期休暇を増やします」といった公約は、学校の教育方針や年間計画に関わるため、生徒会の一存で決定できるものではありません。こうした公約は、以下のような深刻なリスクを内包しています。
- 生徒からの信頼失墜:約束を守れないリーダーというレッテルを貼られてしまいます。
- 先生方との関係悪化:学校運営の根幹を理解していないと見なされ、協力が得られにくくなります。
- 生徒会活動の停滞:実現不可能な目標に固執することで、他の実現可能な活動まで滞ってしまいます。
大切なのは、自分たちの責任範囲で着実に達成できる目標を見極めることです。例えば、「トイレの各個室に荷物を掛けられるフックを設置するよう学校に要請します」「定期テスト前に、希望者が利用できる自習教室を3つ確保します」といった、具体的で達成可能な公約は、地味に聞こえるかもしれません。しかし、これこそが真に生徒のためになり、あなたの評価を「信頼できる実務家」として高めることに繋がるのです。
中学生が掲げるべき公約のポイント
中学生が生徒会副会長の公約を立案する際には、「身近な学校生活の課題解決」と「先生との緊密な連携」という二つの柱を意識することが、成功への近道です。
高校の生徒会と比較して、中学校の生徒会活動は、より先生方の指導やサポートを受けながら進めるのが一般的です。そのため、生徒の自治だけで完結する大規模な改革案よりも、学校側と協力して着実に実行できる、地に足のついたテーマが適しています。
特に、学校生活の基盤となる部分の改善は、全校生徒にメリットがあり、先生方からの理解も得やすいため、公約として非常に有効です。
学校生活の基礎を充実させる公約
- 挨拶運動の活性化と質の向上:ただ門に立つだけでなく、「週替わりで各委員会が担当し、オリジナルのポスターを掲示する」「挨拶の声が大きかったクラスを表彰する」など、参加したくなるような楽しい工夫を提案します。文部科学省の調査でも、挨拶などの基本的な生活習慣の重要性が指摘されています。(参照:文部科学省「生徒指導提要」)
- 校内の美化活動と環境整備:学期に一度、全校生徒で地域のゴミ拾いを行うボランティア活動を企画する。また、「各クラスの清掃用具(ほうき、ちりとり等)の状況を調査し、破損しているものは計画的に補充するよう学校に要請する」といった提案も具体的で良いでしょう。
- 忘れ物対策の強化とリサイクル精神の涵養:各学年の廊下に「忘れ物BOX」を設置し、一定期間持ち主が現れなかった文房具などは、必要とする生徒が使える「リサイクルステーション」として活用する仕組みを提案します。
全く新しいことをゼロから始めるだけでなく、現在行われている活動を「もっと良くするにはどうすればいいか?」という改善・改良の視点を持つことも非常に大切です。例えば、既存の委員会活動に新しい役割を追加する提案などは、実現可能性が高く、評価されやすい公約になります。
これらの公約は、具体的なアクションを起こしやすく、活動の成果が目に見えやすいという大きなメリットがあります。まずは、自分たちの学校をより安全で快適な学びの場にするための、着実な一歩となる提案から考えてみましょう。
学校生活が良くなる公約の具体例

ここでは、多くの学校で応用可能であり、生徒の満足度向上に直結する公約の具体例を掘り下げて紹介します。これらの例をテンプレートとして活用し、自分の学校の特色や課題に合わせてカスタマイズしてみてください。
| 公約の例 | 目的・メリット | 実現に向けた具体的なアクションプラン |
|---|---|---|
| 意見箱のデジタル化と回答の徹底 | 紙媒体では意見を出しにくい生徒も、スマートフォンやタブレットからなら匿名で気軽に投稿できる。これにより、潜在的なニーズを吸い上げ、生徒会活動への参加意識を高める。 | 1. 学校で導入されている連絡ツール(Google Forms, Classiなど)のアンケート機能の活用を、生徒指導の先生と情報担当の先生に提案する。 2. 月に一度、集まった意見を生徒会で集計・分析し、対応可能なものと難しいものを仕分ける。 3. 全ての意見に対して、生徒会としての見解や対応状況を、校内掲示板やデジタル掲示板で必ず公表するサイクルを確立する。 |
| 昼休みの校内放送BGM(リクエスト制) | 単調になりがちな昼休みの時間を、音楽の力でよりリラックスできる、あるいは活気のある雰囲気にする。生徒が選曲に関わることで、学校への愛着を育む。 | 1. 放送委員会と全面的に協力体制を築く。 2. 楽曲のリクエスト方法(例:専用ボックスの設置、デジタルフォームの活用)と、選曲のルール(例:週ごとにテーマを設定、J-POPデー、洋楽デーなど)を明確に定める。 3. 先生方への配慮として、試験期間前はヒーリングミュージックに限定するなどの運用ルールも設ける。 |
| 雨天時の体育館・特別教室の利用ルール見直し | 雨天時に屋外で活動できず、エネルギーを持て余している生徒のために、安全で公平な屋内活動の場を提供する。生徒間のトラブル防止にも繋がる。 | 1. 各運動部のキャプテン、文化部の部長、そして顧問の先生方と「屋内施設利用に関する合同会議」の開催を提案する。 2. 体育館の利用を曜日や時間帯で区切る、柔道場や卓球場などの特別教室の利用枠を設けるなど、具体的な改善案を複数用意し、議論のたたき台とする。 3. 決定したルールは全校生徒に分かりやすく周知徹底する。 |
| 図書室の蔵書充実(生徒リクエスト制度の導入) | 生徒が本当に読みたい本を揃えることで、図書室の利用率を向上させ、生徒の読書習慣を促進する。学習意欲の向上にも貢献する。 | 1. 図書委員会と協力し、図書室内に専用のリクエストボックスとリクエストカードを設置する。 2. 月末にリクエストを集計し、ジャンルの偏りや予算を考慮した上で、購入希望リストを作成する。 3. 作成したリストを学校司書の先生に提出し、選書の参考にしてもらう。リクエストした本が入荷された際には、リクエスト者の名前(希望者のみ)を掲示するなどの工夫も行う。 |
これらの公約に共通しているのは、「誰の、どんな課題を解決するために(Why)」「何を(What)」「どのように実行するのか(How)」が具体的で明確である点です。自分の考えた公約も、この3つのポイントがしっかりと盛り込まれているか、客観的に見直してみることを強くおすすめします。
参考になる公約アイデア一覧
公約の方向性が定まらない、あるいはアイデアが枯渇してしまった場合に備え、参考になるアイデアをカテゴリー別に幅広く紹介します。これらをヒントに、自分の学校ならではの課題と結びつけて、オリジナルの公約へと昇華させてください。
学習環境の改善系
- 定期テスト対策のための学習サポートウィークの実施:テスト一週間前に、放課後の教室を教科ごとの質問スペースとして開放し、得意な生徒や先生が質問に答える「寺子屋」のような場を設ける。
- 放課後自習室の利用環境向上:単に場所を提供するだけでなく、利用ルールの明確化(私語厳禁、飲食禁止など)や、監督の先生への協力を要請し、静かで集中できる環境を整備する。
- 教室の空調設定に関するルール作り:「窓際の席は寒い」「送風口の真下は暑い」といった不公平感を解消するため、生徒の意見を集約し、休憩時間ごとの温度調整や換気など、快適な環境を維持するための具体的な運用ルールを提案する。
学校行事の充実系
- 文化祭・体育祭におけるデジタル技術の活用:各クラス・団体の出し物を紹介する特設サイトの作成や、当日の様子をライブ配信するなど、保護者や地域住民も巻き込んで盛り上げる企画を提案する。
- 全校生徒参加型の新イベント企画:学年の垣根を越えた交流を促進するため、「eスポーツ大会」や、謎解きを取り入れた「ウォークラリー」など、多様な生徒が楽しめる新しいイベントを企画・提案する。
学校設備の改善・有効活用系
- 傘立ての増設と「シェアリングアンブレラ」制度の導入:雨の日の傘の盗難や取り違えを防ぐ。また、家庭で不要になった傘を寄付してもらい、急な雨で困っている生徒に貸し出す制度を導入する。
- 校内掲示板の活性化:各委員会の活動報告や部活動の大会結果だけでなく、生徒が自由に作品を発表できる「アートスペース」や、おすすめの本を紹介するコーナーなどを設け、情報発信・交流の場として活用する。
- 購買部・食堂のメニュー改善交渉:生徒へのアンケートで人気メニューや新商品の希望を調査し、その結果を持って業者の方と直接交渉の場を設けてもらうよう、先生を通じてお願いする。
これらのアイデアを実現するためには、その多くが先生方や、関連する委員会、時には外部の業者の方々との連携・協力が不可欠です。
公約として発表する際には、「この計画は、〇〇委員会と協力して進めます」「実現のためには、先生方のご協力が必要です。そのための交渉を責任を持って行います」といった、具体的な協力体制やプロセスまで言及することで、計画性と実行意欲の高さを示し、公約の説得力を格段に高めることができます。
差がつく生徒会副会長の公約例と応用

- インパクトを意識した公約とは
- 少し変わった面白い公約の考え方
- 気持ちが伝わる演説のコツと例文
- 信頼される生徒会副会長の公約例まとめ
インパクトを意識した公約とは
生徒会選挙において、他の候補者との差別化を図り、有権者の記憶に強く残るためには、公約に「インパクト」を持たせることも有効な戦略です。ただし、ここで言うインパクトとは、前述の通り、実現不可能な大言壮語を吐くこととは全く異なります。
真のインパクトとは、「多くの生徒が内心望んでいるけれど、これまで誰も提案しなかったこと」や、「当たり前だと思っていた常識を覆す意外な視点」から生まれます。
例えば、以下に挙げる公約は、堅実な実現可能性を保ちつつも、生徒たちの心を強く掴むインパクトを秘めています。
- 月一回の「テーマ付き自由服登校デー」の試験的導入
単なる私服デーではなく、「自分の好きな色を取り入れた服装」「部活動Tシャツデー」など、月ごとにテーマを設定することで、一体感を醸成しつつ個性を表現する機会を提供します。校則の範囲内で実施できる点を強調し、まずは試験的な導入として先生方の理解を得るアプローチが現実的です。 - 給食に「地産地消メニュー」や「世界の名物料理」を導入
「A定食とB定食」のような選択制に加え、「自分たちの住む地域の特産品を使った給食」や「異文化理解に繋がる世界の料理」を月替わりで提供するアイデアです。食育の観点からも有意義であり、給食委員会や栄養士の先生との連携を密にすることで、実現の可能性を探ります。 - 校内Wi-Fiの学習目的での利用拡大と情報リテラシー講座の開催
調べ学習やオンライン教材の活用が不可欠となっている現代において、Wi-Fi環境の整備は喫緊の課題です。利用時間の制限やフィルタリングといった具体的なルール作りとセットで提案すると共に、「安全なインターネットの使い方」を学ぶ情報リテラシー講座の開催も公約に盛り込むことで、責任感のある姿勢を示すことができます。このような教育的な取り組みは、総務省も推進しており、説得力のある提案となります。
これらの公約は、単に目新しいだけでなく、「生徒の満足度向上」や「教育的価値の創出」といった明確な目的と繋がっているため、単なる人気取りの政策ではないと評価されやすくなります。
少し変わった面白い公約の考え方
選挙演説において、有権者の興味を強く引きつけ、会場の空気を掴むために、「面白い公約」を掲げるというアプローチは非常に効果的です。ユニークな公約は、候補者の柔軟な発想力や人柄を伝え、他の堅実な候補者との差別化を図る上で大きな武器となり得ます。ただし、その面白さが単なる「ウケ狙い」で終わってしまわないよう、細心の注意が必要です。
面白い公約を成功させる最大のコツは、そのユニークな企画の裏側に、「学校をより良くしたい」という真剣な目的や理念を明確に忍ばせることです。聴衆が笑ったり驚いたりした後に、「なるほど、そういう深い考えがあったのか」と納得できるようなストーリーを構築することが重要です。
面白い公約の例と、その裏にある真の目的(ストーリー)
- 公約:先生方の意外な一面(例:学生時代の部活動、好きな音楽など)を紹介する「先生プロファイルクイズ」を校内放送や掲示物で定期的に実施します。
目的(演説での語り口):「私たちは毎日先生方から多くのことを教わっていますが、先生方のことを深く知る機会は意外と少ないのではないでしょうか。この企画を通じて、先生方の人間的な魅力に触れることで、授業中の質問がしやすくなったり、進路相談がしやすくなったりと、生徒と先生のコミュニケーションをより円滑にし、信頼関係を深めたいと考えています。」 - 公約:地域のゆるキャラや伝統工芸の職人さんを学校に招待し、交流イベントを企画します。
目的(演説での語り口):「私たちはこの地域で学び、生活しています。自分たちの住む地域の魅力を再発見し、地域の方々と交流することで、学校と地域の連携を深め、将来、私たちが地域社会に貢献していくための意識を高めるきっかけにしたいのです。」 - 公約:学年末に、全校生徒の投票で「学校あるある大賞」を決定し、ささやかな賞品と共に表彰します。
目的(演説での語り口):「『この学校の生徒なら誰でも頷いてしまう』、そんな共通の体験は、私たちの見えない絆です。この企画を通して、学校生活の何気ない一コマをみんなで笑い合い、共有することで、全校生徒の一体感を醸成し、最高の思い出作りを促進したいと考えています。」
このように、一見するとただ面白いだけの企画に見えても、その背景にあるしっかりとした理念や目的を、自分の言葉で情熱的に語ることができれば、「この候補者はユニークな視点を持ちながら、学校のことを誰よりも真剣に考えている」と評価され、多くの生徒の心を動かし、力強い支持を集めることができるでしょう。
気持ちが伝わる演説のコツと例文
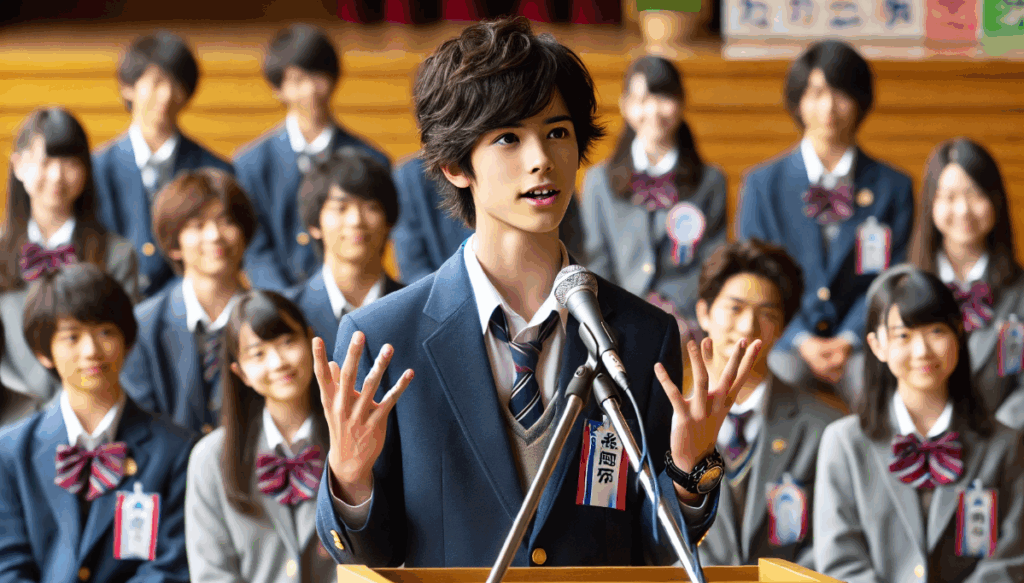
どれほど素晴らしい公約を練り上げたとしても、その魅力や実現への熱意が演説で伝わらなければ、票には結びつきません。多くの生徒の前で話すことは緊張を伴いますが、いくつかのコツを押さえることで、聴衆の心に響く、気持ちの伝わる演説を行うことが可能です。
ここでは、そのための基本的な構成と、表現力を高めるための具体的なテクニックを紹介します。
基本構成は論理的な「PREP法」を意識する
演説の骨子となる構成は、ビジネスプレゼンテーションなどでも用いられる「PREP法」を基本にすると、話が脱線せず、聴衆に内容が整理されて伝わりやすくなります。これは、結論から先に述べることで、聞き手の関心を引きつけ、話のゴールを明確にする効果があります。
-
- Point(要点・結論):「皆さん、こんにちは。私が生徒会副会長になったら、まず第一に『目安箱のデジタル化と回答率100%』を実現します。」
- Reason(理由):「なぜなら、現状の目安箱は意見を出しにくく、寄せられた意見がどうなったか分からない、という声が多くの友人から聞かれるからです。このままでは、生徒の声が学校運営に届きません。」
- Example(具体例・方法):「そのために、具体的には、今皆さんが使っている連絡アプリのアンケート機能を活用します。これなら匿名で24時間いつでも意見を送れます。そして、私たちが責任を持って全ての意見に目を通し、翌月の生徒会だよりで必ず回答を公表するサイクルを作ります。」
- Point(要点・結論の再強調):「この公約を通じて、皆さんの小さな声一つひとつを大切にし、風通しの良い学校を作ります。どうか、私〇〇に、皆さんのための仕事をさせてください。清き一票を、よろしくお願いいたします。」
演説を聴衆の記憶に残すための3つのテクニック
- 自分の「物語」を語る:ただ公約を説明するだけでなく、なぜ自分がその公約を実現したいのか、という個人的な想いや経験を語ることで、演説に血が通い、共感を呼びます。「私は入学したての頃、学校に馴染めず悩んでいました。その時、先輩がかけてくれた一言に救われた経験があります。だからこそ、今度は私が、全校生徒が安心して過ごせる環境を作る手助けをしたいのです」といったストーリーは、聴衆の心に深く刻まれます。
- 非言語コミュニケーションを意識する:言葉の内容だけでなく、話し方も重要です。少しゆっくり、はっきりとした口調で話すことを心がけましょう。また、最も伝えたいキーワードの部分で少し間を置いたり、声を強めたりすると効果的です。そして、自信を持って背筋を伸ばし、聴衆全体を見渡しながら、時にはジェスチャーを交えて語りかけることで、熱意とリーダーシップを印象付けることができます。
- 心に響く言葉を引用する:歴史上の人物の名言や、有名なことわざを効果的に引用すると、演説に深みと説得力をもたらします。「『一人の百歩より、百人の一歩』という言葉があります。私一人では何もできません。どうか、皆さんのその一歩を、私に託してください」のように、公約と関連付けて引用するのがポイントです。
完璧にスラスラと話すことだけが、良い演説ではありません。たとえ少し言葉に詰まってしまっても、誠実に、自分の言葉で一生懸命に語りかける姿勢こそが、何よりも人の心を動かすのです。自信を持って、あなたの想いを伝えてください。
信頼される生徒会副会長の公約例まとめ
この記事では、生徒会副会長選挙で勝利し、当選後も信頼される役員として活動するための、公約の考え方から具体的なアイデア、そして効果的な伝え方までを網羅的に解説しました。
最後に、本記事の重要なポイントを改めてまとめます。
- 生徒会副会長の最も重要な役割は会長を支える有能なサポーターであること
- 公約を考える上での最優先事項は実現可能性と具体性
- 「学校を楽しくする」といった抽象的なスローガンではなく具体的な行動計画を示す
- 公約のアイデアは自分や友人が日常で感じている身近な課題から見つける
- 生徒の意見を吸い上げる仕組み(意見箱やアンケート)の改善は鉄板の公約
- 挨拶運動や環境美化といった定番の公約は堅実で先生方からの理解も得やすい
- 中学生は特に先生や関係委員会との連携を前提とした公約を考えると良い
- インパクトのある公約とは単なる奇抜さではなく意外性と生徒の潜在的な願望を突くこと
- 面白い公約はユーモアの裏に隠された学校を良くしたいという真剣な目的を語ることが重要
- 実現不可能な公約は当選後の信頼を大きく損なうため絶対に避けるべき
- 演説の構成は結論から話すPREP法を意識すると聴衆に伝わりやすい
- 自分の経験や想いを自身の言葉で語ることが何よりの共感を呼ぶ
- 会長候補の公約を理解しそれをどう具体的にサポートするかという視点が有効
- 学校行事を円滑に進めるための実務的な改善案も副会長の役割に適している
- 公約の背景にある理念や目的をしっかりと持つことが信頼の基盤となる





