学級委員のスピーチは、多くの中学生にとって、クラスというコミュニティの前で初めて「リーダーとしての表現」を求められる重要な場ですよね。私も最初はとても緊張したのを覚えています。
この記事では、「学級委員 スピーチ 例文 中学生」というテーマを深く掘り下げ、単なる例文の紹介に留まらず、学級委員長として持つべき心の姿勢や、聞いているクラスメイトの心を掴む「面白い」スピーチの技術、そして最も基本となる立候補スピーチの具体的な作り方まで、ステップバイステップで紹介していきますね。
色々なテクニックがありますが、結論として、中学生のスピーチで最も大切なのは、「誠実さ」「前向きさ」、そして「自分らしさ」という3つの要素を、自分自身の言葉で短く、力強く伝えることです。
また、小学生時代のスピーチとの明確な違いや、高校生になっても応用できる普遍的なスピーチ構成についても詳しく解説しています。
そのため、初めて学級委員に挑戦する人はもちろん、「前回は上手くいかなかったな」とリベンジを誓う人にも役立つ内容になっているかなと思います。
最後には、スピーチ全体をビシッと締める、印象に残りやすい「意気込みの一言」の具体例も集めました。
この記事を読み終える頃には、あなたが自分の言葉で自信を持ってクラスメイトに語りかけ、クラスを良い方向に動かしていく、そんなスピーチがきっと作れるようになっているはずです。
- 学級委員長としてスピーチで意識すべきポイント
- 面白い立候補スピーチを成功させるコツ
- 小学生との違いから見る中学生らしい話し方
- 高校生にも応用できるスピーチ構成と最後の締め方
学級委員のスピーチの例文から学ぶ中学生の基本と考え方
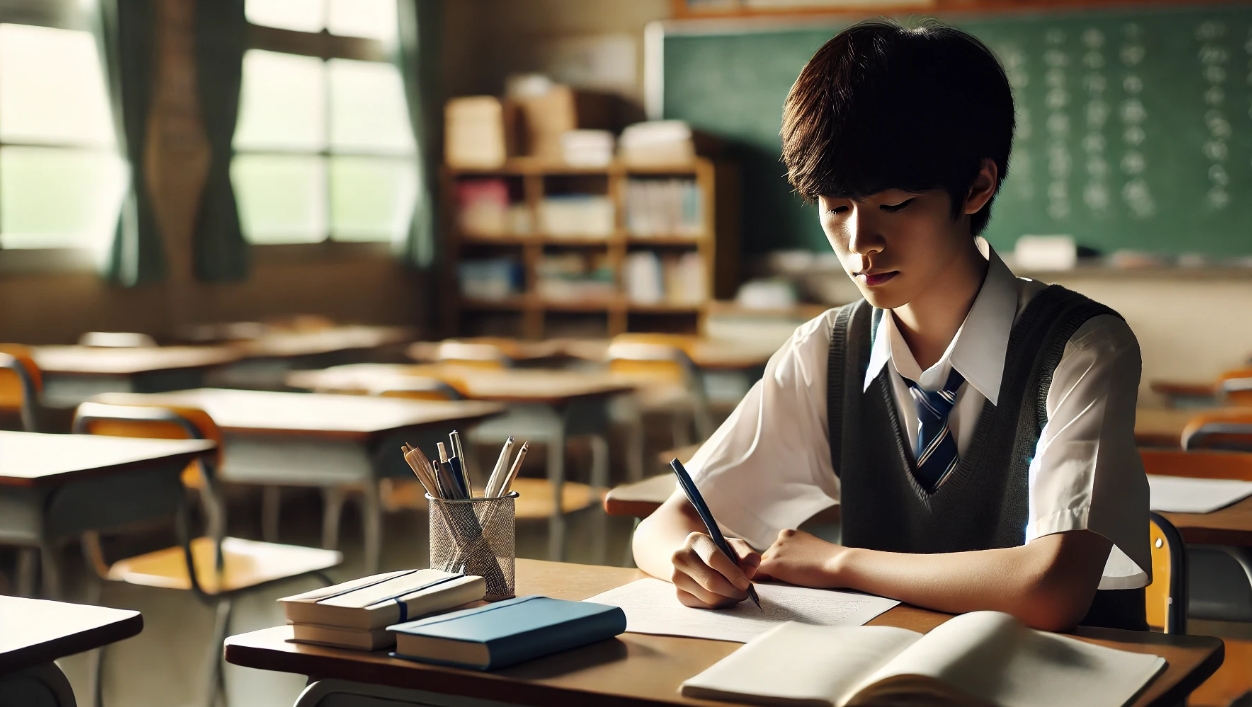
学級委員のスピーチって、本当に「伝え方」ひとつで、聞いているみんなの印象がガラッと変わるものですよね。
同じ「頑張ります」という一言でも、自信なさげに下を向いて言うのと、みんなの顔を見てハッキリ言うのとでは、信頼感がまったく違ってきます。中学生として、少し大人びた視点を持ちながら、自分らしさをどう表現していくかが大切なポイントになります。
ここからは、学級委員長としての心の持ち方、具体的な立候補スピーチの組み立て方、ちょっとユニークで面白い話し方の工夫、そして小学生時代とはどう違うのか、最後にビシッと決める「意気込みの一言」の例まで、スピーチを作る流れに沿って詳しく紹介していきますね。
どの内容も、ただ上手に話すためじゃなく、あなたの本気や誠実さをクラスメイトの心に届けるための、実践的なヒントばかりを集めました。
学級委員長として意識すべきポイント
学級委員長として立候補する上で、最も大切にしてほしいのは、「クラス全体のために行動するリーダーとしての自覚」を持つことです。スピーチは、その決意をみんなに伝える最初の場所。この姿勢を言葉に乗せることが、聞いている人の信頼を得るための第一歩になります。
よくある誤解ですが、学級委員長は「偉い人」や「指示を出す人」ではありません。むしろ、クラスメイト一人ひとりの意見に耳を傾け、時には先生方との「橋渡し」をする、大切な調整役なんですね。
だからこそ、スピーチでは「協調性」「責任感」「行動力」この3つを感じさせる言葉を選ぶのがすごく効果的です。たとえば、「みんなの意見を大切にしながら、文化祭が最高に盛り上がるよう、裏方として全力でサポートします」といった具体的なフレーズは、謙虚でありながらも前向きなリーダー像を強く印象づけます。
また、スピーチの言葉以上に、普段のあなたの行動が説得力を持ちます。「誰かが黒板消しで困っていたら自然と手伝う」「面倒な行事の準備を率先して行う」といった日々の小さな行動を、スピーチに盛り込むのも良いですね。
「私はいつも掃除を真面目にやっています」と直接的に言うのではなく、「このクラスが毎日気持ちよく過ごせる場所であるよう、小さなことでもコツコツと行動します」と表現する方が、中学生らしい誠実さが伝わります。難しい言葉を並べるよりも、実際の行動で信頼される人であることを示す方が、心に響くものです。
つまり、学級委員長として意識すべきは、「みんなのために汗をかける姿勢」と、その「誠実なリーダー像を自分の言葉で伝えること」です。あなたが実現したい理想のクラス像を具体的に描き、その実現のために自分がどう動くのか、その意志を短くても強く語ることで、聞いている人の「この人に任せてみたいかも」という気持ちを引き出すスピーチになります。
中学生らしい立候補スピーチの作り方
中学生の立候補スピーチで心がけたいのは、背伸びをしないこと。「わかりやすく」「前向きで」「自分らしい言葉」でストレートに話すことが何よりも重要です。どこかで聞いたような立派な表現や、大人びた難しい言葉を使おうとするよりも、等身大の自分の言葉で誠実に伝える方が、ずっと人の心に残ります。
まず、スピーチが苦手な人でも迷わない、基本的な構成を紹介しますね。「1. 立候補の理由(きっかけ) → 2. クラスへの思い(現状や理想) → 3. 目標や意気込み(具体的な行動)」この順番で話すと、とても自然にまとまります。「今のクラスは挨拶が少なくて寂しいと感じたから、私から元気な挨拶を広めたいと思い立候補しました」「みんながもっと気軽に意見を言い合えるような、話しやすい雰囲気をつくりたいです」といった具体的な理由や思いを述べると、あなたの真剣さがストレートに伝わります。
スピーチの基本構成(3ステップ)
- 【理由】なぜ立候補したのか?(例:「もっと明るいクラスにしたいから」「去年の学級委員を見て憧れたから」)
- 【思い】どんなクラスにしたいのか?(例:「みんなが主役になれるクラス」「いじめや仲間外れのないクラス」)
- 【目標】そのために何をするのか?(例:「意見箱を設置します」「行事の準備を全力でサポートします」)
次に大切なのが、構成を守りつつも「自分らしさ」をしっかり入れること。真面目な話ばかりだと、聞いている方も疲れてしまいますよね。そこで少しユーモアを交ぜると、一気に親しみやすさが生まれます。「見ての通り、背は小さいですが、やる気だけは誰にも負けません!」「ちょっとおっちょこちょいなところがありますが、その分、みんなの助けを借りながら、一緒にクラスを作っていきたいです!」のように、自分の個性や短所さえも前向きな言葉に変換する一言があるだけで、聴衆の印象はぐっと柔らかくなります。
そして最後に、テクニックとして「聞き取りやすさ」も大事です。焦って早口になると、せっかくの良い内容も伝わりません。落ち着いた声で、大切な言葉の前では少し「間(ま)」を意識すると、言葉に重みが出ます。原稿を丸暗記することに集中するよりも、「この思いだけは絶対に伝えたい」という気持ちを大切にすれば、多少言葉に詰まっても、それはあなたの誠実さとして伝わるはずです。自然で説得力のあるスピーチを目指しましょう。
面白いスピーチで印象に残すコツ

「面白いスピーチ」と聞くと、つい「爆笑を取らなきゃ」とハードルを上げてしまいがちですが、それは違います。学級委員のスピーチにおける「面白い」とは、「笑わせること」よりも「聞く人をリラックスさせ、親近感を持ってもらうこと」が目的だと考えると、すごく上手くいきますよ。もちろん真面目さは求められますが、ほんの少しのユーモアは、あなたのスピーチをその他大勢の候補者から際立たせるスパイスになります。
最大のポイントは、無理にギャグを言うのではなく、自分のキャラクターをありのまま活かすことです。たとえば、いつも元気で明るい性格の人なら「私の元気と大きな声で、クラスの空気を毎日ポジティブにします!」と宣言するだけで十分面白いですよね。逆におっとりした人なら「私はカタツムリのように歩みは遅いかもしれませんが、一歩一歩、着実にみんなの意見をまとめていきます」なんていう風に、自分の個性を前向きな比喩で表現するのも一つの手です。
また、「自分の経験談」、特に「ちょっとした失敗談」から笑いを生むのも非常に効果的です。「前回の球技大会では、張り切りすぎて空振りばかりでしたが、今度の学級委員では、みんなの意見を空振りしないよう、しっかりキャッチします!」というように、少し自虐を混ぜつつも「今度は頑張る」という決意に繋げると、共感と笑いが同時に生まれます。
一番大切なのは、笑いを狙いすぎないこと。やりすぎると「ふざけている」「軽い」という印象を与えてしまい、リーダーとして最も重要な「信頼」を損ねてしまいます。スピーチの大部分は真面目な決意表明で構成し、ユーモアは冒頭の掴みや、中盤のアクセントとして「ひとつまみ」加える程度がベスト。この絶妙なバランスを意識して、「明るく、前向きに、自分らしく」を軸にユーモアを取り入れると、聞く人の心に強く残るスピーチになります。
小学生と中学生のスピーチの違い
小学生の頃にも学級委員の選挙はあったかもしれませんが、中学生のスピーチは、それとは明確に違う点が求められます。その最大の違いは、「伝える内容の深さ」と「自分の役割に対する意識」にあります。小学生のスピーチは、元気や素直さ、「みんなと仲良くしたい」という気持ちが中心でも受け入れられました。しかし、中学生になると、より客観的にクラスを見つめ、具体的な課題解決に向けた責任感や考え方が求められるようになります。
例えば、小学生なら「明るく楽しいクラスにしたい」という感情中心の表現が多くなります。一方、中学生では、「明るいクラスにするために、具体的に何をすべきか」まで踏み込むと効果的です。「全員が安心して発言できる環境をつくるために、まずは私から、色々な人に積極的に声をかけます」「行事を成功させるために、意見が対立した時は、間に入って調整する役を引き受けます」など、具体的な行動や目標を盛り込むことが求められます。
これは、中学生に「自主、自律及び協同の精神」や「主体的に社会の形成に参画」する態度が求められるようになるためです。(出典:文部科学省『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説』)
また、話し方そのものにも違いが出てきます。小学生のスピーチは元気いっぱい、大きな声で話すことが評価されがちですが、中学生はそれだけでは不十分です。落ち着いたトーンで、しっかりと相手の目を見て「聞かせる話し方」を意識することがポイント。熱意は必要ですが、それ以上に「この人なら冷静にクラスをまとめてくれそう」という安心感を与える姿勢が、成熟した印象と信頼感に繋がります。
小学生と中学生のスピーチ比較
| 比較ポイント | 小学生のスピーチ | 中学生のスピーチ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 元気・やる気のアピール | 信頼感・責任感の表明 |
| 内容の中心 | 感情・願望(〜したい) | 具体的な目標・行動(〜する) |
| 求められる役割 | クラスのムードメーカー | クラスの調整役・橋渡し役 |
| 話し方 | 大きく元気な声 | 落ち着いたトーン・説得力 |
つまり、中学生のスピーチは「自分の熱い思い」に加えて、「それを実現するための冷静な行動計画」を語る段階に進むのです。この意識の違いを持つだけで、あなたのスピーチはぐっと説得力を増し、同級生からも「中学生らしい」と評価される仕上がりになりますよ。
スピーチで伝えるべき意気込み 一言の例
スピーチの最後にバシッと決める「意気込みの一言」は、たとえ短くても、聞いている人の心に最も強く響くメッセージとなります。スピーチ本編の内容が少し飛んでしまっても、この最後の一言が良ければ「良いスピーチだった」と印象づけられるほど、重要な決め手になるんです。
意気込みを伝える際は、「ポジティブ(前向き)」「具体性(何をするか)」「決意(言い切る)」の3つを意識しましょう。「〜できたらいいなと思います」といった弱気な表現はNGです。「〜します!」「〜をつくります!」と力強く言い切ることが大切です。たとえば、「みんなで協力して、笑顔の絶えない最高のクラスをつくります!」「私は、クラス全員の意見をまとめ、誰もが話しやすい雰囲気をつくることを約束します!」といった一言は、誠実さと具体的な行動力を同時に感じさせます。
また、ここでも「自分らしさ」を出すことを忘れずに。「私の取り柄である元気と笑顔で、このクラスの毎日を明るく照らします!」「たとえ失敗しても、すぐに立ち上がって最後まであきらめずに頑張ります!」など、自分の性格や大切にしている信念を反映した言葉は、他の候補者との明確な差別化にもつながります。
タイプ別「意気込みの一言」例文
- 【誠実さアピール型】「見えないところの仕事こそ、責任を持って引き受けます。よろしくお願いします!」
- 【行動力アピール型】「言葉よりも行動で示します。クラスのために、誰よりも先に動きます!」
- 【協調性アピール型】「私一人では何もできません。どうか、みんなの力を貸してください。一緒に最高のクラスにしましょう!」
- 【ポジティブ型】「毎日『学校が楽しい!』とみんなが思えるクラスにします!私に任せてください!」
スピーチの最後の一言は、あなたがクラスに向ける「本気度」の集大成です。聴衆の印象に最も鮮烈に残る部分だからこそ、自分の信念をすべて込めて、照れずに、自信を持って言い切るようにしましょう。その真っ直ぐな視線と力強い言葉が、聞く人に「この人になら任せてもいいかも」と思わせる、最強のスピーチになります。
学級委員のスピーチの例文集 | 中学生が参考にすべき実例

ここからは、実際にスピーチ原稿を作成する上で、すぐに役立つ「例文」と「構成のコツ」をセットで紹介していきますね。
まずは、学級委員長として堂々と決意を述べるための王道スピーチ、次に、少しのユーモアで場を和ませる面白いスピーチ、時間がない時でも伝わる短い立候補スピーチ、さらに高校生になっても応用できる構成の組み方、そして最後に、聞いている人の記憶に強く残る締め方まで、具体的なシチュエーションに沿って順番に解説します。
ただし、これらの例文はあくまで「土台」です。一番大切なのは、あなたの個性やクラスへの本物の想いを込めて、「あなた自身の言葉」に置き換えること。そのヒントを探しながら、聞く人の心に届くオリジナルのスピーチを完成させましょう。
学級委員長向けスピーチの例文
学級委員長のスピーチでは、「クラスを良い方向に引っ張っていく覚悟」と、「決して独りよがりにならず、仲間と協力する姿勢」という、一見相反するように見える2つの要素を、バランス良く明確に伝えることがとても大切です。中学生にとっての学級委員長は、強いリーダーであると同時に、みんなの声を吸い上げる「調整役」でもあります。そのため、スピーチでは責任感の強さと、共感力の高さの両方を感じさせる言葉を選ぶのが効果的です。
たとえば、具体的で誠実な次のような例文があります。
「この度、学級委員長に立候補しました、〇〇です。
私は、このクラスが、みんなにとって安心して自分の意見を言える場所であってほしいと思い、立候補しました。もし選ばれたら、まずは人の話をしっかりと聞き、クラスの中で困っている人がいたらすぐに手を差し伸べられる、そんな委員長を目指します。
私一人の力は小さいですが、みんなと力を合わせれば、必ず笑顔の絶えない最高のクラスが作れると信じています。どうぞ、よろしくお願いします。」
このスピーチのポイントは、「1. 立候補の理由(安心できるクラスにしたい)」→「2. 目指す姿(話を聞き、手を差し伸べる)」→「3. 決意(みんなと力を合わせて)」という3つの要素が非常に明確に盛り込まれている点です。特に「みんなと力を合わせて」という言葉を最後に入れることで、強いリーダーシップをアピールしつつも、独りよがりな印象を避け、協調性を強く強調できていますよね。
学級委員長のスピーチでは、立派すぎる言葉を並べるよりも、「誠実さ」「思いやり」、そして「クラスとしての一体感」を大切にする姿勢を見せることで、聞いているクラスメイトに「この人なら信頼できる」という安心感を与えることができます。
面白いスピーチで笑顔を生む例文
面白いスピーチで印象を残す最大のコツは、「自分の弱みや失敗、個性をポジティブに笑いに変えること」です。無理に流行りのギャグを言う必要は全くありません。むしろ、自分を少し下げる(自己開示する)ことで、聞いている側の緊張を解き、自然体のユーモアで場の空気を和ませることが狙いです。
たとえば、次のような、短所を長所に転換する例文が効果的です。
「みなさん、こんにちは。私は忘れ物が多いことで有名ですが、今日、このスピーチの原稿だけは絶対に忘れませんでした!
こんな私ですが、このクラスのみんなともっと仲良くなり、役に立ちたいと思って、勇気を出して学級委員に立候補しました。
忘れ物チェックは苦手かもしれませんが、みんなの笑顔をチェックすることだけは誰にも負けません!笑顔で協力し合えるクラスにしたいです!」
このスピーチでは、まず「忘れ物が多い」という自分の短所をユーモアに変え、聞く人の心を掴んでいます。そして、「でも、クラスのために頑張りたい」という前向きなギャップで締めくくっています。聞いている方は思わずクスッと笑顔になり、同時にその努力しようとする姿勢に共感を覚えるはずです。
ただし、再三になりますが、「面白い=軽い」ではありません。あくまでスピーチの目的は「親しみやすさ」と「印象に残ること」です。上記のように、少し笑えるエピソードを「掴み」として入れながらも、最後は「クラスのために何をしたいか」という真面目な思いを添えること。この緩急のバランスが、ただ面白いだけではない、深みのある感動的なスピーチに繋がります。中学生らしい明るさを大切に、あなたらしいスピーチを心がけてみてください。
立候補スピーチに使える短い例文集

スピーチの時間が1分も無い、なんてこともよくありますよね。でも、短いスピーチであっても、伝えるべきポイントをギュッと凝縮させれば、しっかり印象に残すことは可能です。特に中学生の立候補スピーチでは、ダラダラと長く話すよりも、「簡潔で分かりやすい言葉」で熱意をまとめることが非常に効果的です。
たとえば、すぐに使える「30秒以内」を想定した短文例文をいくつか紹介します。
【協調性アピール】
「私は、みんなが安心して学校生活を送れるクラスをつくりたいです。そのために、一人ひとりの声を大切にします。協力し合って、楽しいクラスにしましょう!」【責任感アピール】
「責任を持って、みんなの意見をまとめ、先生方へしっかり伝える学級委員になります!縁の下の力持ちとして、クラスを支えます。よろしくお願いします!」【元気・明るさアピール】
「私の長所は、この明るい笑顔です!この笑顔と元気で、クラスの雰囲気を明るくします!どうぞ、よろしくお願いします!」
どれも非常に短いですが、「1. どんなクラスにしたいか(思い)」→「2. 何をするか(行動)」→「3. 決意」というスピーチの核となる要素がしっかり含まれているのが分かるかなと思います。短いスピーチほど、一言一言に重みが出ます。だからこそ、自信なさげに言うのではなく、語尾を「〜します!」とハッキリ言い切ることが何よりも大切です。
限られた時間で印象を残すには、あれもこれもと欲張らず、「誠実さ」「前向きさ」「やる気」のどれか一つでも、簡潔に伝えることがポイント。短くても、心のこもったまっすぐな言葉は、必ず聞いている人に伝わります。
高校生にも応用できるスピーチ構成
高校生のスピーチになると、クラス運営へのより深い洞察力や、具体的な問題解決能力、高いレベルの表現力が求められます。ですが、実はスピーチの基本的な「型」は、中学生も高校生も同じなんです。つまり、中学生のうちからこの論理的な構成に慣れておけば、高校生になってからも、さらには大学受験の面接や将来のプレゼンテーションでもずっと役立ちます。
その最強の構成が、「1. 理由 → 2. 目標 → 3. 行動計画 → 4. 意気込み」という4ステップの流れです。
たとえば、次のように構成すると、非常にスムーズで説得力のあるスピーチになります。
スピーチの黄金構成(4ステップ)
- 【理由】「私が立候補したのは、自分のクラスをもっと活発で、意見交換が自由な場所にしたいと強く思ったからです。」
- 【目標】「そのために、文化祭や体育祭だけでなく、日常の授業から全員が意見を言いやすい環境をつくります。」
- 【行動計画】「具体的には、朝の会で『プチ討論会』の時間を設けたり、委員会活動の報告を分かりやすく掲示したりして、積極的に意見をまとめていきます。」
- 【意気込み】「責任を持って、クラスの中心として全力で頑張ります。よろしくお願いします。」
この構成は、中学生のスピーチにももちろん応用可能です。論理的で分かりやすいだけでなく、スピーチ原稿を作る際に、自分の考えを整理するのにも非常に役立ちます。
高校生では特に「リーダーシップ」や「主体性」が評価されます。中学生と高校生の違いは、この「3. 行動計画」の具体性にあるんですね。中学生のうちから「なぜやるのか(理由)」と「そのために何をするのか(行動)」をセットで考えるクセをつけておくと、進学後も、自信を持って堂々とスピーチできる本物の力が身につきます。
スピーチの最後に好印象を残す締め方
スピーチの「最後の一言」は、聞いている人の心に最も強く、そして長く残る部分です。まさに「終わりよければすべてよし」。だからこそ、明るく、前向きで、力強い言葉で締めくくることが非常に重要です。この最後の一言で、あなたの本気度が伝わり、「この人なら任せたい」と、投票行動の最後のひと押しが決まる可能性だってあります。
効果的な締め方のポイントは、「決意」と「一体感」を込めることです。具体例をいくつか挙げると、
【一体感を促す締め】
「みんなで協力して、1年後、『このクラスで良かった』と全員が思える、最高のクラスをつくりましょう!よろしくお願いします!」【誠実さを伝える締め】
「派手なことはできませんが、小さなことからコツコツと、笑顔で頑張ることを誓います!あなたの一票を私にください!」【力強い決意の締め】
「私は必ず、みんなが安心して過ごせるクラスにします!私を信頼してください。よろしくお願いします!」
このように、ポジティブで明確なメッセージを「言い切る」形にするのが最大のポイントです。「〜したいと思います」のような曖昧な言葉は避け、「〜します!」と自信を持って言い切ることで、あなたのリーダーらしさが格段に伝わります。
そして、言葉を言い終わった後、すぐに下を向かないこと。最後の一言を言い終えたら、にっこりと笑顔を添え、クラス全体を見渡し、それからゆっくりと、深くお辞儀をしましょう。
言葉(言語)だけでなく、その表情や態度(非言語)にも誠実さを込めることで、聴衆の印象はぐっと良くなります。
最後の一言は、あなたのスピーチ全体に美しい「余韻」を作る重要な部分です。心を込めた一言と、丁寧な所作で締めくくることで、聞く人の記憶に深く刻まれるスピーチになります。
まとめ
ここまで、学級委員のスピーチについて、考え方から具体的な例文まで詳しく見てきました。最後に、この記事の大切なポイントをまとめますね。
この記事のポイントまとめ
- 学級委員のスピーチ(中学生)では、難しい言葉よりも「誠実さ」と「前向きさ」を自分の言葉で伝えることが大切
- 学級委員長は「指示する人」ではなく、みんなの意見を聞く「行動力」と「協調性」を言葉で示す
- 「面白いスピーチ」とは、爆笑させることではなく、自分の個性を活かして聞く人をリラックスさせ、親近感を持ってもらう工夫が効果的
- 小学生との違いは、「〜したい」という感情表現よりも、「〜する」という具体的な責任感や目標を語る点にある
- 立候補スピーチの基本構成は「1. 理由 → 2. クラスへの思い → 3. 意気込みの一言」の流れが自然で伝わりやすい
- 短いスピーチでも「思い・行動・決意」の3要素を盛り込むことで、熱意はしっかり印象に残せる
- 高校生にも応用できる黄金構成は「1. 理由 → 2. 目標 → 3. 行動計画 → 4. 意気込み」の4ステップ
- スピーチの最後は「〜します!」と前向きな言葉で締め、自信を持って言い切ることが聴衆の信頼に繋がる
- 面白い話し方や、自分らしい失敗談などのエピソードは、他の候補者との差別化になり記憶に残りやすい
- 言葉だけでなく、堂々とした態度、笑顔、そして丁寧なお辞儀が、学級委員としての信頼を築く大切な第一歩になる
学級委員のスピーチは、決して上手に原稿を読むためのものではなく、「クラスを良くしたい」という、あなたの熱い思いを自分の言葉で形にする場です。
学級委員長としての責任感、仲間と協力する協調性、そして何よりも「あなたらしさ」を込めた言葉が、クラスメイトの心を動かします。小学生から中学生、そして高校生へと成長していく中で、スピーチで語るべき内容も深まり、あなたの言葉には少しずつ重みが増していきます。
たとえ短い時間であっても、誠実な気持ちを込め、前向きな意気込みを一言に託して、あなたらしいスピーチでクラスをより良い方向へ導いていきましょう。あなたの勇気ある立候補を、心から応援しています!


