生徒会演説で「面白いけど本気が伝わるスピーチ」をしたいと考える人にとって、最も大切なのは“笑い”と“誠実さ”の絶妙なバランスです。
中学生でも高校生でも、多感な時期の聞く人の心を動かすには、表面的な言葉だけでは不十分です。「共感」「ユーモア」「個性」という3つの要素を上手に組み合わせることが欠かせません。
ウケ狙いだけの演説では「面白い人」で終わってしまい、リーダーとしての信頼は得られません。逆に、真面目すぎる正論ばかりでは、どれほど素晴らしい内容でも「退屈な時間」と認識され、記憶に残りません。
だからこそ、学校生活の貴重な時間である3分という短い時間で強烈な印象を残すには、「つかみ」から「締めの言葉」まで計算された流れを意識し、聞く人の心に深く刺さる“コツ”を押さえることが何よりも重要になるのです。
この記事では、一見相反するように思える「面白さ」と「本気(誠実さ)」を共存させ、あなたの立候補を力強く後押しする生徒会演説の作り方を、具体的な実例や構成術とともにわかりやすく徹底解説します。
- 中学生にも伝わる、ウケ狙いになりすぎない「親しみやすい」面白い演説の作り方
- 高校の生徒会で「この人なら任せられる」と差がつくスピーチ術と構成のコツ
- 限られた3分で聴衆を惹きつけ、飽きさせない「つかみ」と効果的なユーモアの活かし方
- 聴く人の心に響く「締めの言葉」で、投票日当日まで印象に残り続ける演説を作る方法
生徒会演説の例文で面白いスピーチの基本と魅せ方

生徒会の演説で「面白いけど本気が伝わるスピーチ」を目指すなら、ただ流行りのネタやギャグを盛り込むだけでは不十分です。それは単なる「ウケ狙い」であり、聴衆を一時的に笑わせることはできても、あなたへの「信頼」や「一票」には繋がりません。
本当に求められるのは、聴衆を笑わせつつも「この人なら学校を良くしてくれそう」という信頼感を勝ち取り、自分の熱い思いをしっかり届けるための、計算された構成力と表現力です。
ここからは、中学生から高校生まで、学年や学校の雰囲気に応じて使い分けられる実践的なコツを、順を追って詳しく紹介していきます。
まずは、演説の土台となる「中学生にも伝わる面白い演説の考え方」から始まり、最も難しいウケ狙いと真面目さのバランスの取り方、3分という制限時間で効果を最大化する構成術、より論理性が求められる高校生向けの話し方、そして聴衆の記憶に焼き付くユーモアの活かし方までを、深く掘り下げて解説します。
あなたの演説が、ただの「面白い話」から「笑えて心に深く残る」本物のスピーチに変わるヒントを、一つずつ確実に見ていきましょう。
中学生にも伝わる面白い演説の考え方
生徒会演説で中学生に「面白い」と感じてもらうためには、笑いを取ること自体を目的にするのではなく、「親しみやすさ」と「自分らしさ(等身大であること)」を大切にすることが何よりも重要なポイントです。
中学生の聴衆は、大人が使うような難しい言葉や立派すぎる公約よりも、自分たちの日常に根差したリアルな感覚に強く共感しやすい傾向があります。だからこそ、日々の学校生活で誰もが一度は感じたことのある“あるあるネタ”(例:「給食の献立に一喜一憂する」「定期テスト前の謎の自信と結果のギャップ」「部活のキツい練習」など)を冒頭の「つかみ」に入れることで、最初のわずか数秒で「あ、この人、私たちのこと分かってる」という仲間意識を生み出し、場の空気をつかむことができます。
例えば、単なる自己紹介から入るのではなく、
「朝のチャイムが鳴ってから昇降口をダッシュし、ギリギリ教室に滑り込む常習犯の〇〇です。ですが、そんな私だからこそ、“誰もが朝起きるのが楽しみになる学校”を目指します!」
というように、自分の弱点や失敗談をあえてユーモラスに表現すれば、完璧な優等生よりもずっと身近に感じられ、自然な笑いと共感を得られます。
また、中学生にとっての「面白い」演説とは、単にギャグやネタが連発されることではなく、最終的に「この人なら、今の退屈なルールを変えてくれそう」「この人がリーダーなら、学校生活がもっと楽しくなりそう」と感じさせることに本当の価値があります。
そのため、面白さの中にも必ず「なぜ自分が立候補したのかという動機」や「学校を具体的にどう良くしたいのかという熱い想い」を、自分の言葉で織り込むことが大切です。
中学生には“立派な正論よりも、不器用でも伝わる人柄”が響きます。完璧な言葉を並べ立てるよりも、「自分もみんなと同じ生徒なんだ」という「等身大の自分」を素直に見せる演説が、結果として最も印象的で心に残るスピーチになるのです。
ウケ狙いと真面目さを両立させるコツ
生徒会演説で一番難しく、そして最も重要なのが、「笑いを狙いすぎて、ふざけているだけの人に見えないようにすること」です。
ウケ狙いと真面目さ(誠実さ)を両立させるには、まず「笑いを目的ではなく、本題を伝えるための手段にする」という意識改革が不可欠です。笑いは、緊張している聴衆の心を開き、自分という人間に興味を持ってもらうための“導入の潤滑油”として使うのが理想です。
文部科学省は、生徒会活動を「生徒が主体的に行う自治的活動」と位置づけています。 (参照:文部科学省「生徒指導提要(改訂版)」) この「主体性」や「自治」こそが、あなたの「本気度」の核となります。笑いは、この本気度をより多くの人に届けるための、あくまで「手段」なのです。
例えば、最初の自己紹介で軽く笑いを取り、聴衆の顔がほころんだ瞬間に、すぐに表情を引き締め、自分の本気の思いや具体的な公約を語る構成にすると、聴衆は「面白いだけじゃなく、しっかり考えている人だ」という良いギャップを感じ、強く印象づけられます。
(例)「私の特技は、昼休みの購買で、目当てのパンを誰よりも早くゲットするスピードです。(ここで一拍)…しかし、生徒会では、その“行動力の速さ”で、皆さんの意見を誰よりも早く実現するために全力を尽くします!」
といった具合に、ユーモアのある一文を「フリ」として使い、それを真面目な公約や自己PRに「転換」させることが非常に効果的なポイントです。
また、言葉遣いにも細心の注意が必要です。ふざけた表現や俗語が多すぎると、聴衆や先生方からの信頼性が一気に下がってしまいます。「です・ます」調の丁寧な言葉を基本としながら、要所で「軽い冗談」や「親しみやすい表現」をスパイスとして加える、というバランスを意識すると良いでしょう。
最終的に最も大切なのは、「笑わせた後に、必ず共感させる(あるいは納得させる)」という流れを構築すること。
この「緊張から緩和、そして再び緊張(集中)」という流れを意識することで、ウケを狙いつつもあなたの誠実さがしっかりと伝わる、聴く人の心に深く響く演説になります。
3分で聴衆を惹きつける構成の作り方
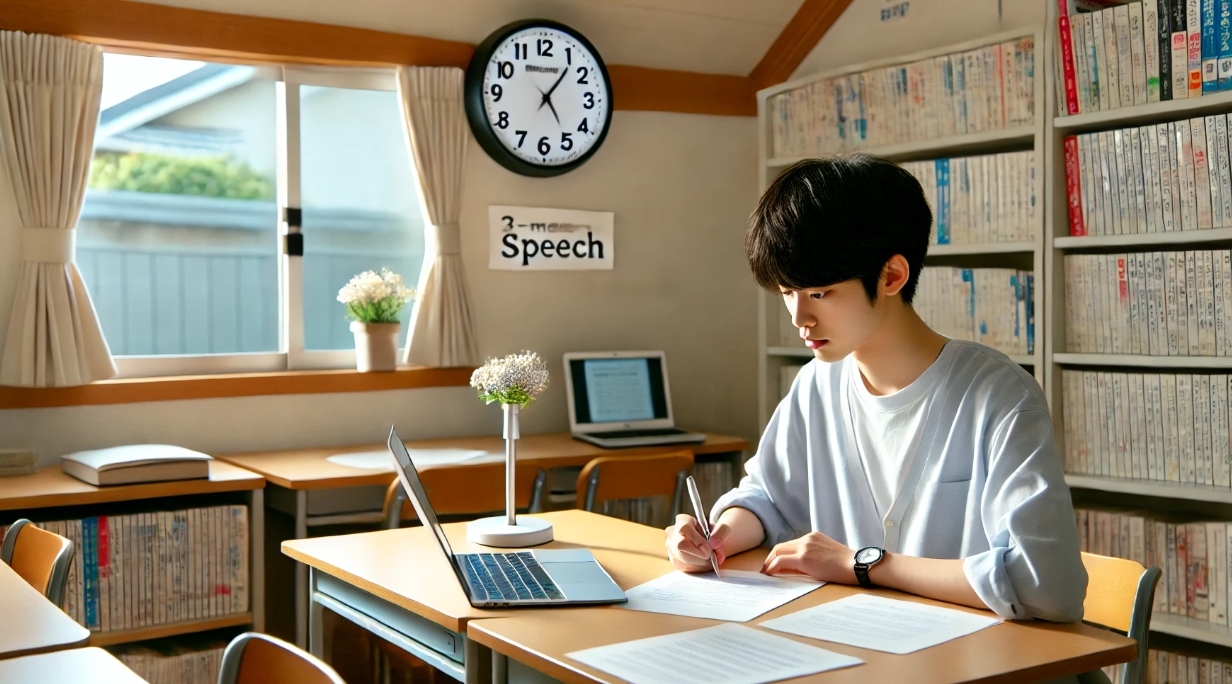
学校にもよりますが、生徒会演説の持ち時間は3分程度が一般的です。この短い時間で聴衆を惹きつけるには、「つかみ(導入)・展開(本論)・結び(結論)」の三段構成を明確に意識し、時間配分を最適化することが重要です。理想は、最初の30秒で聴衆の心を掴み、続く2分で最も伝えたい公約やビジョンを語り、最後の30秒で印象的な一言で締める構成です。
まず“つかみ”では、前述の通り、笑いと共感を生む「あるあるネタ」や「ユーモラスな自己開示」を取り入れましょう。
「昨日も宿題の提出を忘れて、先生に厳重注意を受けました。本当に反省しています。(少し間を置いて)…でも、そんな私だからこそ、“うっかり忘れても大丈夫”ではなく、“誰もが宿題を前向きに取り組めるような楽しい学校”を作りたいと本気で思っています!」
といった形で、ユーモラスな自己開示からスタートすることで、会場の堅苦しい雰囲気が一気に柔らぎます。
次に“展開”では、自分の公約やビジョンを具体的に伝えます。ここで陥りがちなのが、アレもコレもと公約を詰め込みすぎることです。3分では伝わりません。公約は「最も実現したいこと一つ」に絞り、「なぜそれをやりたいのか(動機)」と「どうやって実現するのか(具体策)」を、中学生にも分かる言葉で簡潔に説明することが大切です。
最後の“結び”では、ダラダラと続けるのではなく、短く、力強く、前向きなメッセージで締めくくりましょう。
「私と一緒に、明日も来たいと誰もが思える、笑顔で通える学校を作っていきましょう!清き一票をよろしくお願いします!」
といったポジティブで未来志向の言葉で終えると、聴衆の記憶に強く残り、演説全体が引き締まります。
3分間で効果的な構成例を以下のテーブルにまとめます。
| 構成 | 時間配分(目安) | 主な内容 | 目的とポイント |
|---|---|---|---|
| つかみ(導入) | 30秒〜45秒 | ・挨拶と自己紹介 ・ユーモラスな自己開示(失敗談、あるあるネタ) |
・聴衆の緊張をほぐし、注目を集める ・「この人の話は面白そう」と思わせる |
| 展開(本論) | 1分30秒〜2分 | ・立候補した動機(なぜやりたいのか) ・最も重要な公約(一つに絞る) ・公約の具体策(どうやるのか) |
・演説の核。「本気度」と「実現可能性」を伝える ・難しい言葉を使わず、具体的に語る |
| 結び(結論) | 30秒 | ・改めて決意表明 ・聴衆への呼びかけ(未来への期待) ・最後の挨拶 |
・最も印象に残る部分。力強く、前向きに! ・感謝の気持ちを込めて締めくく_る |
3分という制限の中で最も伝わるスピーチは、多くのことを詰め込んだものではなく、“短く・楽しく・本気”のバランスが取れた、焦点の定まった構成なのです。
高校の生徒会で差がつくスピーチ術
高校の生徒会演説では、中学生の時よりも聴衆が成熟しており、「論理性」と「人間味」の両立が高度に求められます。中学生には「楽しそう」という感覚的な共感が響きやすいのに対し、高校生は「その公約は本当に実現できるのか?」という視点で冷静に聞いています。
ただ面白いだけでは、一発ギャグとして消費され、印象に残りません。そこで重要になるのが、“笑いの中に明確な目的とロジックを込める”高度なスピーチ術です。
例えば、
「私は文化祭の準備で、いつも遅刻ギリギリで作業に参加していました。(ここで笑い)しかし、誰よりも効率的な作業手順を考え、結果的にクラスの準備を一番早く終わらせました。この経験を活かし、生徒会でも“アイデアと実行力”で学校を良くするアイデアを誰よりも早く出します!」
というように、ユーモアを活かしつつも、それが自身の「問題解決能力」や「行動力」のアピールに直結するよう構成することで、知的で誠実な印象を与えることができます。
高校生の場合、聴衆は「共感」と同時に「納得」を強く求める傾向があります。したがって、「学校行事を盛り上げます」といった曖昧な公約ではなく、「スマートフォンの校内利用について、具体的なルール案を提示し、全校生徒で議論の場を設けます」など、具体的な改善策や実現へのプロセスを一言でも入れることで、演説全体の説得力が格段に増します。
さらに、声のトーンや「間(ま)」の取り方も重要です。全体的に早口でまくし立てるのではなく、あえて落ち着いた声でユーモアを交え、公約を語る場面ではしっかりと間を取って強調することで、“面白いけれど、冷静に物事を判断できるリーダー”という信頼感のある印象を与えられます。
つまり、高校生の生徒会演説で他者と明確な差をつける秘訣は、以下の三拍子を意識することです。
高校生に響く「三拍子」
- ユーモア(親しみやすさ):聴衆の心を開くための導入
- ロジック(論理性):公約の具体性と実現可能性で「納得」させる
- パッション(人柄・情熱):「この人に任せたい」と思わせる人間的魅力
印象に残る演説を作るユーモアの使い方
ユーモアは、正しく使えば生徒会演説における最大の武器となります。しかし、使い方を誤れば「ふざけている」と一蹴される諸刃の剣でもあります。成功の鍵は、それが“笑いを取るための笑い”ではなく、“自分の本気や公約を効果的に伝えるための笑い”になっているかどうかです。
本当に印象に残る演説とは、笑った瞬間のことよりも、「あの面白い話、実はすごく深い意味があったな」と後から思い出してもらえる演説です。
たとえば、
「私は、クラスで一番忘れ物が多い常習犯として有名です。(笑い)…だからこそ、忘れ物をしてしまう人の気持ちが誰よりも分かります。忘れ物ゼロを目指すのではなく、万が一忘れても、生徒同士で助け合える“シェアリング・ボックス”の設置を提案します!」
というように、自分の失敗談や弱点を、具体的な公約や他者への優しさへと前向きに転換することで、単なる自虐を超えた「信頼」と「期待」を同時に得られます。
ユーモアを入れるときに絶対に守るべき鉄則は、“他人をイジって笑う”のではなく“自分をネタにして笑わせる”ことです。特定の友人や先生、あるいは特定の集団を笑いの対象にすると、それは「いじめ」や「差別」と受け取られ、一瞬で信頼を失います。自分の失敗談や学校生活の「あるある」を使うことで、誰も傷つけない、温かい共感が生まれます。
さらに、ユーモアを使う効果的なタイミングは、主に「冒頭(つかみ)」「展開の転換点(中だるみ防止)」「締めの直前(後味)」の3か所です。特に締めの直前に小さな笑いを入れ、会場の雰囲気を再び柔らかくしてから、本気の締めの言葉を伝えることで、そのメッセージがより深く、温かく聴衆の心に届きます。
笑いを戦略的に味方につけることで、あなたの演説は単なる“堅苦しい発表”から、“記憶に残り続ける魅力的なスピーチ”へと劇的に変わるのです。
生徒会演説の例文で面白い話し方と実践テクニック

実際に全校生徒の前に立つスピーチ本番では、「何を話すか(内容)」が完璧であっても、「どう話すか(伝え方)」が伴わなければ、その魅力は半減してしまいます。せっかく練り上げた面白い構成も、自信なさげな小さな声や、原稿を読み上げるだけの単調な話し方では、聴衆の心に響きません。
ここでは、聞く人の心をつかみ、3分間決して飽きさせないための、声の出し方、間の取り方、視線といった具体的な実践テクニックを紹介します。
これから紹介する5つの重要なポイントでは、演説の第一印象を決定づける最初の「つかみ」から始まり、自己紹介を本題へスムーズにつなげる技術、ユーモアと真面目さを声色で切り替える方法、聴衆の当事者意識を引き出すエピソードの語り方、そして最後にあなたの思いを焼き付ける「締めの言葉」のデリバリーまでを詳しく解説します。
あなたの演説が、笑いと感動の両方で聴衆を惹きつける、忘れられないスピーチになるための具体的なヒントを学んでいきましょう。
冒頭のつかみで笑いを生むテクニック
生徒会演説の成否は、冒頭の10秒で決まると言っても過言ではありません。この最初の10秒で“空気をつかむ”ことが鍵です。そのために最も効果的なのが、計算された笑いを生む「つかみ」のテクニックです。多くの生徒が緊張して聞いている中、最初に場を和ませる一言を投じることで、聴衆の心理的なバリアを取り払い、あなたの話に一気に引き寄せることができます。
つかみのコツは、大げさなギャグではなく、「身近なあるあるネタ」や「等身大の自分の失敗談」を、少しだけ大げさに、しかし堂々とユーモラスに話すことです。たとえば、
「(マイクの前に立ち、一呼吸置いて)…毎朝、チャイムと同時に教室へ滑り込む私ですが、今日この場所へは、チャイムの5分前に到着しました! そんな私ですが、この学校を“時間厳守の学校”に…ではなく、“ゆとりを持って行動できる学校”に変えたいと思います!」
といったフレーズは、自分をユーモラスに笑いのネタにすることで強い共感を得ながら、それを前向きな印象(公約)へと巧みに転換しています。
また、笑いの“量”も重要です。最初から全力でウケを狙うと、スベった時のリスクが大きすぎます。目指すのは爆笑ではなく、会場全体から「クスッ」という温かい笑いが漏れる程度です。大げさなボケよりも「先生に怒られたけど学んだこと」「部活でのちょっとした恥ずかしい失敗」など、誰もが経験しうるリアルな経験を、少しだけ面白おかしく話すほうが、あなたの「人柄」が伝わり、信頼感を高めます。
さらに、声のトーンと「間(ま)」の取り方が笑いの質を決定づけます。面白いことを言う時こそ、焦って早口にならず、ゆっくり、はっきり、少し間を置いてからオチを言うことで、聴衆が「ん?今なんて言った?」と考える余裕が生まれ、笑いが起こりやすくなります。緊張していても、焦らず堂々と話すことが、面白さとリーダーとしての自信の両立につながるのです。
冒頭の笑いは、単なるジョークではなく「この人の話、もっと聞いてみたい」と聴衆に思わせるための重要な「招待状」です。この「つかみ」を意識的に設計するだけで、あなたのスピーチ全体が、聴衆の記憶に一段と鮮烈に残るものになります。
自己紹介から自然につなぐ話し方のコツ
生徒会演説では、自己紹介が「〇年〇組の〇〇です。生徒会長に立候補しました」という単なる名前や役職の説明で終わってしまうことが非常に多いです。しかし、実はここに“自然な流れ”と“個性”を盛り込むことで、聴衆をグッと惹きつけられます。
ポイントは、自己紹介を単なる挨拶ではなく、「自分のキャラクターや人柄を伝える導入プレゼンテーション」に変えることです。
例えば、
「皆さん、こんにちは。2年A組の〇〇です。クラスでの私のあだ名は“歩く目安箱”です。(ここで笑い)なぜなら、友人から『ちょっと聞いてよ』と、いつも教室で様々な相談や不満を聞いているからです。」
といったように、自分の特技や趣味、あるいはユーモラスなエピソードを交えることで、あなたの「人となり」が伝わり、親しみやすさと強い印象を同時に与えることができます。
そのうえで、自己紹介の直後に「なぜ立候補したのか」という本題の公約へ、違和感なく自然につなげるのがプロのコツです。
「(上記の続き)…でも、そんな“歩く目安箱”として皆さんの声を聞いているうちに、『聞くだけじゃダメだ、本気で学校を変えたい』と強く思うようになり、生徒会に挑戦することを決意しました。」
というように、軽いユーモラスな話題(あだ名)から、本題(立候補の動機)へのスムーズな「橋渡し」を作ることで、聴衆を置いてきぼりにしないスムーズな展開が生まれます。
また、自己紹介部分では“自分をアピールしすぎない”ことも、逆に信頼を得るためには大切です。聴衆は、露骨な自慢話よりも、謙虚さの中にある「本物の自信」を感じ取ります。自分の強みを「私はリーダーシップがあります!」と言葉で誇張するよりも、上記のようなエピソードで「この人なら、みんなの意見を聞いてくれそう」とさりげなく見せる方が、何倍も説得力があります。
自己紹介は単なる形式的な挨拶ではありません。「この人なら信頼できそうだ」「この人の話をもっと聞きたい」と思わせる最初の絶好のチャンスです。自然な流れとユーモアを効果的に組み合わせることで、演説全体の印象が一気にポジティブなものになります。
ユーモアを入れても伝わる本気の伝え方

ユーモアを入れつつも、決して軽く見られず、本気を伝えるには、「笑わせたあとに、間髪入れずに真剣な思いを語る」という流れを作ることが最も重要です。人は笑った直後、心理的なガードが下がり、感情が開いた状態になります。
その瞬間に、あなたの最も伝えたい真剣な言葉を届けることで、そのメッセージは普段以上に深く心に突き刺さります。
例えば、
「(明るいトーンで)僕は掃除当番の日に限って、雑巾を忘れてしまいます。本当にダメですよね。(ここで一呼吸。真剣なトーンに変えて)…でも、生徒会では、皆さんの大切な意見を“忘れない仕組み”を絶対に作ります!」
というように、笑いを生むエピソードの後に、明確な目的や決意を語ることで、「面白いけど、やるべきことはしっかりやる人だ」というポジティブなギャップ(信頼)を生み出すことができます。
ユーモアの入れ方には“順序”が決定的に大切です。先に真面目な公約を延々と語ってから、最後に付け足しのように笑いを挟むと、せっかくの真面目な内容が軽く見えてしまう危険性があります。「フリ(笑い)→オチ(本気)」の順です。笑いを「前座」として使い、その後に続く「本題(信念)」を際立たせるのです。そのギャップこそが、聴衆の心を強く掴みます。
さらに、この「ギャップ」を演出するために、声のトーン、表情、姿勢を意識的に変えることが極めて効果的です。ユーモラスな部分では、少し声を張り、笑顔で身振り手振りを加えて話し、本題の公約を語る部分では、一転して声のトーンを落とし、聴衆の目をまっすぐ見て、落ち着いた声で語りかける。この視覚的・聴覚的な変化によって、聴衆は自然に「ここからが大事な話だ」と感じ取り、あなたの本気度を疑いなく受け取ります。
ユーモアと誠実さのバランスを巧みにコントロールすることで、笑いのある演説でも信頼を失うどころか、むしろ「面白くて頼りになり、人間的な魅力のあるリーダーだ」という最も望ましい印象を残すことができるのです。
聴衆の共感を得るエピソードの盛り込み方
演説で「この人、わかってるな」という深い共感を得るためには、「私はこう思います」という一方的な主張ではなく、「みんなが心の奥底で共通して感じていること(潜在的な不満や願望)」を話題にすることが最も効果的です。人は、自分の経験や感情と重なる話を聞いたときに、初めて「他人事」ではなく「自分事」として心を動かされます。
たとえば、
「(聴衆に問いかけるように)毎朝の校門前の、あの生徒と自転車が入り乱れる混雑、正直ちょっと危ないし、ストレスに感じている人はいませんか?」
というように、多くの生徒が日常的に感じているであろう具体的な不便や課題を、情景が浮かぶように挙げることで、聴衆の意識を「そうだ、そうだ」と一気に引き込みます。
共感を呼ぶエピソードを作るコツは、「個人的な体験(ミクロ)+ みんなへの呼びかけ(マクロ)」という構成です。
「(上記に続けて)実は私も先日、靴箱の前で急いでいる人とぶつかって、教科書を全部ぶちまけてしまいました。(少し間を置いて)…だから、私は生徒会役員として、まずあの場所の動線を見直す提案をしたいです。皆さんの安全と朝の小さなイライラを解消したいのです。」
といったように、自分のリアルな実体験を起点にしつつも、それを「私一人の問題」ではなく「学校全体の課題」として語ることで、聴衆は「自分のためにも、この人に解決してほしい」と、あなたの公約を“自分ごと”として強く受け止めてくれます。
また、こうした共感エピソードを話す際は、感情を込めすぎて大声で訴えるよりも、むしろ少し抑えたトーンで、淡々と、しかし誠実に事実を伝える方が、聴衆の心には深く響きます。過剰な熱意は時に聴衆を引かせてしまいますが、冷静な語り口は「この人は感情的にならず、しっかり問題を見てくれる」という信頼を生むのです。
共感エピソードは、聴衆を一方的な「聞く側」から、あなたと一緒に学校を良くしていく「考える側(当事者)」に変える強力な力を持っています。身近な話題から始めることで、演説の難しい理屈抜きに、自然な共感と強固な信頼を獲得できるのです。
最後に響く締めの言葉で印象に残す方法
演説の最後の一言は、聞き手の心に最も長く、そして強く残るクライマックスです。ここでどんな言葉を選び、どう伝えるかが、あなたの演説全体の印象を決定づけます。
締めの言葉で何よりも大切なのは、「短く、具体的で、前向き(未来志向)であり、聴衆の行動を促す」メッセージにすることです。
たとえば、
「(力強く)私と一緒に、“誰一人取り残さない、笑顔で通える学校”を、本気で作りましょう!あなたの一票を、私に託してください!」
といったフレーズは、具体的(笑顔)で前向き(作る)であり、「一緒に」という一体感を生み出し、「一票を託す」という行動を促すため、聴衆の記憶に強く残ります。
この最後のメッセージを伝える直前に、あえて一瞬の“間(ま)”を置くことで、体育館全体の空気が引き締まり、聴衆が自然にあなたの言葉に耳を傾ける雰囲気を作れます。その一呼吸が、言葉の重みを何倍にも増すのです。
締めのメッセージには、必ず“あなたの信念(コア・メッセージ)”を込めること。
「私は、この学校の誰一人として、自分らしく過ごすことを諦めてほしくありません。そのために、私は全力で行動します。」
というように、演説全体を通して伝えたかった自分の根本的な思いを、最後に改めて明確に伝えることで、聞く人の心を強く動かせます。
最後の一言は、演説の「終わり」ではなく、あなたの活動の「始まり」を感じさせるものにしましょう。聴衆に希望と、学校を変えることへの「参加意識」を促す締めの言葉が、あなたの演説を単なるスピーチから、“聴衆の記憶に永遠に残る伝説のスピーチ”へと変えてくれるのです。
まとめ
この記事で解説してきた、「面白いけど本気が伝わる」生徒会演説のポイントを、改めてまとめます。
- 生徒会演説では、単なる面白さよりも「親しみやすさ」と「等身大の自分らしさ」を重視することが最も大切
- 中学生には、難しい公約よりも、リアルな学校生活の“あるあるネタ”や失敗談が共感を生みやすい
- ウケ狙い(笑い)は目的ではなく、聴衆の心を開き、本題を伝えるための「手段」として戦略的に使うのが効果的
- 面白さの中にも、必ず自分の目標や「学校を良くしたい」という本気の想いを織り込むことが信頼につながる
- 3分間のスピーチでは、公約を一つに絞り、「つかみ(30秒)・展開(2分)・結び(30秒)」の三段構成を意識すると伝わりやすい
- 高校の生徒会では、ユーモアに加えて「公約の具体性」という論理性と、「この人なら」と思わせる人間味の両立が求められる
- ユーモアを入れるなら、他人を傷つけず、自分をネタにする「自虐ネタ」や「あるあるネタ」で共感を得るのがベスト
- 聴衆の共感を得るには、個人的な体験を「みんなの共通課題」として提示し、当事者意識を引き出すこと
- 締めの言葉は短く前向きにし、「私と一緒に学校を変えていこう」という未来への期待と行動を促すメッセージを込める
- 「笑い(緩和)」と「本気(緊張)」のギャップを意識的に作ることで、あなたの演説は聴衆の記憶に強く刻まれる
生徒会演説は、立派な公約を発表する場であると同時に、それ以上に「あなた自身の人柄と情熱を伝える場」です。完璧な原稿を読み上げることよりも、多少言葉に詰まっても、笑いを交えながら自分の言葉で、しっかりとした想いを持って話すことのほうが、何倍も聴衆の心に響く言葉を届けられます。
ウケを狙うことだけに終始せず、ユーモアという「武器」を通してあなたの誠実さ、本気度を伝えることこそが、本当に印象に残り、信頼を勝ち取る演説の最大のコツです。
3分という短い時間に、あなたの個性と情熱、そして学校への愛を込めれば、きっと会場全体が温かい笑顔と深い共感に包まれる、最高のスピーチになるでしょう。




