生徒会演説の準備、いよいよ大詰めですね。演説全体の構成や公約は決まったものの、「最後の締めの言葉がどうしても決まらない…」と頭を悩ませている中学生も多いのではないでしょうか。
演説全体の印象を決定づける締めの言葉は、聴衆の心にあなたの名前と熱意を刻み込むための最も重要なパートです。どんな言葉を選べば自分の本気度が伝わるのか、他の候補者と差をつけるにはどうすればいいのか、考えることは尽きません。
印象に残る演説にするためのコツ、聴衆の心をつかむためのつかみ、そして聞いている人を惹きつける終わりの言葉は、選挙の当落を分けると言っても過言ではありません。
面白いウケ狙いを考えるべきか、それとも真面目に徹するべきか、短い時間でどうまとめるか。また、2回目の立候補や友人の応援演説といった状況によっても、最適な言葉は変わってきます。
この記事では、そのまま使える豊富な例文を交えながら、定番の「ご清聴ありがとうございました」という言葉の効果を最大限に引き出す方法まで、生徒会演説の締めの言葉に関するあらゆる疑問に、具体的かつ丁寧に答えていきます。
なお、公約そのもののアイデアに迷っている場合は、生徒会の公約が思いつかないときの斬新なアイデア出しのコツもあわせて参考にしてみてください。
- 生徒会演説における締めの言葉の重要性と、その効果を最大化するための基本構成
- 聴衆の心に深く響く、印象的な締め方の具体的なコツやテクニック
- 真面目な決意表明、面白いアピール、応援演説など、すぐに使える締めの言葉の例文集
- 演説の評価を下げてしまうNGな締め方のパターンとその対策
生徒会演説の締めの言葉で差がつく基本構成
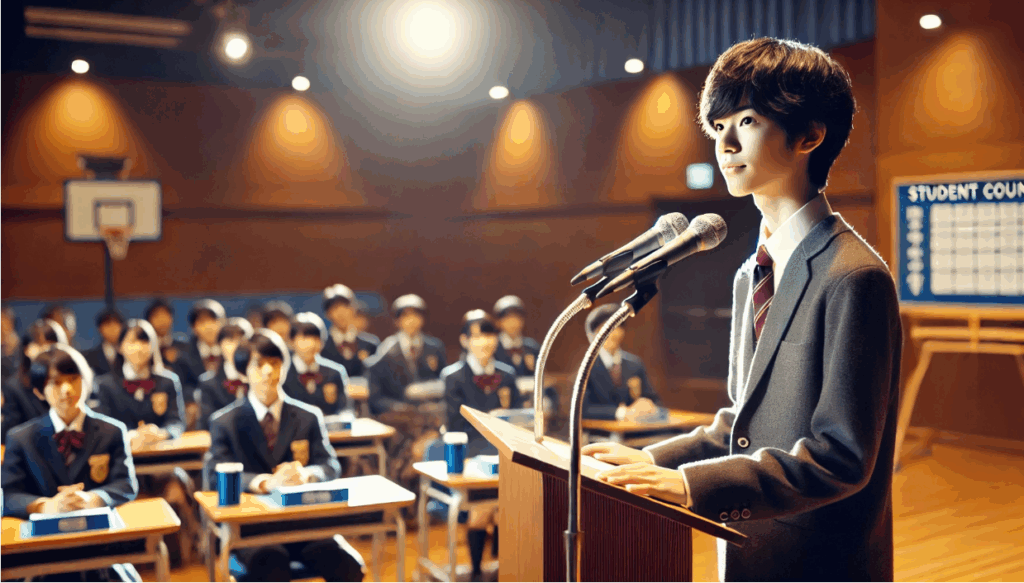
- 印象に残る演説は最初のつかみが肝心
- 中学生にも分かりやすく伝えるコツ
- そのまま使える締めの言葉の例文
- 短い言葉で想いを凝縮させるには
- 面白いウケ狙いで個性をアピール
印象に残る演説は最初のつかみが肝心
生徒会演説の成功を考えるとき、多くの人がクライマックスである「締めの言葉」に意識を集中させがちです。
しかし、その締めの言葉の効果を120%発揮させるためには、演説の冒頭、つまり「つかみ」が決定的に重要になります。なぜなら、人間の集中力が最も高いのは「物事の始まり」だからです。
演説の開始直後の数十秒で聴衆の心を掴めるかどうかが、その後の話を聞いてもらえるか、そして最終的な印象を左右するのです。ここで聴衆の興味を引きつけられなければ、どんなに感動的な締めの言葉を用意しても、BGMのように右から左へと聞き流されてしまうかもしれません。
聴衆の心を開き、話に引き込むための具体的な「つかみ」には、いくつかの効果的なパターンが存在します。
効果的な「つかみ」の5パターン
- ユーモアで心を開く
「心臓の音がマイクに拾われていないか心配です。」といった少し自分をネタにするような一言は、会場の緊張を解きほぐし、あなたへの親近感を一気に高めます。笑いは心の壁を取り払う最も効果的な手段の一つです。 - 問いかけで引き込む
「皆さん、この学校は『自分たちの学校だ』と胸を張って言えますか?」といった、少しドキッとするような問いかけも有効です。聴衆に「自分ごと」として考えてもらうことで、一方的な演説ではなく、対話のような雰囲気を作り出せます。 - 意外な事実や数字を提示する
「昨年度、この学校で出された落とし物の数は、実に130個を超えていたことをご存知でしょうか?」のように、具体的な数字を示すと、聴衆は「え、そうなの?」と興味をそそられます。その後の問題提起にスムーズにつなげることができます。 - 自分のエピソードを語る
「私は入学当初、人前で話すのがとても苦手でした。」というように、自分の弱さや過去の経験を正直に話すことで、人間味あふれる候補者として共感を得やすくなります。 - 名言や印象的な言葉を引用する
「『変化を望むなら、まず自分がその変化になれ』。この言葉に背中を押され、私は今日ここに立っています。」有名な言葉の力を借りることで、演説に重みと説得力を持たせることが可能です。
演説の冒頭、わずか15秒で「お、この人の話は聞いてみたいぞ」と思わせることができれば、勝負は半分決まったようなものです。その勢いを保ったまま、クライマックスの締めの言葉まで駆け抜けましょう。
このように、つかみで聴衆の心をしっかりと掴んでおくことで、演説の最後まで集中力を切らさず、あなたの最も伝えたい締めの言葉を、最高の形で届ける準備が整うのです。
中学生にも分かりやすく伝えるコツ
生徒会演説の聴衆は、社会経験豊富な先生方だけでなく、中学1年生から3年生までの全校生徒です。そのため、一部の人にしか分からない難しい言葉や表現を避け、誰もが直感的に理解できる平易な言葉を選ぶことが、最も重要かつ基本的なコツと言えるでしょう。
どんなに素晴らしい理念や政策を掲げていても、それが聴衆に伝わらなければ意味がありません。難しい四字熟語や、どこかで借りてきたような堅苦しい表現は、かえって「本心で語っていない」という印象を与えてしまう危険性すらあります。
全校生徒の心に響く、分かりやすい演説にするためには、以下の点を常に意識してみてください。
分かりやすく、そして心に響く伝え方の4つのポイント
- 結論から話す(PREP法):「私は、目安箱を各クラスに設置します。なぜなら、全校生徒の小さな声も拾い上げたいからです。例えば…」というように、まず結論(Point)を述べ、次に理由(Reason)、そして具体例(Example)を話し、最後に再び結論(Point)でまとめる構成は、聞き手が話の要点を非常に掴みやすくなります。
- 具体的なエピソードを交える:「いじめのない、明るい学校にします」という抽象的な言葉だけでは、聴衆の心には響きません。「私が1年生の時、一人で困っていたら声をかけてくれた先輩がいました。その時の嬉しさが忘れられません。今度は私が、誰もが安心して過ごせる空気を作ります」のように、あなた自身の体験に基づいた具体的なエピソードを話すことで、言葉に魂が宿り、強い共感を呼び起こします。
- 一文をシンプルに短くする:緊張するとつい早口になり、長い文章を一度に話してしまいがちです。しかし、聞いている側は情報処理が追いつきません。「~で、~だったので、~ということなのですが」と長く続けるのではなく、「~です。だから、~なのです。そして、~ます。」のように、短い文章で区切り、テンポよく話すことを心がけましょう。
- 非言語コミュニケーションを意識する:言葉の内容と同じくらい、伝え方も重要です。少しゆっくり、はっきりとした声で話す。原稿ばかり見るのではなく、会場の奥まで、そして左右の友人たちの顔を見渡しながら語りかける。熱意がこもる部分では、少し身振り手振りを加える。こうした非言語的な要素が、あなたの本気度を何倍にも増幅させて伝えてくれます。
演説全体の構成や話し方の流れをもっと詳しく知りたい人は、生徒会選挙の演説必勝法|票を集める圧倒的戦略と成功ポイントもチェックしておくと安心です。
言葉だけでなく、あなたの表情、声のトーン、視線、ジェスチャー、そのすべてがメッセージになります。原稿をただ暗記して読み上げる「発表会」ではなく、全校生徒一人ひとりの心に向かって「語りかける」という意識を持つことが、心を動かす最高の演説へと繋がるのです。
そのまま使える締めの言葉の例文

「自分らしい言葉が一番」とは言っても、ゼロから考えるのは難しいものです。まずは基本となる型を知り、そこから自分流にアレンジしていくのが成功への近道です。
ここでは、演説で伝えたい方向性や、あなたのキャラクターに合わせて使える締めの言葉の例文を、ポイント解説付きで豊富に紹介します。ぜひ、あなたにぴったりのフレーズを見つける参考にしてください。
| 方向性 | 例文 | ポイントと応用 |
|---|---|---|
| 熱意・覚悟を伝える (リーダーシップを示したい人向け) |
「変えたい、じゃなく『変える』。その覚悟を、今日ここで伝えました。あとは、皆さんの判断に託します。私に、その一票をください。」 | 断定的な言葉で強い意志を示します。「~したい」ではなく「~する」と言い切ることで、聴衆に頼もしさと本気度を感じさせることができます。 |
| 協調性をアピール (みんなと協力したい人向け) |
「私の力は小さいかもしれません。でも、皆さんの力が加われば、この学校はもっと素晴らしい場所に変わると信じています。私に、その『輪の中心』になるチャンスをください。」 | 独善的ではなく、全校生徒と手を取り合って進みたいという姿勢を示します。「輪の中心」「架け橋」といった言葉を使うと、イメージが伝わりやすくなります。 |
| 誠実さ・謙虚さを伝える (縁の下の力持ちタイプ向け) |
「私は、誰よりも大きな声で挨拶をすることしかできないかもしれません。でも、その小さな行動から学校を変えていけると本気で信じています。どうか、私のこの想いを、あなたの一票で後押ししてください。」 | 等身大の自分を正直に伝えつつ、ひたむきな想いを語ることで、応援したいという気持ちを引き出します。具体的な行動を挙げるのがポイントです。 |
| 未来への希望を示す (ビジョンを語りたい人向け) |
「『どうせ変わらない』。そんな言葉が聞こえない学校にしたい。皆さんの意見が主役になる学校を作ります。あなたの一票で、その新しい物語を始めさせてください。」 | 現状への問題意識と、それを乗り越えた先の明るい未来像を提示します。「新しい物語」「次のページ」など、未来を連想させる言葉が効果的です。 |
| ユニークさで記憶に残す (個性を出したい人向け) |
「私の夢は、生徒会の伝説になることです。まずは、伝説の始まりとなる一票を、私にお願いします!」 | 少し大げさで面白い表現を使うことで、他の候補者との差別化を図ります。ただし、キャラクターに合っていないとスベる可能性もあるため注意が必要です。 |
【重要】アレンジを忘れずに!
これらの例文は非常に強力ですが、そのまま使うと「どこかで聞いたことがあるな」と思われてしまう危険性があります。必ず、「なぜ自分がそう思うのか」という具体的なエピソードや、「どんな学校にしたいのか」というあなた自身のビジョンを付け加えて、世界で一つだけの、あなたの言葉に昇華させてください。
短い言葉で想いを凝縮させるには
生徒会演説の時間は、多くの場合1分から3分程度と非常に限られています。この短い時間の中で、自分の想いの全てを伝えようと情報を詰め込みすぎると、結局何が言いたいのかがぼやけてしまい、聴衆の記憶には何も残らないという最悪の結果になりかねません。
短い言葉で聴衆の心に深く想いを刻み込むには、「最も伝えたい核心的なメッセージを、たった一つに研ぎ澄ます」という、いわば「言葉の断捨離」が不可欠です。
例えば、あなたの公約が「挨拶の活性化」「目安箱の設置」「行事の改善」の3本柱だったとしても、締めの言葉でその全てに再び触れる必要はありません。
演説全体を通して伝えたかった理念、例えば「生徒が主役の学校」という核心的なメッセージを、最後に象徴するような一つのキーワードやインパクトのあるフレーズに凝縮させるのです。
想いを凝縮させるための具体的なテクニックは、以下の通りです。
メッセージを凝縮させる3つのテクニック
- キャッチフレーズ化する
「動く生徒会へ。変わる学校へ。」のように、対比を使ったり、リズミカルな言葉を選んだりすることで、聴衆が口ずさめるような覚えやすいフレーズになります。これは演説後も記憶に残り、投票行動に直結する可能性を高めます。 - 断定形で力強く言い切る
「~を実現できたらいいな、と考えております」といった弱々しい表現は、聴衆に不安を与えます。「この学校を、日本一楽しい学校にしてみせます!」と力強く言い切ることで、あなたの覚悟と揺るぎない決意が伝わり、頼もしさを感じさせます。 - 聴衆への問いかけで締めくくる
「皆さんも、そんなワクワクする学校を、一緒に作っていきませんか?」と問いかけることで、演説を一方的なアピールの場で終わらせず、聴衆を「学校づくりの当事者」として巻き込むことができます。これにより、強い一体感と共感が生まれます。
豆知識:1分間の魔法
人が心地よく聞けるスピーチのスピードは、1分間におよそ300字と言われています。これは、一般的な400字詰め原稿用紙の4分の3程度です。短い演説の原稿を作成する際は、この文字数を目安に、本当に伝えたいことは何か、削ぎ落とせる部分はないか、何度も見直す作業が極めて重要です。
情報をあれもこれもと欲張って詰め込むのではなく、あえて「言わない」勇気を持つこと。それが、短くても深く、力強いメッセージを生み出すための秘訣なのです。
面白いウケ狙いで個性をアピール
緊張感に包まれがちな生徒会演説の場で、「面白いウケ狙い」を巧みに取り入れることは、非常に効果的な差別化戦略になり得ます。成功すれば、他の真面目な候補者たちの中であなたの存在は際立ち、聴衆に強烈なインパクトを残すことができます。
「あの面白い人だ!」と覚えてもらうことは、投票において大きなアドバンテージとなるでしょう。しかし、これは同時に大きなリスクを伴う諸刃の剣でもあります。一歩間違えれば、「ふざけているだけ」「生徒会を軽く見ている」という致命的なネガティブイメージを与えかねません。
ウケ狙いに挑戦する前に、そのメリットとデメリットを天秤にかけ、冷静に判断することが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ 会場の空気が一気に和み、その後の話を聞いてもらいやすくなる。 | ❌ 完全にスベった場合、会場が凍りつき、演説を続けるのが精神的に辛くなる。 |
| ✅ 強い個性とユーモアのセンスをアピールでき、聴衆の記憶に残りやすい。 | ❌ 「不真面目」「軽い」という印象を与え、候補者としての信頼を失う可能性がある。 |
| ✅ 「この人が生徒会に入ったら面白そう」という期待感を抱かせることができる。 | ❌ ネタの内容によっては、一部の生徒や先生を不快にさせてしまう危険性がある。 |
もしウケ狙いをするのであれば、「自分を少し下げる」タイプの自虐ネタが比較的安全でおすすめです。「緊張で手汗がすごく、さっき原稿が少しふやけました(笑)。でも、それくらい今日の演説に本気です!」のように、自分の弱さや失敗談を正直に話し、そこから真面目な決意表明へと繋げると、人間味が出て共感を呼びやすくなりますよ。
最も大切な心構えは、笑いを取ること自体をゴールに設定しないことです。あくまでユーモアは、あなたの本気のメッセージを聴衆の心に届けるための「潤滑油」や「スパイス」であるという意識を忘れてはいけません。
【警告】絶対に避けるべきNGネタ
面白い演説と、ただの悪ふざけは全くの別物です。以下のネタは、百害あって一利なしなので絶対に避けましょう。
- 内輪ネタ:特定の友人グループやクラスでしか通じないネタは、大半の生徒を置いてけぼりにし、白けさせてしまいます。
- 誰かをいじるネタ:先生や特定の生徒をからかうような発言は、いじめと受け取られかねません。絶対にやめましょう。
- 過度な下ネタや悪ノリ:品位を疑われ、生徒の代表としてふさわしくないと判断されます。
誰もが安心して笑える「学校あるある」や、前向きな自虐ネタなど、健全なテーマを選ぶようにしてください。挑戦する際は、必ず事前に複数の友人や先生に原稿をチェックしてもらい、客観的な意見をもらうことを強く推奨します。
応用編!生徒会演説の締めの言葉のポイント

- 2回目の立候補で経験を語る締め方
- 候補者を勝たせる応援演説の締め
- 「ご清聴ありがとうございました」の注意点
- 決意が伝わる終わりの言葉の選び方
- あなたらしい生徒会演説の締めの言葉の見つけ方
2回目の立候補で経験を語る締め方
2回目の立候補、つまり現役の生徒会役員としての演説は、初挑戦の候補者とは全く異なる強みを持っています。それは、1年間の活動で得た「経験」と「実績」という、誰にも真似できない説得力です。締めの言葉では、その具体的な経験を語り、単なる経験者ではなく「即戦力」としてさらに学校を良くしていける存在であることを力強くアピールする必要があります。
「この経験を活かして頑張ります」という漠然とした言葉では、あなたの価値は伝わりません。過去1年間の活動を通して、「具体的に何を見て」「何を学び、感じ」「だからこそ、次はこうしたい」という、過去・現在・未来を繋ぐ明確なストーリーを伝えましょう。
経験者の説得力を最大化する締めの言葉の構成例
- 具体的な実績の提示
「私はこの一年間、書記として毎月の生徒会新聞の発行を担当し、ベルマークやインクカートリッジの回収活動にも力を入れてきました。」
→まず、自分が何をしてきたのかを具体的に述べ、責任感と実行力を示します。 - 活動から得た課題の発見
「しかし、その活動の中で、皆さんの素晴らしい意見が生徒会まで届く前に埋もれてしまっている現状を目の当たりにし、悔しい思いをしました。」
→ただ活動しただけでなく、そこから学校全体の課題を見つけ出す洞察力があることをアピールします。 - 経験に基づく今後の展望
「この経験があるからこそ、私には分かります。来期は、目安箱の意見一つひとつに生徒会からの返事を新聞で特集するなど、皆さんの声が『形になる』仕組みを必ず作ります。」
→過去の経験が、未来の具体的な行動計画にどう繋がるのかを明確に示し、実現可能性の高さを感じさせます。 - 力強い決意表明
「先輩方が築き上げてこられたこの〇〇中学校の伝統を、今度は私が受け継ぎ、さらに発展させる覚悟です。どうか、私にもう一度、皆さんのために働くチャンスをください。」
→継続して学校に貢献したいという強い意志と責任感を、自信を持って語ります。
このように、過去の実績と未来へのビジョンを一本の線で繋げることで、あなたは「学校の課題を深く理解し、具体的な解決策と熱意を持つ、唯一無二の候補者」であることを証明できます。
「学校は生徒が作り上げていくもの」という当事者意識と、誰よりもこの学校を愛しているという想いを、あなたの言葉で語りましょう。
候補者を勝たせる応援演説の締め
応援演説者に与えられた使命は、ただ一つ。それは「あなたが心から信じる候補者を、必ず当選させること」です。
そのため、応援演説の締めの言葉は、聴衆が投票用紙に名前を書くその瞬間、「やっぱり、この人しかいない」と最終的に決断させるための、最も強力な一押しとなるメッセージでなければなりません。
そのために最も重要なのは、候補者の人柄や能力がいかに素晴らしいかを語るだけでなく、その素晴らしさが、聴衆である全校生徒一人ひとりにとって、どのような大きなメリット(利益)をもたらすのかを、具体的に、そして情熱的に示すことです。
心を動かす応援演説の締めのポイント
- 「私」の視点で語る
「彼はリーダーシップがあります」と客観的に言うよりも、「私は、彼がクラスの揉め事を解決してくれた姿をこの目で見ました。彼の言葉には、人を動かす力があります」と、あなた自身の具体的なエピソードを交えて語ることで、言葉の信憑性が格段に増します。 - 聴衆のメリットに変換する
「〇〇さん(候補者)の誰にでも優しい性格は、私たちの学校から『一人ぼっち』をなくしてくれるはずです。彼(彼女)が生徒会に入れば、この学校は、今よりもっと温かい場所になると私は確信しています。」のように、候補者の長所を全校生徒の利益に繋げて語ります。 - 最後は力強く、明確にお願いする
「どうか、私たちの未来を、〇〇さんに託してください。〇〇くんに、皆さんの清き一票を、よろしくお願いいたします!」と、自信を持って、ストレートに投票をお願いすることで、あなたの本気度が伝わります。
応援演説の原稿をゼロから作りたい場合は、生徒会選挙の応援演説の例文|中学生・高校生別の面白ネタとスピーチ術で、全体の構成や具体的な例文も確認しておくとイメージしやすくなります。
応援演説で絶対にやってはいけないのが、自分自身が目立ちすぎてしまうことです。あくまで主役は候補者。あなたの役割は、最高のスポットライトを候補者に当てることです。ユーモアを交える際も、候補者の魅力を引き立てるような内容を心がけましょう。
あなたの心からの言葉で、候補者の隠れた魅力や真摯な人柄を語り、彼(彼女)がどれほど信頼に足る人物であるかを熱意を持って伝えること。それが聴衆の心を動かし、友人を勝利へと導く、貴重な一票へと繋がるのです。
「ご清聴ありがとうございました」の注意点

「ご清聴ありがとうございました」という言葉は、演説の締めくくりとして非常に一般的であり、丁寧で礼儀正しい印象を与えることができます。
しかし、その使い方を一つ間違えるだけで、それまでの熱のこもった演説全体の印象を台無しにしてしまうほどの、大きな影響力を持つ言葉でもあるため、細心の注意が必要です。
最も避けなければならないのは、この感謝の言葉だけで演説を唐突に終えてしまうことです。例えば、「…以上の公約を実現します。ご清聴ありがとうございました。」と、まるで定型文のようにあっさりと終わってしまうと、どこか他人行儀で形式的な印象を与え、「本当に当選したいのだろうか?」と聴衆に思わせてしまうかもしれません。
【比較】締めの言葉 NGパターンとOKパターン
❌ NG例(熱意が伝わりにくい)
「皆さんと一緒に、より良い学校にしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。」
✅ OK例(決意と感謝が伝わる)
「この学校を、生徒一人ひとりが『明日も来たい!』と心から思える場所にしてみせます。どうか、私、〇〇に皆さんの大切な一票を、よろしくお願いいたします。(一呼吸おいて、聴衆全体を見渡してから)ご清聴ありがとうございました。」
このように、「ご清聴ありがとうございました」を述べる直前に、「最後のお願い(投票依頼)」や「最も伝えたい決意表明」といった、演説の核心となるメッセージを必ず挿入するようにしましょう。この力強い一言があるだけで、あなたの言葉は聴衆の心に深く突き刺さり、強い印象を残すことができます。
さらに、この言葉を口にする際の「非言語的要素」も極めて重要です。決意表明を述べた後、少しだけ「間」を作り、一呼吸おいてから、ハッキリとした、しかし穏やかな声で「ご清聴ありがとうございました」と述べます。そして、聴衆全体をゆっくりと見渡し、感謝の気持ちを込めて深々とお辞儀をする。
この一連の流れるような所作が、あなたの誠実さと感謝の心を雄弁に物語り、演説を完璧に締めくくるのです。
決意が伝わる終わりの言葉の選び方
演説の「終わりの言葉」は、スピーチの最後のフレーズであり、聴衆の記憶に最も鮮明に焼き付く部分です。心理学でいう「ピーク・エンドの法則」の通り、人々は物事の最も感情が動いた部分(ピーク)と、最後の部分(エンド)を強く記憶します。
つまり、ここで力強いメッセージを伝えられるかどうかで、選挙の結果が大きく左右されると言っても過言ではありません。あなたの決意を聴衆の心に届けるためには、ポジティブで、行動的、そして未来志向の、エネルギーに満ちた言葉を選ぶことが絶対条件です。
曖昧な表現や自信のなさそうなネガティブな言葉は、候補者としての信頼性を損ないます。聴衆が「この人に任せたい」と心から思えるような、自信に満ちた言葉を選びましょう。
| ❌ 避けるべき弱気な言葉の例 | ✅ 推奨する力強い言葉の例 |
|---|---|
| 「もし当選できたら、~を実現できたらいいなと思います」 | 「私に任せてください。必ず~を実現してみせます」 |
| 「私のような未熟者がどこまでできるか分かりませんが…」 | 「私にできることは小さいかもしれません。だからこそ、皆さんの力を貸してください」 |
| 「精一杯頑張りますので、よかったら投票してください」 | 「この学校の未来を、皆さんと一緒に、この手で作り上げていきたいです」 |
特に、「~してみせます」「~することを約束します」といった、未来への強い意志を示す断定的な表現は、候補者の揺るぎない覚悟と責任感を示す上で非常に効果的です。また、「私にそのチャンスをください」「あなたの一票で学校を変えさせてください」といった、聴衆に具体的な行動を促す言葉も、投票へと直接結びつきやすい強力なフレーズです。
そして、技術的なこと以上に最も大切なのは、その言葉が、誰かの受け売りやテンプレートではなく、あなた自身の本心から湧き出たものであることです。あなたが立候補を決意した時の熱い想い、この学校を本当に良くしたいと願う純粋な気持ち、それを飾らない言葉で表現してください。
心の底からの言葉は、どんな美辞麗句よりも強く、必ず聴衆の心に響くはずです。
あなたらしい生徒会演説の締めの言葉の見つけ方まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 生徒会演説の締めは、聴衆の記憶に最も残る、演説全体の印象を決定づける最重要パート
- 締めを成功させるには、演説冒頭の「つかみ」で聴衆の興味関心を引きつけ、話を聞く姿勢を作らせることが不可欠
- 全校生徒が対象であることを忘れず、中学生にも伝わるよう、専門用語や難しい言葉を避け、具体的でシンプルな表現を心がける
- 熱意、協調性、誠実さなど、自分が最も伝えたい方向性に合った例文を参考にしつつ、必ず自分の言葉でアレンジを加える
- 特に短い演説では、伝えたいメッセージを一つに絞り込み、覚えやすくインパクトのあるキャッチーな言葉に凝縮させることが効果的
- 面白いウケ狙いは、成功すれば強い印象を残せるが、不真面目と捉えられ信頼を失う大きなリスクも理解しておく必要がある
- ウケを狙う際は、内輪ネタや誰かを傷つける内容は絶対に避け、誰もが共感でき、かつ自分のメッセージに繋がる健全なテーマを選ぶ
- 2回目の立候補では、具体的な活動実績とそこから見えた課題、そして今後の展望を結びつけて語ることで、経験に裏打ちされた説得力を示す
- 応援演説の締めは、候補者の長所が聴衆全体のメリットにどう繋がるのかを情熱的に訴え、力強く投票を呼びかける
- 「ご清聴ありがとうございました」は感謝を示す大切な言葉だが、その直前に必ず投票のお願いや決意表明を入れ、演説の熱量を保つ
- 終わりの言葉は、「~してみせます」「~を約束します」といった、ポジティブで行動的、かつ未来を感じさせる力強い言葉を選ぶ
- テンプレートや例文に頼りすぎず、自分が立候補した理由や学校への想いといった、自身の経験や感情を乗せた言葉で語ることが最も重要
- 自信を持って、堂々と、時には笑顔で、聴衆一人ひとりの目を見て語りかける姿勢そのものが、あなたの熱意を何よりも雄弁に伝える
- 演説の最終目的は、ただ当選することだけではなく、その先にある「より良い学校を生徒全員で作り上げていく」ことだと忘れない
- 様々なテクニックはあれど、最終的に人の心を最も強く動かすのは、飾らない、あなた自身の本気の言葉である


